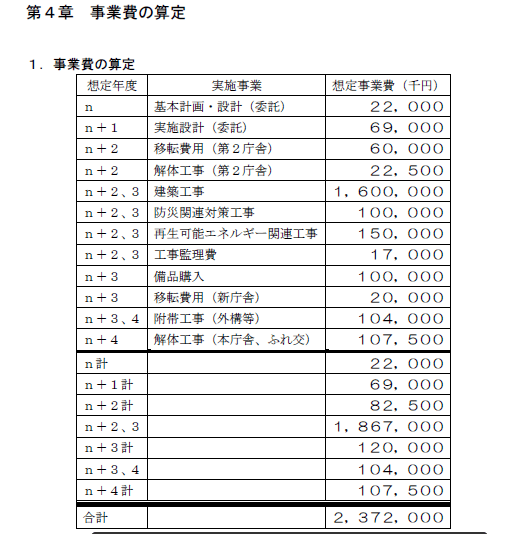
「広さを決める根拠」
役場職員数
第1庁舎(本庁舎)3000㎡ 74名
第2庁舎 900㎡ 46名
公民館の教育委員会 200㎡ 20名
保健福祉センターアイアイ2階1000㎡ 45名
①積み上げ方式 5200㎡ 計185名
②総務省起債許可に係る標準面積 4452㎡
③国土交通省新営一般庁舎面積算定基準 4000㎡
古い一般住宅を耐震化するなら、通し柱の固定アンカー。これが最も費用対効果が高い。
「ホールダウン金物」 。古い家に後づけて取り付けられる。
昭和56年に、この金物の取り付けが義務化された。、それ以前の家は危ない。
器用なお父さんなら日曜大工で
10万以下で取り付けられる
官庁の耐震安全性
官庁施設に対しては、2007年に官庁施設の総合耐震計画基準が定められました。
ここでは、施設の重要度に応じて、I類、II類、III類に分類し、
それぞれ、建築基準法に定める耐力に対して、1.5倍、1.25倍、1倍の強さにすることを求めています。
市役所の本庁舎などはI類とすべき官庁施設だと思われます。
なお、地域によって、地震地域係数が定められており、
東京、大阪、愛知などは1.0、新潟、島根、高知、熊本の一部、大分の一部、宮崎は0.9、
山口、福岡、佐賀、長崎、鹿児島、熊本の一部、大分の一部などは0.8、沖縄は0.7となっています。
静岡だけは、静岡県建築構造設計指針により独自に1.2と定めています
新築する理由
総合化と耐震化
①施設が老朽化している(本庁舎 1968年 築48年)
(第2庁舎 1956年 築60年)
②災害時防災拠点としては耐震基準を満たしていない
(本庁舎は平成6年に耐震補強工事実施済み 費用4500万円)
構造耐震判定指数(Is値) 0.9が望ましいが0.75である。
建物が丈夫でも地震発生時町民の命は守らない 1日何人訪問者がいるか 第1庁舎 1日平均187人
役場が倒壊しても自衛隊がテントで災害本部を作る
③住民サービス向上のため中央公民館や保健福祉センターに
分散している窓口を一本化する
④バリアフリー化の不足(エレベータがない)
2階は企画財政課と総務課、町長室
3階は議会事務局、監査委員室
暮らしに関係する部門は1階にある
成5年の釧路沖地震のとき「ふれあい交流館」1962年 旧 町民児童会館 建設費5338万円 築53年
1200㎡
第2庁舎築60年は被害なし 役場職員が設計
自治体庁舎は、
被害状況の情報収集や避難者対応、
り災証明書発行など災害時の拠点となる
2012年度に耐震化した熊本県益城町(マシキ)の庁舎は震度7の前震、本震によって損壊
災害時に業務を行えるよう業務継続計画を策定し、
別の建物に住民データをバックアップしていたため、住民票発行をすぐに再開でき
災害の本部になるところは一番耐震がしっかりとしないといけない。司令塔がなくなれば、住民の心も折れる。今回はじめて分かった
ふれあい交流館では
社協職員22名
サークル41団体
1階 37団体 350人 2階4団体 180人 が利用している
。
平成7年 1995年 6月 築21年 保健福祉センター 2481㎡ 地上2階 地下1階
第1庁舎は 面積3047㎡ 建設費 1億3800万円 調度品660万円 合計1億4500万円
第2庁舎 面積1000㎡ 地下 1階 地上2階 建設費1400万円
特別養護老人ホーム 芽室けいせい苑 敷地面積 12、036㎡ 3階 延べ床面積 5512㎡
建設費 14億円 定員120床 ショート4床
道補助金31.8% 4億4000万円 町28.5% 4億円 自己資金残り30.7% 5億5000万円
中心街活性化を目的としてスーパー空き店舗活用の自治体もあるようです
ジャスコ渋川店 群馬県渋川市第2庁舎として利用 跡地買取 平成16年
ダイエー鳥取駅南店 鳥取市役所駅南庁舎として利用 平成16年
マルショク杵築店 大分県杵築市 キツキ市 平成12年から市役所として利用
1 計画策定の背景と目的
○我が国は近年、人口減少や少子・高齢化の進行などによる人口構造が大きく変化して
いることに加え、高度経済成長期に整備されてきた公共施設等の社会資本は、老朽化
・耐震性不足に伴う施設の改修や更新、人口減少に伴う施設の統廃合や複合化、施設
更新コスト圧縮のための長寿命化という大きな変革時期が到来しようとしています。
○これまで、本町では行政需要の増大に応じて、小中学校、体育施設、公営住宅、地域
会館などの公共施設(建築物)や道路、橋りょう、上下水道などのインフラ系施設を
集中的に整備し、町民の生活基盤、地域コミュニティの拠点などその役割を果たして
きました。
○しかし、これらの公共施設等は、老朽化の進行や更新時期の到来、人口減少や少子・
高齢化の進行に伴う統廃合や複合化の必要性、大規模災害等への対応など、施設等を
取り巻く環境は大きく変化しており、これらへの対応が迫られています。
○一方、財政面では、人口減少に伴う税収の伸び悩みや社会福祉関連経費の増加に伴う
財政の逼迫が懸念されます。
○このため、これまでと同様の水準で公共施設等への投資を継続していくことは困難に
なると予想され、公共施設等の維持管理にあたっては財政状況を勘案し、今後の方針
を決定する必要があります。
○以上のことから、「芽室町公共施設等総合管理計画」は、様々な社会情勢を踏まえ
公共施設等の全体像を明らかにし、長期的な視点を持って、公共施設等の総合的かつ
計画的な管理を推進することを目的として策定します
3 人口及び財政の状況
(1)人口の推移と将来推計
芽室町では、平成22(2010)年度の国勢調査人口18,901 人をピークに、町独
自推計では、今後は人口が減少し、平成52(2040)年度には、平成22(2010)
年度に比較して、約3,000 人少ない15,790 人と推計されています。
また、高齢化率については、平成22(2010)年度の23.1%から、平成52(2040)
年度には29.5%となり、年少人口(0 歳から14 歳)の比率が16.3%から13.8%
に、生産年齢人口(15 歳から64 歳)の比率が、60.6%から56.7%に減少するな
ど、少子高齢化が一層進展することが予測されています。
(1)更新必要額
現在、本町に存在する公共施設等(建物・公園・道路・橋りょう)を耐用年数どお
りにすべて更新(建て替え)したとすると、平成27(2015)年度から平成77(2065)
年度までに約1,031 億円と推計されます。これを平成28(2016)年度以降に1 年
ごとに平準化したとすると年間(年平均)にかかる費用は、約21 億円となり、直近
10 年平均公共施設等投資的経費の1.3 倍程度となります。一時期に集中して改修・
更新等の費用がかかることによる財政への負担が懸念されることから、このままの状
態で改修や更新等を行っていくと多額の財源不足に陥る状況にあります。
また、今後人口も減少することが想定されており、人口減少を踏まえた公共施設等
への改修・更新等の費用の平準化に向けた取組が必要となります。











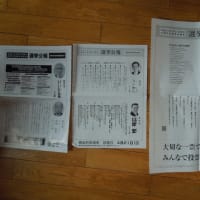

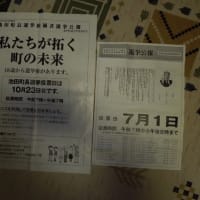

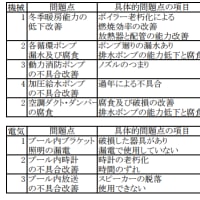
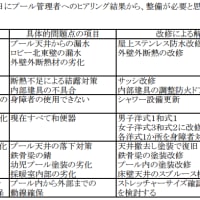
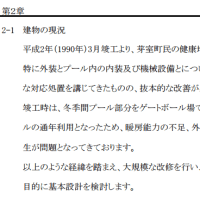


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます