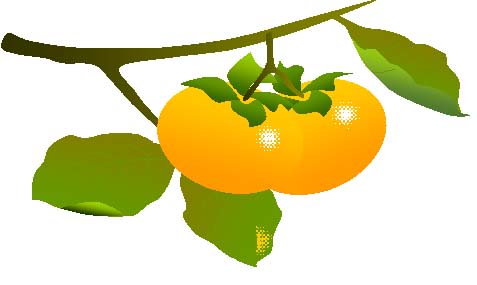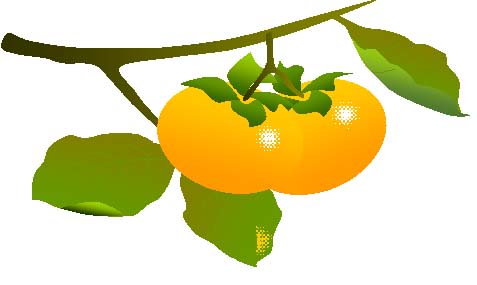11月も下旬になって、秋もそろそろ終わりですね。
毎年、秋になると思い出して気になる歌がありました。 何年か前、NHK夕方の番組で流れていた秋の歌です。
うろ覚えの歌詞で検索して判らなかったのですが、下記の質問コーナーで「秋の子」という歌だということが、ようやく判りました。
質問者、回答者の方、ありがとうございます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129709497
何年も前に出ていたのに辿り着けなかったのは、出だしを知らなかったのと、歌詞の『ハゼ釣りしてる子…』を『影踏みしてる子…』と覚えていたからでした。
でも、この質問者さんも『影踏み』と書いてるから、NHK版では『影踏み』だったのかな? このコーナー、他の歌でも歌詞を変えてたことがあったようです。
作詞はやっぱりのサトウハチローだけど、作曲者が末広恭雄さんと知って、感慨深いものがありました。
故・末広恭雄先生(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AB%E5%BA%83%E6%81%AD%E9%9B%84)はお魚博士として有名だった方。 エッセイの名手で作曲も趣味とされていたことは、よく知られています。
その先生の音楽に関するエッセイに、こんな話がありました。
末広先生が在学する旧制中学校の近所に、大作曲家、山田耕筰先生が住んでおられました。 作曲家志望の末広少年は、ある日、自作の曲の楽譜を持って山田先生のお宅を訪ねました。 山田先生はその曲を見てひとしきり褒めてくれた後、プロの音楽家の厳しさを説いて、音楽は趣味として続けることを勧めてくれました。 その日は一応気を良くして帰った末広少年、上記ウィキペディアには「山田耕筰の弟子」とありますから、その後も時々遊びに行って、音楽の話を聞くなどしていたのでしょう。
さて、末広少年の中学の後輩に、後の作曲家、団伊玖麿氏がいました。 団少年も同じように自作の曲を持って山田先生を訪ねましたが、その楽譜を見た山田先生、すんなりと弟子入りを許したそうです。
後にその話を伝え聞いた末広先生は、あのとき山田先生が自分の曲を褒めてくれたのはお世辞で、本当は自分には才能がなかったのだと悟った、と書いておられます。
そのエッセイを読んだ時、末広先生の音楽を知らなかった私は、そんなもんだろうなと思っていました。
でも、「秋の子」の歌が気になったのは、素朴で親しみやすく、懐かしいようなメロディーがこころに沁みたから。
「先生の歌も素敵ですよ」と、天国の末広先生にお伝えしたいですね。