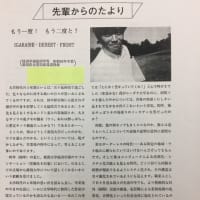●不思議なおばちゃん達と僕(その10) ※「連載初回」はこちら
急死した父に関する諸手続きや気落ちした母の励ましのためもあって、毎週のように実家に帰省するようになったのは、大学進学と共に一人暮らしを始めて以来10年ぶりくらいたった。それに伴って、日常的な買い物や暇な時間の散策などで地元の街中を久々に見て回るようになった。
それまで春の大型連休とか盆暮れの長期休暇の時期に帰省していた時には、商売っ気のない我が田舎の商店街では、大方の店が同様のタイミングで休業していたので、あまり気にならなかったのだが、"平時"の街なかは僕が暮らしていた高校生までとは大きく変わり始めていた。
端的に言うと商店街の衰退が深刻だなあということだ。平成5年のその頃は、いわゆるバブルが崩壊した直後であったのだか、正直なところ僕が住んでいる地方都市や実家のあった小さな街では、大都会のような異常ともいえる経済社会の高揚は無かったし、地元の商店街は、普段使いの商品を中心とした地元住民向け商店の集積地であったので、"あぶく銭"が蒸散したことによる景気後退が決定的な打撃を与えたとは思えなかった。
週末の書き入れ時にも締まるシャッターの並びを見ていると、その表面はずいぶん錆びて久しい趣だ。住宅地にある僕の実家の近くで、鉄道ローカル線の駅の直ぐ前に、僕が中学生の頃に華々しくオープンしたショッピングモール"ファミリーデパート"などは、近接する高校への通学生もいるので安定集客を見込める良い立地だと思っていたが、僕が地元を離れた直ぐ後の昭和時代の後半には閉店してしまっていた。
実家暮らしの高校生時代は、移動手段といえば自転車で、寝坊して学校に遅刻しそうだとか少し急ぐ時に原付バイクの"ヤマハメイト"を駆っていたくらいで、あまり行動範囲が広くなかった。色々なところに遠出する学友もいたが、中学までの部活動漬けの毎日に続いて、高校生時代にあまり成績が良くなかった僕は早期から大学受験勉強を意識していたこともあり、手近な街なかで用事を済ますことが多かった。なので、地元の郊外の変わりようとその影響に気が付くのは、自分自身もそのターゲットとなる自家用車のドライバーとして、郊外の大型店やチェーン店を訪れる機会が増えたこの頃であり、勤めて数年後して父の亡くなった平成初期だったというわけだ。
全国各地を同じような風景にしてしまう郊外型の大型小売店の乱立は、車で出掛けることの効率性や遊興も兼ねられるという魅力から、マイカーデフォルト世代といえる僕の少し上くらいの世代の需要をわしづかみにしていった。それでも、出不精だった僕のような子供や年寄りなど行動範囲の狭い人達には近くの商店街に買い物場所が求められるだろうに。
寂れゆく商店街やシャッターの開かない店舗などについて、地元情報通の母から茶飲み話で聞くと、郊外型の大型店の進撃もさることながら、跡取りになり得る子供達が進学や就職でみな地元を出て行ってしまい商いが続けられないのだという。若手が地元から蒸散していくことで、地元商業界の形勢変化に抗う気力と体力が商店街の店舗から失われていったことが、商店街衰退の何よりも大きな問題だったのだ。
それにしても、己を顧みればなんとも"ばつが悪い"。僕自身が地元活力のための一兵卒とならずに家を出てやりたいようにしてきた手前、地元の衰退を嘆くとは実に勝手なこと極まりないなあとは思う。それでも、平成5年当時は、バブル経済の崩壊で大都会の求人が激減し、新潟も含めた地方へ仕事を求める若者の環流が見られた時期だ。県の人口総数もいまだ右肩上がりと聞いていた。若者の偏在は問題だが、新潟県マクロでは大丈夫であり、未来を担う世代が県内に存在しさえすれば、車社会で育った若者達から好まれる造りへの進化など、コンパクトな商店にもイノベーションがもたらされるだろうし、地域に残り続ける老人も長寿命化して住民総数の減少率が緩慢となり商店街の需要もしばらくは維持されるのではと、楽観的に考えていた。
さて、祖母と父が2年ほどの間に無くなり、気落ちした母も「血圧が高いので医者から突然死するかもと言われた」などと昔から僕を脅していたので、早晩おばちゃん達の面倒も僕の肩に一気に押し掛かるかもというのが大きな懸念の一つだったわけだが、僕の当時の仕事は、父の葬儀の関係で一週間開けて職場復帰してみれば、口を開けた段ボール二箱に決裁文書やら作業が必要な資料やらが山盛りになって待ち構えているほど繁忙を極めていたので、父の死後の対応が一通り終えて母も落ち着くと、実家への帰省の間隔は以前のように少しずつ間が空くようになってきた。
しかしながら、有難いことに、元来気丈な母も独り暮らしの気楽さを楽しめるようになってきたことと、おばちゃん達も、生まれながらの貧乏による質素な生活の賜なのか、大病もしないで安定的に暮らしていてくれたので、僕は次第次第に仕事への専念へと軸足をシフトして行き、地元の衰退への関心も、僕の頭の中では塩漬け気味になっていったのだ。
それでも、"ふるさとを見捨てている感"は頭の隅の黒い斑点のように時折気になってしょうがなくなり始めた。当時の僕は、農林水産部農政企画課という部署に着任したばかりで、稲作の経営効率化を通じた新潟県の農業振興のための政策に関わり始めていたところであり、日々の具体的な実務を通じて、郊外に田園が広がり農家やその関係者が多く住む自分が生まれ育った地元の振興に少なからず寄与していきたい‥、などと言い訳がましいのがせいぜいてあったのだが。
それまで春の大型連休とか盆暮れの長期休暇の時期に帰省していた時には、商売っ気のない我が田舎の商店街では、大方の店が同様のタイミングで休業していたので、あまり気にならなかったのだが、"平時"の街なかは僕が暮らしていた高校生までとは大きく変わり始めていた。
端的に言うと商店街の衰退が深刻だなあということだ。平成5年のその頃は、いわゆるバブルが崩壊した直後であったのだか、正直なところ僕が住んでいる地方都市や実家のあった小さな街では、大都会のような異常ともいえる経済社会の高揚は無かったし、地元の商店街は、普段使いの商品を中心とした地元住民向け商店の集積地であったので、"あぶく銭"が蒸散したことによる景気後退が決定的な打撃を与えたとは思えなかった。
週末の書き入れ時にも締まるシャッターの並びを見ていると、その表面はずいぶん錆びて久しい趣だ。住宅地にある僕の実家の近くで、鉄道ローカル線の駅の直ぐ前に、僕が中学生の頃に華々しくオープンしたショッピングモール"ファミリーデパート"などは、近接する高校への通学生もいるので安定集客を見込める良い立地だと思っていたが、僕が地元を離れた直ぐ後の昭和時代の後半には閉店してしまっていた。
実家暮らしの高校生時代は、移動手段といえば自転車で、寝坊して学校に遅刻しそうだとか少し急ぐ時に原付バイクの"ヤマハメイト"を駆っていたくらいで、あまり行動範囲が広くなかった。色々なところに遠出する学友もいたが、中学までの部活動漬けの毎日に続いて、高校生時代にあまり成績が良くなかった僕は早期から大学受験勉強を意識していたこともあり、手近な街なかで用事を済ますことが多かった。なので、地元の郊外の変わりようとその影響に気が付くのは、自分自身もそのターゲットとなる自家用車のドライバーとして、郊外の大型店やチェーン店を訪れる機会が増えたこの頃であり、勤めて数年後して父の亡くなった平成初期だったというわけだ。
全国各地を同じような風景にしてしまう郊外型の大型小売店の乱立は、車で出掛けることの効率性や遊興も兼ねられるという魅力から、マイカーデフォルト世代といえる僕の少し上くらいの世代の需要をわしづかみにしていった。それでも、出不精だった僕のような子供や年寄りなど行動範囲の狭い人達には近くの商店街に買い物場所が求められるだろうに。
寂れゆく商店街やシャッターの開かない店舗などについて、地元情報通の母から茶飲み話で聞くと、郊外型の大型店の進撃もさることながら、跡取りになり得る子供達が進学や就職でみな地元を出て行ってしまい商いが続けられないのだという。若手が地元から蒸散していくことで、地元商業界の形勢変化に抗う気力と体力が商店街の店舗から失われていったことが、商店街衰退の何よりも大きな問題だったのだ。
それにしても、己を顧みればなんとも"ばつが悪い"。僕自身が地元活力のための一兵卒とならずに家を出てやりたいようにしてきた手前、地元の衰退を嘆くとは実に勝手なこと極まりないなあとは思う。それでも、平成5年当時は、バブル経済の崩壊で大都会の求人が激減し、新潟も含めた地方へ仕事を求める若者の環流が見られた時期だ。県の人口総数もいまだ右肩上がりと聞いていた。若者の偏在は問題だが、新潟県マクロでは大丈夫であり、未来を担う世代が県内に存在しさえすれば、車社会で育った若者達から好まれる造りへの進化など、コンパクトな商店にもイノベーションがもたらされるだろうし、地域に残り続ける老人も長寿命化して住民総数の減少率が緩慢となり商店街の需要もしばらくは維持されるのではと、楽観的に考えていた。
さて、祖母と父が2年ほどの間に無くなり、気落ちした母も「血圧が高いので医者から突然死するかもと言われた」などと昔から僕を脅していたので、早晩おばちゃん達の面倒も僕の肩に一気に押し掛かるかもというのが大きな懸念の一つだったわけだが、僕の当時の仕事は、父の葬儀の関係で一週間開けて職場復帰してみれば、口を開けた段ボール二箱に決裁文書やら作業が必要な資料やらが山盛りになって待ち構えているほど繁忙を極めていたので、父の死後の対応が一通り終えて母も落ち着くと、実家への帰省の間隔は以前のように少しずつ間が空くようになってきた。
しかしながら、有難いことに、元来気丈な母も独り暮らしの気楽さを楽しめるようになってきたことと、おばちゃん達も、生まれながらの貧乏による質素な生活の賜なのか、大病もしないで安定的に暮らしていてくれたので、僕は次第次第に仕事への専念へと軸足をシフトして行き、地元の衰退への関心も、僕の頭の中では塩漬け気味になっていったのだ。
それでも、"ふるさとを見捨てている感"は頭の隅の黒い斑点のように時折気になってしょうがなくなり始めた。当時の僕は、農林水産部農政企画課という部署に着任したばかりで、稲作の経営効率化を通じた新潟県の農業振興のための政策に関わり始めていたところであり、日々の具体的な実務を通じて、郊外に田園が広がり農家やその関係者が多く住む自分が生まれ育った地元の振興に少なからず寄与していきたい‥、などと言い訳がましいのがせいぜいてあったのだが。
(空き家で地元貢献「不思議なおばちゃん達と僕」の「その11」に続きます。)
※"空き家"の掃除日記はこちらをご覧ください。↓
「ほのぼの空き家の掃除2020.11.14」
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
※"空き家"の掃除日記はこちらをご覧ください。↓
「ほのぼの空き家の掃除2020.11.14」
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。