
内地の土佐料理をモチーフにした飲食店で「鰹の藁焼き」を食べることはあっても、藁焼きを実演しているのは一度たりとも見たことのないnobuta。
10月になり、各地でビアフェスが開催されていた某週末のこと。高知市の「鮮魚の和田」さんが首里にて実演販売されるということを聞いて1節購入するために出かけました。






写真のとおりなんですが、藁であぶるんですね~
1節のサイズが豪快過ぎ(笑)
炙って焼き目が付いた鰹1節を包んでいったん冷ました上で受取りです。
1節は、大きいサイズが3,500円、ワンサイズ小さめが3,000円。


土佐の「ひやおろし」も販売されていたので、1本購入したところ、売り手のお姉さんから、藁焼きは
塩
で食べるのが基本であること、
大蒜
を一緒に食べるべしと教えて貰いました。
という事で、自宅に持ち帰って早速カットします(2センチくらいの分厚さ)。
その1部をお皿に盛って、大蒜とお塩で頂きましたよ~

もちろん、1節のサイズ感から、その日では食べきることができず、チルドに入れて2日掛けて食べきったのでした。
藁の燻製の薫りが芳ばしくて美味しかったな~。
沖縄で食べる機会なんて、そうそうあるもんじゃないので感謝ですね!!
美味しかったです。
ご馳走様でした!!!!

高知市西塚ノ原34-1













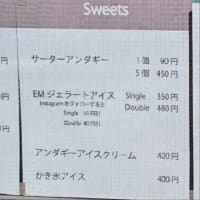






せっかくの楽しいタイミングなのですが、残念なお話を。
昨今、本場の高知、特に中でも本場の久礼町でも本来の「カツオのタタキ」が継承されなくなりつつあります。高知市内の有名な「ひろめ市場」でも同じです。
カツオのタタキ というのは記事の調理の後にそこそこの大皿に切り身(刺し身に作ったカツオ)を敷き詰めて、粗塩をふり冷やした手の甲側で優しく叩いて馴染ませます。もうお解りだと思いますが、叩くからこそタタキなのです。記事の状態では「焼き切り」という状態です。「カツオのタタキ」は焼き切りからの発展系とも言われています。
この基本形では昨今呼ばれている塩味の「塩タタキ」状態です。(注)「塩タタキ」は塩をふっただけです。ここから先の頂き方はほぼ自由です。薬味はニンニク・おろし生姜・刻みネギ・大葉等々で、一切れで薬味をくるんでそのまま頂いても良し、ポン酢をつけても良し、白味噌ベースに葉ニンニクをすりこんだ「土佐のヌタ」「ニンニクヌタ」で頂くも良し、これは葉ニンニクの旬の春の上りカツオのころの新鮮な葉ニンニクがベストかと思います。辛子マヨネーズやワサビマヨネーズという裏技もあったりします。
本来、「カツオのタタキ」は上りカツオのアッサリと脂っ気がないカツオの頂き方と教わって育ちました。秋の下り(戻り)カツオは脂が充分のっているので「お刺身」が良いと言われています。まあ、好みもありますので、それは好きずきで良いと思っています。
ちなみに私はうどん県の爺68です。親類が高知にあったので幼い頃から春と秋のカツオシーズンに交互の家でカツオでお客(宴会)をやっていました。どちらの家もそこそこの広さの庭があったので、そこで藁焼きにしていました。さばくのも外の水道で外でした。当然ながら私も作り方を仕込まれました。
材料・道具・場所が揃えば今でも作れます。
うどん県の「讃岐手打ちうどん」も「カツオのタタキ」と同じく本来の物が継承されなくなりつつあるので気になっていたのでコメントいたしました。
お目汚し失礼しました。
「鰹のたたき」とは奥が深いものなのですね。年末にも、こちらのタタキを頂く機会があるので、実践してみたいと思います。
夫がタタキ大好きなので、このイベントを知っていたら行けばよかったなあ~て思いました。
うどん県の方のコメントも、興味深く読ませていただきました。
なんと高知なんですね!人生で一度だけ、しかも5時間くらい滞在しましたよ(笑)
私は広島出身ですがあんこが苦手なので、ノーマルなもみじ饅頭が食べれませんよ(笑)