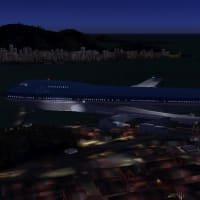カーナビなんか使うのが常識
こんな人は..このゲームに対して愚問が出てくる。
ちなみに..
航空機もカーナビみたいなものはある。
本物にもついているして、実際FSも搭載しているので、
それを使っているとは思うが...
それでも
計器飛行証明という計器飛行の習得にはそれじゃだめ..
専用で使っている航空無線援助設備の習得が必要だ。
さて話は少し飛躍する..
色々な分野に、こんな場所が分かる無線システムは
存在する。
有名どころは船舶用の航法援助設備
ロラン--オメガ--NNSS--GPS
これらはアメリカ海軍が利用するために作ったシステムを..
同盟国のみ..一部機能を民間開放している。
GPSの本来の役目は..
横須賀の空母か..佐世保の潜水艦か..大和の作戦機か..
沖縄の海兵隊の陸上機器に対して使うのが役目である。
詳細はそれぞれ調べてください。
カーナビで使っていて..
かたや..給油反対運動していたり...
でも、米国海軍様システムの一部機能おこぼれ利用なので..
そんな米軍が戦争をやると..
間違いなくカーナビがおかしくなる可能性が高い。
実際イラク戦の初日に民間用は精度が若干落ちたことがある。
何セ..
GPSの精度管理は米国で出来るようになっている。
敵国に使えないようにするのが基本ですからね...
そんなカーナビは
米国海軍機器のお下がりだと認知している人が少ないのには..
本当に困ってしまう。
→本当は位置を知りたいのだ.....

さて...
本題に行こう。
飛行機の操縦室にも場所が分かる計器がある。
が
どう視たらいいのか..
の前に電波物の屁理屈をを考えてみよう..
どの家にも..
ちゃんと電波の到来する向きが分かるものがある。
→ラジオはダイヤル1242 ニッポン放送なのだ.....
→電波探知機なのだ.....
ということだ。
難しく考えない方がいいかも..
基本はこのあたり..あとはコレの応用である。
ところで..
本物テレビ局もそうだけど..
FS無線局はサービスエリアがある。
そのサービスエリア範囲に入らないと
いくら周波数を合わせても
空港手前でATISすら聞けない..
本物操縦の手順みたいに..
かなり手前で事前に仕入れたいんだけど..
ならサービスエリアを広げる手段がある。
それはAFCADに設定項目がある。
通常の無線エリアはL/Mという設定なっている。
これをLLにすればLの倍..約200KM手前からATISを聞くことが出来る。
AFCADは駐機場や滑走路修正だけではない。
無線関係の設定変更も容易に出来る。
→AFCADなのだ.....
だけど..
エリアを広げると混信の問題も考えないといけないことも書いた。
こんな考慮話までFSは本物同様である。
この話は日本の場合..航空局でなく..
総務省の電波管理局の下請機関のARIBとしてやっている。
現在進行中の地デジの中継局設置配置と変わらない。
ということなのだが、
FSゲームというものは..
ただ飛行機の雑学が分かっても駄目。
トータル的に広範囲な雑学が必要になる。
こんな..ごく一部分の話すら
個人的雑学ラベルの差があることに
気がつけばいいのだね..
→ギリギリまで分からないのだ.....

さて..
プレーヤーだけでいいよの人ですら
困ってしまうのが計器飛行の最重要項目。
航空無線援助設備を利用した航法。
実際の飛行機もコレをやっている。
航空路は..
ずばりこの専用無線局間が航空路になっている。
航空路の話も書いたけど..
巡航高度設定も、ルールあり..いい加減ではなかったり..
AI機の巡航高度設定を見れば..出来の良し悪しもわかる。
→道の作り方なのだ.....


※簡単に降りているように見えるけど、こんな御気楽に見えるシーンもご苦労さん
という感じに見えてきたらFSプロパイロットに近づいたのかな..
飛行機には
NDBという方位だけ分かる物と
VOR/DMEといって..方位と距離が分かる物がある。
→基本はラジオ局に向かうのだ.....
以前書いた着陸を思い出していただきたい。
セントマーチンのVOR/DMEを受信して
常時10ノーチカルマイルになるように
飛行すれば..セントマーチンのSTARの円形航路に入るとね..
→STAR/SID.....
そのとき利用する計器がコレ..
VOR/DME
NAV受信機に..事前にセントマーチンの周波数を
付属地図に明記されているので調べて、周波数を設定して受信する。
あとは方位角度の話..
セントマーチン滑走路の向きが96度なっている。
方位96度で10ノーチカルマイル高度1600フィート
ならULUBAという
セントマーチン9滑走路..最終進入点にいることになる。
ここからはILSが受信している。
ちなみにこのポイントは目標地点であり
実際にはこの手前で標準旋回しないといけない。
方位と角度の話は以前書いた。
→セントマーチンで雑学.....
→セントマーチン着陸編.....


ところで
どんな基準での方位角度なのか..知らん人が多い。
単純に地図が北..なんて思っている人もいる。
磁石の向きか..本物の北極点の向きか..
地球は若干歪んだ球体だということも考慮して..
だんだん分からないかも..
ここで書くと頭を使わないので..
ここは宿題にしておく。

※たぶんカーナビみたいな画面をトレース操縦しているだけですかね...
(旅客機の基本は同じかな..)

※天気が悪いと、どこに島があるのかすら分からん...
さて本文に戻る。
そんなセントマーチン局の受信指針が96度近くに
なったら標準旋回で
その向きにヘッダーを合わせるまではやった。
ここに条件が書いてある。
指定高度1600フィート(約500M)
かなり低いのだ..スピードも250ノット以下だけど
車輪を下ろすには230ノット以下でないと降りない。
それで、10ノーチカルを守るよう操縦。
管制無線は入るし、本物より忙しい..
こんな状態でも慣れたらうまく出来る。
ワンマン操縦が簡単でないのは分かるが..
計器操縦といつても、マニュアルで基本的に出来ないと駄目らしい。
あと追記しておくけど..
コレでも本物より楽というか..気象変化を考える必要性がない
本物と同じの通常着陸手法である、楽に出来る自動操縦の道もあるが...
さて、この空港の場合..
ILSが設置されているので
機体をセントマーチンVOR/DME無線局の方位と方位角度が96度になっていたら
ローカライザーに会合している。
あとはPFD画面でILSローカライザーの十字の会合を
キチンと合わせる操縦をすればいい。
こんな過程は付属マチャドスクールでやっているんだが..
この無線航法のアプローチは本物教官も使えると言っている。
なので、パイロットの卵もこのゲームを持参させられ..やっている。
ただし..
この無線の把握する部分が使えるだけで、
実際は気まぐれな気流や変化する気象と戦わないといけない。
こんな計算は家庭用最新スーパー20万円ボロパソでは不可能。
本物シムは現家庭用30台分以上の性能の物を使っているとか...
逆に言うと1/30程度なら..このゲームでも出来るということなのだ...
※PFD..高度/姿勢/速度の表示されている画面
最終段階では滑走路脇のAPAIの表示が進入の正確不正確を知らせてくれる。

※セントマーチンのAPAI少し低すぎと出ている。
でも..暫定運用空港の場合どうなのかなぁ..
表示は極めて簡単..
完全に全部赤だと危険すぎるほど低すぎ..
逆に全部黄色だと完全なる高すぎ..
四灯式の理想は黄色2つ赤2つ..なら正規進入角度に乗っているという意味。
この進入角度表示灯は色々な方式があってAFCADで選択設置変更も出来る。
そんなILSも無線なのでAFCADでいじれる。
以前映画..
ダイハード2でILSローカライザーをいじって
飛行機を墜落させるシーンがあったが
あれができてしまう..
本物はそんな単純じゃないけど、
以前グァムで大韓航空のジャンボが
着陸時に手前の山に激突した事故あった
が、
なんと地上でILSを調整整備中にも関わらず
ノータム等の不確認でILS進入したのが原因であった...
といわれている。

ということなのだ..
他にもNAV1号と2号無線機の使い分け方とかもあるけど
それくらいは自分で考えて使ってくれ。
無線機は通信周波数を
東京--大阪が1CHだけで出来るわけ無い。
Fsも含め現実は空港の中だけで3回も周波数変えている。
まぁ..
コレが面倒とか考えるなら..操縦も..なのかな..
→離着陸管制シーケンスなのだ.....
さらに..
本物も同じだけど..パイロットのフライトプラン航路マップに
そんな周波数がちゃんと記されている。
そんなマップを事前に準備しておくのが
重要かも..
もっと本物パイロット的なら..
そのフライトフラン航路地図に緊急予定着陸空港までの
中間点を記しておくとか..予定燃料消費量とか書いておくとか..
コレくらいは..本物の方は事前にやってあるみたいですよ。
Fsの計器飛行も...
その場しのぎではなく..
雑学習得も含め、
事前の段取りが8割なんですよね..
ゲームですら
宿題だけでなく予習/復習/反省の姿勢を正す日々かな....
こんな人は..このゲームに対して愚問が出てくる。
ちなみに..
航空機もカーナビみたいなものはある。
本物にもついているして、実際FSも搭載しているので、
それを使っているとは思うが...
それでも
計器飛行証明という計器飛行の習得にはそれじゃだめ..
専用で使っている航空無線援助設備の習得が必要だ。
さて話は少し飛躍する..
色々な分野に、こんな場所が分かる無線システムは
存在する。
有名どころは船舶用の航法援助設備
ロラン--オメガ--NNSS--GPS
これらはアメリカ海軍が利用するために作ったシステムを..
同盟国のみ..一部機能を民間開放している。
GPSの本来の役目は..
横須賀の空母か..佐世保の潜水艦か..大和の作戦機か..
沖縄の海兵隊の陸上機器に対して使うのが役目である。
詳細はそれぞれ調べてください。
カーナビで使っていて..
かたや..給油反対運動していたり...
でも、米国海軍様システムの一部機能おこぼれ利用なので..
そんな米軍が戦争をやると..
間違いなくカーナビがおかしくなる可能性が高い。
実際イラク戦の初日に民間用は精度が若干落ちたことがある。
何セ..
GPSの精度管理は米国で出来るようになっている。
敵国に使えないようにするのが基本ですからね...
そんなカーナビは
米国海軍機器のお下がりだと認知している人が少ないのには..
本当に困ってしまう。
→本当は位置を知りたいのだ.....

さて...
本題に行こう。
飛行機の操縦室にも場所が分かる計器がある。
が
どう視たらいいのか..
の前に電波物の屁理屈をを考えてみよう..
どの家にも..
ちゃんと電波の到来する向きが分かるものがある。
→ラジオはダイヤル1242 ニッポン放送なのだ.....
→電波探知機なのだ.....
ということだ。
難しく考えない方がいいかも..
基本はこのあたり..あとはコレの応用である。
ところで..
本物テレビ局もそうだけど..
FS無線局はサービスエリアがある。
そのサービスエリア範囲に入らないと
いくら周波数を合わせても
空港手前でATISすら聞けない..
本物操縦の手順みたいに..
かなり手前で事前に仕入れたいんだけど..
ならサービスエリアを広げる手段がある。
それはAFCADに設定項目がある。
通常の無線エリアはL/Mという設定なっている。
これをLLにすればLの倍..約200KM手前からATISを聞くことが出来る。
AFCADは駐機場や滑走路修正だけではない。
無線関係の設定変更も容易に出来る。
→AFCADなのだ.....
だけど..
エリアを広げると混信の問題も考えないといけないことも書いた。
こんな考慮話までFSは本物同様である。
この話は日本の場合..航空局でなく..
総務省の電波管理局の下請機関のARIBとしてやっている。
現在進行中の地デジの中継局設置配置と変わらない。
ということなのだが、
FSゲームというものは..
ただ飛行機の雑学が分かっても駄目。
トータル的に広範囲な雑学が必要になる。
こんな..ごく一部分の話すら
個人的雑学ラベルの差があることに
気がつけばいいのだね..
→ギリギリまで分からないのだ.....

さて..
プレーヤーだけでいいよの人ですら
困ってしまうのが計器飛行の最重要項目。
航空無線援助設備を利用した航法。
実際の飛行機もコレをやっている。
航空路は..
ずばりこの専用無線局間が航空路になっている。
航空路の話も書いたけど..
巡航高度設定も、ルールあり..いい加減ではなかったり..
AI機の巡航高度設定を見れば..出来の良し悪しもわかる。
→道の作り方なのだ.....


※簡単に降りているように見えるけど、こんな御気楽に見えるシーンもご苦労さん
という感じに見えてきたらFSプロパイロットに近づいたのかな..
飛行機には
NDBという方位だけ分かる物と
VOR/DMEといって..方位と距離が分かる物がある。
→基本はラジオ局に向かうのだ.....
以前書いた着陸を思い出していただきたい。
セントマーチンのVOR/DMEを受信して
常時10ノーチカルマイルになるように
飛行すれば..セントマーチンのSTARの円形航路に入るとね..
→STAR/SID.....
そのとき利用する計器がコレ..
VOR/DME
NAV受信機に..事前にセントマーチンの周波数を
付属地図に明記されているので調べて、周波数を設定して受信する。
あとは方位角度の話..
セントマーチン滑走路の向きが96度なっている。
方位96度で10ノーチカルマイル高度1600フィート
ならULUBAという
セントマーチン9滑走路..最終進入点にいることになる。
ここからはILSが受信している。
ちなみにこのポイントは目標地点であり
実際にはこの手前で標準旋回しないといけない。
方位と角度の話は以前書いた。
→セントマーチンで雑学.....
→セントマーチン着陸編.....


ところで
どんな基準での方位角度なのか..知らん人が多い。
単純に地図が北..なんて思っている人もいる。
磁石の向きか..本物の北極点の向きか..
地球は若干歪んだ球体だということも考慮して..
だんだん分からないかも..
ここで書くと頭を使わないので..
ここは宿題にしておく。

※たぶんカーナビみたいな画面をトレース操縦しているだけですかね...
(旅客機の基本は同じかな..)

※天気が悪いと、どこに島があるのかすら分からん...
さて本文に戻る。
そんなセントマーチン局の受信指針が96度近くに
なったら標準旋回で
その向きにヘッダーを合わせるまではやった。
ここに条件が書いてある。
指定高度1600フィート(約500M)
かなり低いのだ..スピードも250ノット以下だけど
車輪を下ろすには230ノット以下でないと降りない。
それで、10ノーチカルを守るよう操縦。
管制無線は入るし、本物より忙しい..
こんな状態でも慣れたらうまく出来る。
ワンマン操縦が簡単でないのは分かるが..
計器操縦といつても、マニュアルで基本的に出来ないと駄目らしい。
あと追記しておくけど..
コレでも本物より楽というか..気象変化を考える必要性がない
本物と同じの通常着陸手法である、楽に出来る自動操縦の道もあるが...
さて、この空港の場合..
ILSが設置されているので
機体をセントマーチンVOR/DME無線局の方位と方位角度が96度になっていたら
ローカライザーに会合している。
あとはPFD画面でILSローカライザーの十字の会合を
キチンと合わせる操縦をすればいい。
こんな過程は付属マチャドスクールでやっているんだが..
この無線航法のアプローチは本物教官も使えると言っている。
なので、パイロットの卵もこのゲームを持参させられ..やっている。
ただし..
この無線の把握する部分が使えるだけで、
実際は気まぐれな気流や変化する気象と戦わないといけない。
こんな計算は家庭用最新スーパー20万円ボロパソでは不可能。
本物シムは現家庭用30台分以上の性能の物を使っているとか...
逆に言うと1/30程度なら..このゲームでも出来るということなのだ...
※PFD..高度/姿勢/速度の表示されている画面
最終段階では滑走路脇のAPAIの表示が進入の正確不正確を知らせてくれる。

※セントマーチンのAPAI少し低すぎと出ている。
でも..暫定運用空港の場合どうなのかなぁ..
表示は極めて簡単..
完全に全部赤だと危険すぎるほど低すぎ..
逆に全部黄色だと完全なる高すぎ..
四灯式の理想は黄色2つ赤2つ..なら正規進入角度に乗っているという意味。
この進入角度表示灯は色々な方式があってAFCADで選択設置変更も出来る。
そんなILSも無線なのでAFCADでいじれる。
以前映画..
ダイハード2でILSローカライザーをいじって
飛行機を墜落させるシーンがあったが
あれができてしまう..
本物はそんな単純じゃないけど、
以前グァムで大韓航空のジャンボが
着陸時に手前の山に激突した事故あった
が、
なんと地上でILSを調整整備中にも関わらず
ノータム等の不確認でILS進入したのが原因であった...
といわれている。

ということなのだ..
他にもNAV1号と2号無線機の使い分け方とかもあるけど
それくらいは自分で考えて使ってくれ。
無線機は通信周波数を
東京--大阪が1CHだけで出来るわけ無い。
Fsも含め現実は空港の中だけで3回も周波数変えている。
まぁ..
コレが面倒とか考えるなら..操縦も..なのかな..
→離着陸管制シーケンスなのだ.....
さらに..
本物も同じだけど..パイロットのフライトプラン航路マップに
そんな周波数がちゃんと記されている。
そんなマップを事前に準備しておくのが
重要かも..
もっと本物パイロット的なら..
そのフライトフラン航路地図に緊急予定着陸空港までの
中間点を記しておくとか..予定燃料消費量とか書いておくとか..
コレくらいは..本物の方は事前にやってあるみたいですよ。
Fsの計器飛行も...
その場しのぎではなく..
雑学習得も含め、
事前の段取りが8割なんですよね..
ゲームですら
宿題だけでなく予習/復習/反省の姿勢を正す日々かな....