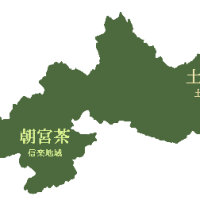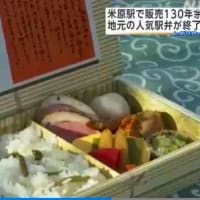目にも鮮やかなこの蕪(カブラ)のルーツは永禄年間(1560年頃)。織田信長が守山市矢島町で寺院を焼き討ちした後、その地に蕪の種を播いたところ、彩りの良いものができたという逸話が残っている。そんな歴史ある野菜だが、元々は「矢島かぶら」と呼ばれ、矢島町内でしか栽培されていなかった。特徴的な蕪の形と色合いは、この町でしか再現できないと思われていたのだそうだ。そうした歴史的背景もあり、広く流通することはなく、長い間、地元農家の手によって細々と栽培が続けられてきた。
そんな「矢島かぶら」の生産に転機が訪れたのは2016年のこと。生産者の高齢化による絶滅を危惧した地元農家と、守山市が発足した「もりやま食のまちづくりプロジェクト」の呼び掛けにより、守山市広域での試験栽培がスタートした。結果、守山市矢島町以外でも生産できたことから、名称も「守山矢島かぶら」に変更。
「守山矢島かぶらの会」が設立され、本格的な栽培・流通の取り組みが始まった。今後は守山市の「特産品」を全国的に有名な「名産品」へと期待が高まる。

「漬物」にすると葉から色が出て、見た目も綺麗に仕上がるという「守山矢島かぶら」。なんと、元々葉は食用ではなく、「染料」として使われていたそうである。
只、外見上、違うのは「守山矢島カブラは球形」、一方、「日野菜は細身の大根形」と明らかに違う。守山矢島かぶらは交配を繰り返すと、「日野菜」や大根のような太さのかぶらができることもあるといい、特徴的な外見を持つ伝統野菜ならではの難しさが窺える。
日野菜(ひのな)

太陽光が当たった部位に赤い色素を生合成する性質を有した、食用のカブの品種の1つである。「滋賀県日野町」が原産地と言われているために、この名で呼ばれるものの、別名として、日野菜カブ(ひのなかぶ)」や「赤菜(あかな)」と呼ばれる事例も見られる。
主な食べ方としては、色素を活かした漬物にしてから食べる方法が知られており、「日野菜の漬物」は、滋賀県日野町の「特産品」として知られる。すなわち、日本各地で品種の栽培が途絶えた事例が起きてきたものの、それらの品種とは異なり、21世紀に入ってからも日野菜の栽培は継続されている上に、漬物の製法も継承され続けている。
「守山矢島かぶら」は9月中旬頃に種まきをして、早ければ11月下旬から収穫を始める。蕪(カブラ)のきめが細かいので、漬物やおでん、みそ汁にサラダなど、どんな料理にもよく合う。この「守山矢島かぶら」は守山市内のJA直売所「JAレーク滋賀 ファーマーズ・マーケット おうみんち」などで2月上旬頃まで販売される。