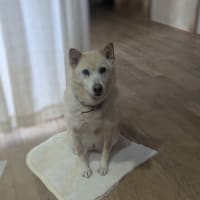少し前の出来事ですが、ちょっと考えを纏める機会がありましたので、あげておきます。
1.事の発端
■温又柔『真ん中の子どもたち』
・集英社、2017年。初出:『すばる』2017年4月号
・第157回芥川賞候補作。
台湾人の母親、日本人の父親をもち、東京で育った主人公の「私」が、上海に語学留学したときの経験を回想形式で語る。
「母国語」とは何か、国家とは何かという疑問と葛藤から、自分たちは複数の国家の間で自らの言葉を模索する「真ん中の子ども」であるという思いに辿り着く。
この作品について、芥川賞選考委員の一人である宮本輝が、以下のような選評を述べました。
■宮本輝「カモフラージュ」
当事者たちには深刻なアイデンティティと向き合うテーマかもしれないが、日本人の読み手にとっては対岸の火事であって、同調しにくい。なるほど、そういう問題も起こるのであろうという程度で、他人事を延々と読まされて退屈だった。
(芥川賞選評、『文芸春秋』2017年9月特別号、383頁)
これについて温又柔さんご本人がTwitter で、
■温又柔 Twitter
@WenYuju
どんなに厳しい批評でも耳を傾ける覚悟はあるつもりだ。でも第157回芥川賞某選考委員の「日本人の読み手にとっては対岸の火事」「当時者にとっては深刻だろうが退屈だった」にはさすがに怒りが湧いた。こんなの、日本も日本語も、自分=日本人たちだけのものと信じて疑わないからこその反応だよね。
10:16 - 2017年8月11日
と書いて、ちょっとした騒ぎになりました。
2.問題点
この宮本輝さんのコメントが、非常に差別的である、ポリティカルコレクトネス的に問題であるということはおそらくかなり分かりやすいことかと思いますが、西原は、以下の二つの点が、より問題であると考えます。
まず一点目は、
①「日本文学」の歴史を無視している。
ということ。
宮本輝評は、漢文学・西欧文学との葛藤の中で、自らの言葉を作りあげてきた日本古典文学・近代文学の歴史を無視するものです。
国籍によるアイデンティティの問題に限定せず、「ことば」に対する意識、「母語」とは何かという葛藤に注目するならば、
そもそも文字・漢字は、海の向こう(対岸)から渡ってきたものですし、『竹取物語』にしても『源氏物語』にしても、漢文学からの影響や葛藤があります。また、近代以降は西洋文学からの影響も強く、その葛藤の中から日本文学は形成されてきました。森鴎外にしても、夏目漱石にしても、芥川にしてもそうでしょう。
いみじくも選考委員の一人である奥泉光が、
■奥泉光「言語の歴史性」(選評、前掲)
これ(=日本語の中に中国語が入り交ざった『真ん中の子どもたち』の文章、引用者注)がテクストとして成立できているのはもちろん、日本語と中国語の表記が漢字を共有する事実に依拠しているわけだが、そのこと自体が言語の歴史性を示すものであり(382頁)
と指摘するように、『真ん中の子どもたち』は、近代以降の日本・台湾・中国の歴史のみならず、漢字が日本に渡ってきて以来の日本語・日本文学の歴史も想起させるだけの射程を持ちます。
宮本輝評は、そういう、異なる言語や文学との葛藤の中で日本文学が作られてきた歴史を無視していると思えるのです。
二つ目の問題は、
②同調・共感可能なもののみを認める姿勢
です。
・あらかじめ「同調」できるものを読み、同調して満足するのであれば、ただあらかじめ知っているものを確認しているだけであって、何かを読むことの意味がどこにあるのか分かりません。
・海面/水面はしばしば「言葉」を象徴します。
あらかじめ同調や共感のできるものではなく、共感できない異物である他者、分からないもの、自分とは違うものである、「対岸」に渡るために、言葉が必要です。
その海面/水面の向こうの「同調」できない他者を、「対岸の火事」として追いやることは、言葉を媒介としたコミュニケーションそのものを否定する態度であると言えます。
そのような態度を、文学に関わるものがとることは、二重三重に問題でしょう。
1.事の発端
■温又柔『真ん中の子どもたち』
・集英社、2017年。初出:『すばる』2017年4月号
・第157回芥川賞候補作。
台湾人の母親、日本人の父親をもち、東京で育った主人公の「私」が、上海に語学留学したときの経験を回想形式で語る。
「母国語」とは何か、国家とは何かという疑問と葛藤から、自分たちは複数の国家の間で自らの言葉を模索する「真ん中の子ども」であるという思いに辿り着く。
この作品について、芥川賞選考委員の一人である宮本輝が、以下のような選評を述べました。
■宮本輝「カモフラージュ」
当事者たちには深刻なアイデンティティと向き合うテーマかもしれないが、日本人の読み手にとっては対岸の火事であって、同調しにくい。なるほど、そういう問題も起こるのであろうという程度で、他人事を延々と読まされて退屈だった。
(芥川賞選評、『文芸春秋』2017年9月特別号、383頁)
これについて温又柔さんご本人がTwitter で、
■温又柔 Twitter
@WenYuju
どんなに厳しい批評でも耳を傾ける覚悟はあるつもりだ。でも第157回芥川賞某選考委員の「日本人の読み手にとっては対岸の火事」「当時者にとっては深刻だろうが退屈だった」にはさすがに怒りが湧いた。こんなの、日本も日本語も、自分=日本人たちだけのものと信じて疑わないからこその反応だよね。
10:16 - 2017年8月11日
と書いて、ちょっとした騒ぎになりました。
2.問題点
この宮本輝さんのコメントが、非常に差別的である、ポリティカルコレクトネス的に問題であるということはおそらくかなり分かりやすいことかと思いますが、西原は、以下の二つの点が、より問題であると考えます。
まず一点目は、
①「日本文学」の歴史を無視している。
ということ。
宮本輝評は、漢文学・西欧文学との葛藤の中で、自らの言葉を作りあげてきた日本古典文学・近代文学の歴史を無視するものです。
国籍によるアイデンティティの問題に限定せず、「ことば」に対する意識、「母語」とは何かという葛藤に注目するならば、
そもそも文字・漢字は、海の向こう(対岸)から渡ってきたものですし、『竹取物語』にしても『源氏物語』にしても、漢文学からの影響や葛藤があります。また、近代以降は西洋文学からの影響も強く、その葛藤の中から日本文学は形成されてきました。森鴎外にしても、夏目漱石にしても、芥川にしてもそうでしょう。
いみじくも選考委員の一人である奥泉光が、
■奥泉光「言語の歴史性」(選評、前掲)
これ(=日本語の中に中国語が入り交ざった『真ん中の子どもたち』の文章、引用者注)がテクストとして成立できているのはもちろん、日本語と中国語の表記が漢字を共有する事実に依拠しているわけだが、そのこと自体が言語の歴史性を示すものであり(382頁)
と指摘するように、『真ん中の子どもたち』は、近代以降の日本・台湾・中国の歴史のみならず、漢字が日本に渡ってきて以来の日本語・日本文学の歴史も想起させるだけの射程を持ちます。
宮本輝評は、そういう、異なる言語や文学との葛藤の中で日本文学が作られてきた歴史を無視していると思えるのです。
二つ目の問題は、
②同調・共感可能なもののみを認める姿勢
です。
・あらかじめ「同調」できるものを読み、同調して満足するのであれば、ただあらかじめ知っているものを確認しているだけであって、何かを読むことの意味がどこにあるのか分かりません。
・海面/水面はしばしば「言葉」を象徴します。
あらかじめ同調や共感のできるものではなく、共感できない異物である他者、分からないもの、自分とは違うものである、「対岸」に渡るために、言葉が必要です。
その海面/水面の向こうの「同調」できない他者を、「対岸の火事」として追いやることは、言葉を媒介としたコミュニケーションそのものを否定する態度であると言えます。
そのような態度を、文学に関わるものがとることは、二重三重に問題でしょう。