
こうした戦記を扱った本では戦車や歩兵の視点から見たものが多いですが、
敢えて砲兵というある種地味な兵科から過去の世界大戦について語った挑戦的な一冊です。
通説では第一次世界大戦末期に誕生した戦車こそが陸戦を支配した。
と言われていますがその認識に対して具体的なデータからむしろ砲兵の方が功績が大きいと論じています。
例えばイギリス軍が第二次世界大戦中の戦車喪失要因は北アフリカ戦線でドイツ軍の対戦車砲に40.3%、戦車38.4%。
と、拮抗していますがこれがイタリア戦線では対戦車砲で16%、戦車12%、間接砲撃・空襲他で42%と大きく変化しています。
そしてノルマンディ上陸作戦から始まる北西ヨーロッパ戦線では対戦車砲22.7%、戦車14.5%、間接砲撃・空襲他40.7%。
などと戦車同士の対決よりも砲兵による砲撃にそれ以外の要因に求めることができるとできます。
では第二次世界大戦初期の機動戦、
すなわち電撃戦の成功は何かといえば「お互い前世界大戦並の砲兵戦力を有していなかった」ことに尽きます。
さらに技術的に砲兵の早期に展開する能力、すなわち「無線一本で砲撃を要請できる」体制に未だなっていなかった上に、
砲兵自身の機動力の低さもあってフランスでの華やかな電撃戦、北アフリカでの巧妙な駆け引きが成立したのですと論じています。
本書では砲兵の歴史から始まり、
第一次世界大戦で塹壕を砲撃で如何に突破すべきか試行錯誤する様子。
さらにその後各国の砲兵ドクトリンの航跡を丁寧かつ詳細に描写しておりお値段以上の価値があると思います。










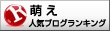





































※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます