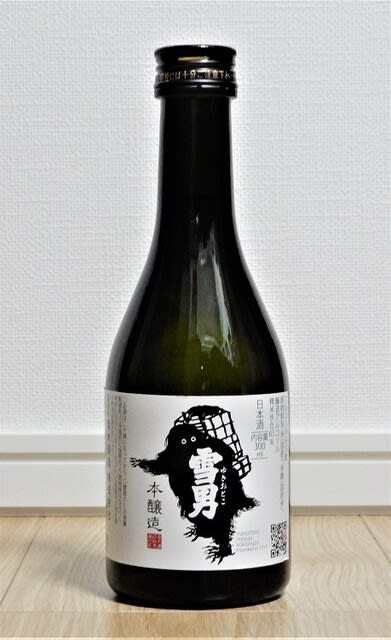日本酒、白鹿のピンズです。

このピンバッジは、季節限定冷酒「白鹿すずろ」の2012年春夏期間限定で販売ボトルのおまけとして付いていました。
また、西宮日本酒学校2016できき酒の全問正解者にプレゼントされ、その後は、2018年2月の「白鹿 蔵開き ソトノミフェス」でのスタンプラリーなどでも配られたようです。

「すずろ」は、白鹿の伝承蒸米仕込で造ったお酒を生のまま搾りたての状態で瓶詰時に低温瞬間殺菌しているため、爽やかでほのかに薫る香りと程よい甘みとのバランス、さっぱりとした飲みごたえはフレッシュで春夏によく冷やして飲むのがぴったりです。

銘酒「白鹿」の名前は、長生を祈る中国の神仙思想に由来します。
唐の時代、玄宗皇帝の宮中に一頭の鹿が迷いこみ、仙人の王旻(おうびん)がこれを千年生きた白鹿と看破しました。調べると、角の生え際には「宜春苑中之白鹿」と刻んだ銅牌が…。
“宜春苑(ぎしゅんえん)”とは、唐の時代を千年もさかのぼる漢の武帝の時代のもので、玄宗皇帝はこれを瑞祥と歓んで慶宴を開き、白鹿を愛養したと伝えられています。
その歴史は、1830年(文政 13)作の「宜春苑 長生自得千年寿 白鹿」という銘が打たれた欅板看板が、江戸新川の酒問屋島屋庄助商店に残っており、下り酒の「白鹿」が“灘の銘酒”として不動の地位を確立していたことを物語っています。
起業は、1662年(寛文二年)、徳川四代将軍家綱の頃、初代辰屋(辰馬家の当時の屋号)吉左衛門が西宮の邸内に井戸を掘ったところ、その水が清冽甘美であたことから酒造りの事業を始めたと伝えられています。灘の酒造家から懇請され、「宮水」として良質であった居宅蔵の井戸水を販売し始めたのもこの頃です。
明治維新後も技術革新に取り組み、1892(明治25)年には醸造高で全国第一位「白鹿」辰馬たきとあり、その生産量は2万3,510石もありました。この年、1892年の全国生産量は380万石弱で、2018年の生産量は270万石強、126年前は今より100万石も多かったのです。1920年(大正9年)には丹波杜氏・梅田多三郎によって新醸造に成功、高級酒「黒松白鹿」が誕生しています。