フィリピンを始めて訪れ、首都圏のマカティ市やBGCを見る限り、そこそこ綺麗であり、飲食からショッピングに至るまで
日本と変わらないと思います。
フィリピンは物価が安い。
日本から外貨を持ってくる人々の話であり、実際に現地で働く者は、年功序列性や能力給とはかけ離れた最低賃金で、
しかも未完全雇用にさらされている国民が多い。
フィリピン首都圏の最低賃金は、非農業部門で日額645ペソ(約1,770円)です。前と比べて5.7%上昇した。
ちなみに日本食のラーメンは1000円以上する。
フィリピンは、低い経済成長、高い所得格差、弱い雇用創出、貧弱な統治、横行する汚職、自然災害に対する脆弱性、
十分に発展していない農業への依存、必要な改革を妨げる強力な政治王朝の存在など、様々な要因が重なり、
全く改善されない継続的な貧困に喘いでいる。
高層ビルが立ち並ぶ首都圏。しかし、一歩足を踏み入れるとそこには現代ではなかなか考えられないような世界が広がります。



そしてその多くは、不法占領区と呼ばれる場所が多く、火事が最も多い地区でもあります。
フィリピンの貧困のポイント
不均等な経済発展:
不均等な経済発展:都市部を中心に著しい経済成長を遂げる地域がある一方、農村部の多くは未発達のままであり、生活水準の格差につながっている。
質の低い雇用:
雇用市場には高賃金で安定した雇用機会がないことが多く、低賃金や労働法では禁止されているENDと言われる不完全雇用が未だに横行している。
政治問題:
政府内の腐敗や政治的支配が、貧困削減を目的とした効果的な政策実施の妨げとなっている。政権が変わるたびに支配方法が変わる。結果としてマルコス政権以降近代に至るまで全く言って良いほど改善が行われていない。ドウテルテ政権で多少改善はされてきた。
自然災害:
フィリピンは台風や地震の影響を受けやすく、経済的に大きな打撃を受け、生活に支障をきたしている。災害復興にかかる期間は長期におよび、例を挙げると、1991年世紀の大噴火といわれるピナツボ火山噴火による災害はその多くが未だに傷跡が残っている。
非効率な農業部門:
農業は依然として多くのフィリピン人にとって主要な収入源であるが、生産性が低く、時代遅れの農法がその可能性を制限している。機械化が遅れている。また毎年の自然災害による収穫減は顕著である。
高い人口増加率:
人口が急速に増加しているため、資源やインフラに負担がかかり、貧困削減の取り組みに影響を与えている。思春期が異常にはやく、性教育や宗教上の問題で若年者の未婚の出産も多い。
続く

























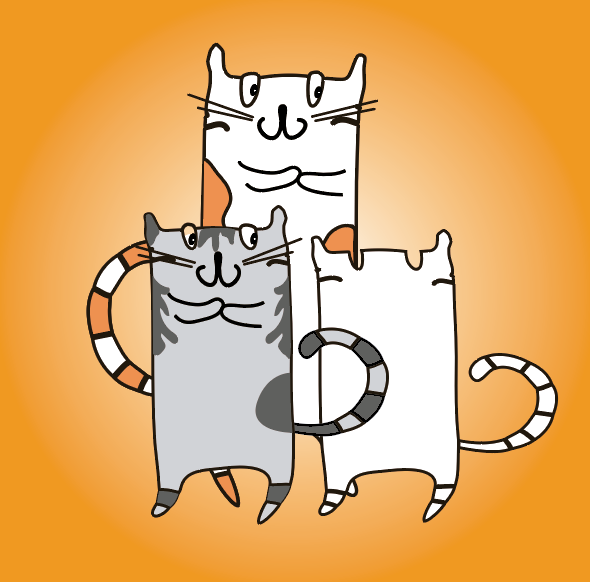

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます