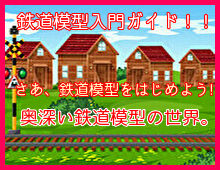高裁、支払い義務認めるも 団体訴訟のほぼ全部を破棄
1980年代後半から90年代初頭のハイパーインフレ時代に、インフレ対策で預金利率を下げた当時の政策は不当だとして、差額利子の返済を銀行側に求める訴訟に関する第2回高裁審理が25日行われた。同裁は、当時の経済政策が預金者に損失を与えたことを認め、銀行側は差額利子分を返済する必要があるとしたものの、団体起訴の有効期限を事象発生から5年に変更した。従来は20年だったものが大幅に短縮され、団体訴訟は99%が破棄される見通し。これに関し、消費者保護と見せかけて、実際は銀行に有利な決定だとの批判が渦巻いている。
全伯で1030件に上る団体訴訟は、ブレッセル(87年)、ベロン(89年)、第1次(90年)・第2次(91年)コロールの各経済プランを対象とするもの。利率引き下げで生じた利子の差額損失分はそれぞれ、26%、42%、44%、21%とされる。高裁は今回、銀行はこれらの差額を支払う義務があるとした。
一方で、団体訴訟の起訴時効期間を従来の20年から5年に短縮することを決めた。このため1030件の団体訴訟は、99%に相当する1015件までが破棄される。現在でも有効なのは、91年に施行された第2コロール・プラン訴訟のみとなる。
これにより銀行側の推定支払額は、600億レアルだったものが100億レアルとなり、銀行にとって有利な決定となった。
1980年代後半から90年代初頭のハイパーインフレ時代に、インフレ対策で預金利率を下げた当時の政策は不当だとして、差額利子の返済を銀行側に求める訴訟に関する第2回高裁審理が25日行われた。同裁は、当時の経済政策が預金者に損失を与えたことを認め、銀行側は差額利子分を返済する必要があるとしたものの、団体起訴の有効期限を事象発生から5年に変更した。従来は20年だったものが大幅に短縮され、団体訴訟は99%が破棄される見通し。これに関し、消費者保護と見せかけて、実際は銀行に有利な決定だとの批判が渦巻いている。
全伯で1030件に上る団体訴訟は、ブレッセル(87年)、ベロン(89年)、第1次(90年)・第2次(91年)コロールの各経済プランを対象とするもの。利率引き下げで生じた利子の差額損失分はそれぞれ、26%、42%、44%、21%とされる。高裁は今回、銀行はこれらの差額を支払う義務があるとした。
一方で、団体訴訟の起訴時効期間を従来の20年から5年に短縮することを決めた。このため1030件の団体訴訟は、99%に相当する1015件までが破棄される。現在でも有効なのは、91年に施行された第2コロール・プラン訴訟のみとなる。
これにより銀行側の推定支払額は、600億レアルだったものが100億レアルとなり、銀行にとって有利な決定となった。