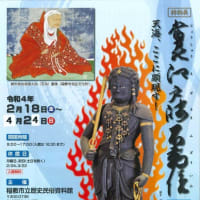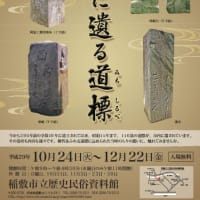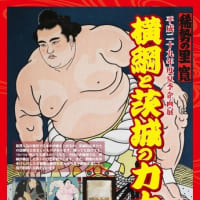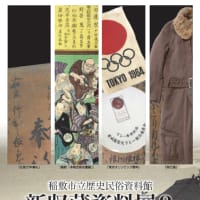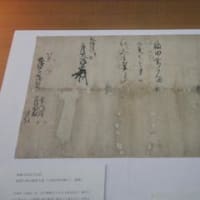4月21日(日)。
この日は、吹き荒れる雨風の中、江戸崎の瑞祥院の
調査をしてきました。
この調査は、稲敷市が合併してから当資料館が
行っている仏像・寺院調査の一環です。
瑞祥院では、これまでも何度か調査が行われていますが、
地元資料館として、より深く、より丁寧な調査を
心掛けているところです。
まず、冒頭に、ご住職には既刊の新利根地区の
調査報告書を見て頂きながら、主旨をご説明させて
いただき、それからは仏像調査、文書調査、絵画調査
と分かれて調査をいたしました。
分かれて、といいましても、人員が居りませんので
各1名ずつ程度なのですが…。

こちらは、市指定文化財にもなっている銅造阿弥陀三尊立像で、
時代は南北朝‐室町初期頃とされています。
本来は「一光三尊」といいまして、一つの光背(註)の前に
阿弥陀如来、勢至菩薩、観音菩薩の三つの仏様がおわす形を
取りますが、ここでは撮影のために光背は取り外しています。
この形の仏様は、長野の善光寺のご本像がそうだとされており、
善光寺式阿弥陀三尊という呼び名もあります。

こちらは、紙本着色釈迦涅槃図です。
この絵は、お釈迦さまが入滅になったことを弟子達や動物、鳥、
そして虫たちまでもが悲しんでいる様子を描いたものです。
この絵は巻物になっており、それが納められている箱には
墨で「天保十二辛丑二月十五日調焉」とあり、
天保12年(1841)に作成されたことがわかります。
この日も、お忙しい中、ご住職と世話人の方が
朝の10時から夕方の5時過ぎまで、一日立会いをして
くださいました。
本当に、ありがとうございました。
(註) 仏様の背後にあってその体から放たれる光明を表したもの