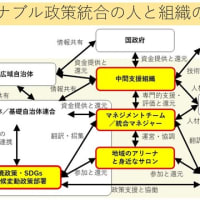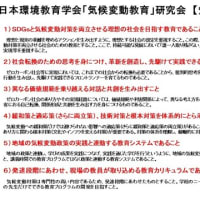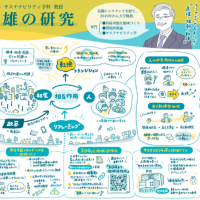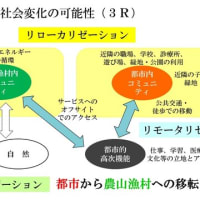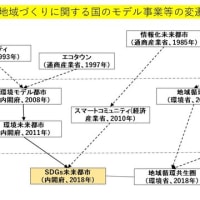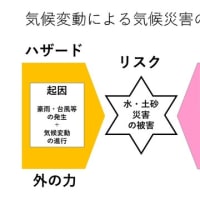3.高度経済成長の歪みが顕在化した時代
(1)重化学工業化とエネルギー革命
何物をも戦争遂行につぎ込んだ挙げ句、日本の都市は焼土となり、多くの山は木を失って、ようやく終戦を迎えた。当時の経済安全本部の調査では、生産設備の44%が破壊されており、特に消費関連部門の生産能力の低下が著しかったと報告している。
戦後の復興においては、当時の吉田内閣の主導により「傾斜生産方式」(1946~48年)が取られた。これは、石炭を増産し、これを鉄鋼に傾斜的に配分して鋼材を増産し、鋼材は石炭産業を傾斜配分して、その増産を図るものである。これによって、鉱工業生産水準の相乗的な引き上げが図られた。
1947年には、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)が締結された。戦争によって植民地や勢力圏を失った日本は、国際的な競争に晒されることになる。特に、明治維新後の日本は、繊維製品を輸出し、外貨を獲得してきたが、アジア各国の綿製品自給能力の向上や合成繊維の普及によって、その継続が困難になってきた。そこで、日本は相対的に付加価値の大きい重化学工業製品の生産を重視し、海外からの原材料・燃料を調達し、重化学工業製品を輸出する加工貿易立国を目指すことになる。
1950年には朝鮮戦争が勃発し、特需ブームとなる。これは、わが国の産業に、国際競争の立ち後れを自覚させ、外国技術の積極的な導入による合理化を進める契機となった。
1950年代、世界的にエネルギー革命が進展し、1958年には、当時の西側先進国における石油と石炭のシェアが逆転することになる。日本では、戦後の「炭主油従政策」があり、西側先進国に比べて、エネルギー革命が遅れた。それでも、1958年頃までには重油価格と石炭価格の格差が決定的になり、1962年に日本の石油と石炭のシェアが逆転した 。
(2)第1次産業の工業化
重化学工業を中心とした産業発展が志向される中で、第1次産業も大きく様変わりを見せた。農業では、1950年代前半から工業製品である硫安や過リン酸石灰が化学肥料として普及した。これにより、農家は、人糞の施肥や刈敷(雑木林の下草等を足で踏んで、田にすき込む作業)等の重労働から解放されたが、一方で土地の悪化や病害虫の多発という事態が発生した。このため、DDTやBHC等の農薬が必要となり、化学肥料の投与は農薬の需要を拡大することとなった。また、1953年には「農業機械化促進法」が公布され、動力耕運機やバインダー、田植機、自動コンバイン等の農業機械が普及した。農業機械の普及は、小型エンジンの開発やエネルギー革命の進展に支えられたものである。また、1951年に農業用ビニールが開発され、1955年頃から各県での使用が奨励されるようになった。
こうした“農業の重化学工業化”が進められた時代に、農産物の収穫量も飛躍的に拡大した。例えば、コメの生産量は1946年以降に900万t台で推移したが、1955年には一挙に1,238万tになり、以降その水準を維持することになった。地主から農地を払い下げる農地改革が農民の労働意欲を増大させたこととともに、化学肥料や農薬、農業機械等の普及が農業生産性を向上させたと言える。しかし、“農業の重化学工業化”は、短期的な生産性を向上させたかもしれないが、農産物の安全性や地力の維持等の問題もあり、両刃の剣であることに、当時気づいていた人は少なかったであろう。
また、畜産業においても、大量生産の方法が導入された。1960年には肉専用鶏ブロイラーの原種をアメリカから輸入し、飼料のほとんどを輸入に依存する方法での養鶏が普及した。豚や牛でも輸入飼料が普及したが、一方で流動食によって胃酸過多になった豚は胃潰瘍になり、牛の乳房炎も増えたと言われる。水産業における養殖業も、この頃からスタートした。加温養殖し、育成期間を短縮する方法でのウナギの養殖や、海洋を生け簀で囲って、飼育するハマチの養殖等が始められたのは、1960年代である。
(3)高度経済成長の進展と環境配慮の軽視
第1次産業をも巻き込んで進展した重化学工業化とエネルギー革命によって、日本経済は高度経済成長期へと突入した。1950年代後半に8.8%であった実質経済成長率は、1960年代前半に9.3%、同年代後半に12.4%へと尻上がりに上昇した。国際競争力を得た輸出と産業を高度化させるための設備投資は、相互に増幅し合い、高度経済成長を加速させた。しかし、重化学工業化によって、GNP1単位当たりの汚濁負荷量は高くなり、汚濁発生量は経済成長率以上のスピードで増えていったものと考えられる。
また、第1次産業における変化は、江戸時代に形成され、その後も農山村地域などで継承されていた循環型の様式(①地域資源の徹底的なリサイクル、②バイオマス資源・自然エネルギーへの依存、③複合的な循環システム)を完全に瓦解させるものであった。この結果、農用林や薪炭林として形成されていた雑木林は、放棄され、宅地等の用途に転用されていくことなった。そして、太陽エネルギーや人力を動力源とした生産が、化石燃料を動力源とする生産に移行することで、枯渇性資源に依存する、またエネルギー消費量が大きな生産システムを築き上げることとなった。
また、高度成長期における政策も、経済活動の隘路となる様々な障害を取り除き、成長力を遺憾なく発揮させることを狙いとされた。例えば、限られた予算に依存している政府資本形成は、道路等の産業基盤整備に振り向けられ、下水道、廃棄物処理、都市公園等の生活環境整備には乏しい予算配分しかなされなかった。例えば、高度成長の末期の1970年の公共事業費のうち、約半分が産業関連事業で、生活環境関連事業は公共事業費の約5%に過ぎなかった。これが、公害の拡大を防ぎきれなかった1つの原因といえる。
さらに、高度経済成長期には、地域間の経済発展の不均衡も問題となった。このため、1962年には、全国総合開発計画が策定され、工場の地方分散、拠点における集中的な地域開発が方向づけられた。この政策にそって、いくつかの地方では、最新鋭のコンビナート等が立地した。工場を誘致するための経済的な優遇策等も用意されたが、それらがもたらす公害問題に対する対応が十分に成されなかったため、公害は地方の工業都市にも広がり、産業規模の増大と共に、深刻の度を深めていくことになった。
(4)公害問題の顕在化
チッソ株式会社の前身である日本窒素肥料(株)が、熊本県水俣市に工場を立地したのは、1908年(明治41年)のことである。当時、水俣市は人口1万2千人の小さな町であり、木材やみかん生産、漁業等を生業とする風向明美な地域であった。工場建設は、町の雰囲気を一新し、水俣の地における高度経済成長が進展した。1956年には、市人口は5万人に達した。しかし、工場排水による水質汚濁が同時に進行し、1920年代には早くも漁業補償問題が生じた。1950年代には、水俣湾の魚が海面に浮き出し、カラスや水鳥が空から落ち、ネコが狂死し始めたと言われる。このような中で、1956年に、原因不明の患者の入院が報告され、これが水俣病の公式発見と呼ばれている。水俣病は、工場排水によって汚染された海域に生息する魚介類に蓄積された有機水銀が人体に取り込まれ、その結果起こる中枢神経系の疾患として、世界に知られることになった。
水俣病は、1965年頃、昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水を原因として、新潟県阿賀野川流域でも発生した。また、富山県神通川流域においては、カドミウム、鉛、亜鉛等の金属類による水質や土壌の汚染を原因とするイタイイタイ病が発生した。
一方、エネルギー革命(石炭から石油への転換)が進展する中で、大気汚染も粉じんを中心としたものから、硫黄酸化物を中心とした汚染に形態を変化させ、また広域化してきた。とりわけ、1950年代後半以降に、日本各地で進められた石油コンビナートの形成は、硫黄酸化物による広域的な大気汚染や悪臭、水質汚濁等の問題を引き起こした。石油コンビナートからのばい煙を原因とする三重県四日市市のぜんそくは、当時の水俣病、イタイイタイ病等と並び、典型的な公害病として称された。
また、この時期には瀬戸内海における赤潮の発生や、臨海工業地帯における地下水使用量の急増による地盤沈下等も深刻化した。
このように、高度経済成長期には、重化学工業を中心とした生産活動が、環境影響への備えのないまま活発化し、明治時代から見られた公害がより深刻な被害となって、社会問題化した。また、日本各地での工業拠点の整備は、各地域の経済振興に貢献する反面、日本各地に公害問題を拡散させる結果となった。
(5)公害反対の世論の高まりと住民運動
高度経済成長期における環境問題の多発に伴い、一般市民も含めた「市民パワー」が現れてきた。例えば、1958年の江戸川の製紙工場排水による漁業被害をめぐる漁民と工場との乱闘事件は、水質汚濁対策を促進する契機になった。
この他、1963年から64年にかけて三島・沼津地域で起こったコンビナート建設反対運動は、これまでの農漁民対企業という従来の公害紛争の型を超え、広く一般市民の関心を集めた。高度経済成長政策の主要な柱である臨海コンビナートの立地が計画段階で公害問題を理由に中止されたことは、国や産業界、地方公共団体に大きな衝撃となった。
一方、自然破壊に反対する人々の動きも次第に活発化してきた。1950年代後半頃から国民生活が安定してくるにつれ、都市住民の間にすぐれた自然とのふれあいを求める気持ちが高まる一方、急激に過疎化が進行した農山村地域では、観光開発が進められた。しかし、道路建設等のこれらの観光開発は、自然保護に対する配慮の不十分さ、施工技術の遅れ等により自然破壊をもたらすとともに、自動車の排出ガス等による2次的な自然破壊を引き起こすことにより、結果的には自然の利用者に深い失望を与えることになった。富士スバルラインや石鎚山スカイライン等は批判の対象となった例であり、こうした批判を背景に、尾瀬道路主要地方道沼田田島線等は工事の中止や路線の変更に至った。
公害問題や自然破壊に対する住民の反対運動は、1960年代後半から大きなうねりとなり、環境配慮に係る市場の枠組みづくりに踏み出す1970年代を迎えることになった。
(6)食品公害と消費革命
公害病は、企業の生産活動に伴う環境負荷によって生じる問題であるが、高度経済成長期にはまた製品の使用段階あるいは廃棄段階の問題が顕在化した。特に、食品産業の工業化に伴う多種多様な食品添加物の使用や、農業の重化学工業化に伴う残留農薬問題、プラスチックの安全性やごみ問題等が、社会問題化した。
1955年には、最初の大規模な食品公害として死者133人、中毒患者1万2千人に及ぶ被害を出した森永ヒ素ミルク事件が発生した。これは、森永乳業徳島工場が粉乳の安定剤として混入した第2リン酸ソーダ(アルミ工場の副産物)に大量のヒ素が含まれていたことによるものだと解明された。この他、医薬品によるサリドマイド事件(1962年)、米ぬか油によるカネミ油症事件(1968年)等の、深刻な被害が発生した。
一方、高度経済成長期は、産業の発展とともに国民生活が大きく変動した。例えば、1953年には、国産の電気洗濯機が登場し、「電化元年」と呼ばれたが、その2年後にはテレビ、電気洗濯機と合わせて、電気製品の「三種の神器」が出揃うこととなった。こうした消費構造の変化を、1959年版国民生活白書では、「消費革命」と呼んでいる。
また、流通分野ではスーパーマーケットが登場した。国内最初のスーパーは、1953年に東京・青山にオープンした「紀ノ国屋」とされ、その4年後、現在のダイエーの前身となる「主婦の店ダイエー薬局」が、大阪・千林にオープンした。スーパーでは、商品単価を下げるために、大量流通を前提とする。このため、スーパーの普及に伴って、農産物を大量にかつ安定的に供給するために、特定農産物を集中的に生産する指定産地制度が設けられた。
家電製品の普及や農産物の大量流通等は、技術革新とともに、アメリカ的生活様式に追随する消費者の志向性によるものだと考えられる。高度経済成長期における環境問題は、企業の製造過程や製品における環境配慮があまりに希薄なことによる加害者が特定される問題だと言えるが、今日の環境問題の根本的要因である大量生産・大量消費・大量廃棄構造は、高度経済成長期において雛形がつくられたのである。
4.公害対策と省エネルギーの時代
(1)公害規制の整備と排出源対策
高度経済成長の歪みが大きな社会問題となり、1970年に至っては、「公害メーデー」等の全国規模の公害反対運動が起こり、「公害国会」が開催される等、公害に明け、公害に暮れる一年となった。この年からの世論は、経済成長のマイナスの側面に対する評価がますます厳しくなり、同年のNHKの世論調査では、「公害や物価上昇をもたらし、国民生活が一部の企業や産業の犠牲になってきた」として、経済成長を否定的に捉える人がはじめて55%と過半数を超えた。
また、1971年の総理府の世論調査では、工場全部の排出物を厳しく規制するという考え方に対して90%の人が賛成したことにも見られるように、公害対策の強化は、国民の一致した世論となるに至った。
既に、1967年に「公害対策基本法」、1968年に「大気汚染汚染防止法」が制定されていたが、1970年の「公害国会」ではこれらの法律の改正を含めて、公害関係の14法案の全てが可決・成立した。成立した法案の多くは、規制を強化し、事業者責任を明確化するものであった。
例えば、「公害対策基本法」をはじめとする公害対策の関係法から「経済の健全な発展との調和」を図りつつ公害対策を進めるといういわゆる「調和事項」が削除され、経済優先ではないかという国民の疑念を払拭した。規制については、大気汚染、水質汚濁に係る従来の指定地域制を改め、未汚染地域を含め全国を規制対象地域とするとともに、規制対象物質項目の範囲を拡大する法律が定められた。また、「公害防止事業費事業者負担法」に、事業者責任が規定され、公害防止事業についての事業者の費用負担義務が具体化された。
こうした法制度の整備による規制に追随する形で、企業は公害対策のための設備投資を進め、1970年代の公害防止のための設備投資は1960年代と比較して、飛躍的に増加した。
(2)石油危機による省エネルギー構造への転換
1970年代は、公害規制や係る事業者負担の枠組みが整備されることでスタートしたが、こうした公害規制への対応に加えて、2度の石油危機に遭遇し、経済の体質や環境配慮に係る姿勢が一変することになった。
第1次石油危機が勃発した1974年度には、戦後初のマイナス成長を経験した。1970年度から74年度の累積成長率(実質)は約20%であったが、1970年代後半の同率は約15%に低下し、さしもの高度経済成長も減速傾向を示すことになった。企業では、エネルギーの節約、人員配置の変更等を通じた徹底した減量経営が行われた。
この時代の動きの象徴的な事例を、自動車産業に求めることが出来る。自動車産業は、1960年から70年にかけて、生産量を11倍に伸ばし、1971年には国内の乗用車生産台数がドイツを抜いて、世界第2位まで成長した。しかし、追い風ばかりではなく、1969年には欠陥車問題があり、1970年には新宿区牛込の住民の血中鉛濃度が高いことや、杉並区の光化学スモッグが社会問題化した。
丁度この時期、米国では、マスキー法が制定された。同法は、自動車排ガス中の有害物質の抑制を目的にしたもので、75年型車からCO、HCを70年規制基準の1/10以下とすること、76年型車からNOxを71年型車平均排出量の1/10以下とするという2つの基準を定めた。これに呼応して、日本ではCOとHCを75年規制、NOxを78年規制としたが、米国は結局、石油危機のためにマスキー法の実施が延期され、日本が世界に先駆けることになった。
特に、本田技研工業(株)では、CVCC(複合渦流調速燃焼方式)エンジンを開発し、排ガス規制に対応するトップランナーとなった。このエンジンを持って、本田技研工業(株)の1974年の売り上げは、73年の60%増となっている。また、自動車業界全体でも、石油危機は国際競争力を高める結果となった。これは、ガソリンの高騰に伴って、米国で小型車ブームとなり、わが国の自動車輸出が急増したためである。
以上のように、環境規制の整備や石油危機は、結果としてわが国産業の技術力や国際競争力を高めたとみることが出来る。
(3)技術革新と知識集約化
明治維新後の工業化は、エネルギー革命(石炭から石油へのエネルギー転換)に支えられ、高度経済成長期に飛躍的なものとなったが、1970年代は環境や資源に配慮しなかったツケがわき出した時代であったと言える。
これらのツケ回しが産業界にフィードバックされたのが1970年代だが、以下の3つの側面の努力や変化によって、一定程度、問題を克服することが出来たと言える。
1つは、自動車の低公害型のエンジン開発や触媒開発等の例にみられるような技術革新である。生産性向上にひたすら振り向けられていた技術開発のパワーが、公害対策や省エネルギーに向けられることで、一定程度の環境負荷の抑制を図ることが出来た。これは、生産活動当たりの環境負荷排出原単位やエネルギー消費原単位を減少させるものであった。
2つめは、産業構造の変化である。1971年の通産省産業構造審議会の答申においては、知的活動の集約度が高い産業(知識集約型産業)を中核とし、これを支える基盤的産業やその他の産業における知識集約度の向上を志向することが示された。実際にも、電子計算機産業が育成され、資源・エネルギー多消費型の重化学工業から卓上電子計算機の小型化等に象徴される「軽薄短小型」の産業構造への転換が加速された。
3つめは、景気低迷によって、生産・消費量が抑制されたことである。これは、石油危機による物価高騰という外的要因によるものであり、結果として環境負荷を抑制させたという側面である。
以上のように、1970年代にわき出したツケは、技術革新と知識集約化によってクリアされ、その見返りとして日本の産業は新たな競争力を獲得することが出来た。
(4)農林漁業におけるツケ回しへの対応
工業界では、高度経済成長期におけるツケ回しを技術革新と知識集約化によって、一定程度克服したが、第1次産業はどうだったのか。
まず、農業においては、重化学工業化に巻き込まれて、農業機械の導入や農薬、化学肥料の消費拡大が進行した。農業機械の導入はまだしも、1970年代には農薬や化学肥料による食の安全性の問題がクローズアップされた。その契機となったのは、1964年に日本で翻訳出版されたレイチェル・カーソンの著作「沈黙の春」である。農薬による自然破壊を訴え、水銀を使用する農薬やDDT、BHC等の使用を禁止する引き金となった。1971年には、化学物質に依存した農業からの脱却を目指す「有機農業研究会」が発足した。この研究会は、元農林事務次官を代表幹事に、農学者、医師、協同組合関係者等が中心となって結成されたもので、これに刺激されて、各地域に有機農業が普及することになった。また、1974年には有吉佐和子が朝日新聞に「複合汚染」を連載し、消費者の間にも有機農産物の存在を知らしめることになった。
漁業の分野では、1970年代に商業捕鯨が国際的な非難に晒され、200カイリ水域が設定されることもあって、遠洋漁業から沿岸漁業に回帰する傾向がみられた。しかし、沿岸では、工場排水や赤潮による被害もあり、漁獲生産力はますます減少した。一方、農業と同様に、漁業従事者の減少と高齢化を補うものとして、漁船の性能向上や魚群探知機の進歩、漁網の改良等、設備・技術の高度化が進められた。技術の向上が乱獲によって、水産資源をさらに枯渇させるという悪循環が指摘されたのも、この頃である。資源管理がクローズアップされた1970年代、漁業では国内の漁獲管理や栽培漁業の進行等が図られたが、国内の漁獲高はますます減少し、水産物輸入をますます増大させることとなった。
一方、林業では、高度経済性成長期に大都市への人口流動が活発化し、住宅需要が増大する中で、スギやヒノキ、カラマツを主体とする植林(人工林化)が活発化した。しかし、国内の多くの人工林が伐採適期を迎えるつつあるのは、ようやく近年のことであり、1970年代に国内林業における環境配慮を進める動きは無かったと考えられる。高度経済成長期の日本は、東南アジアのタイやフィリピンから木材輸入を拡大させてきた。例えば、フィリピンでは、1950年代に日本のラワン材の買い付けが始まり、フタバガキ科の原生林の集中的伐採が進んだ。この結果、フィリピンのフタバガキ科の原生林の森林面積は、1969年の466万haから、1988年には99万haまで激減することになった。
以上のように、第1次産業も、公害問題や資源問題のクローズアップされた1970年代の洗礼を受けた。その動きは、農業はまだしも、漁業や林業においては、国内産業の衰退と輸入への依存体質を強めるものであり、環境配慮型への生産技術の向上や構造転換を促すものではなかったと言える。そして、輸入依存性を高めることで、ツケを海外に回し、見えない自然破壊を進める結果となった。
(1)重化学工業化とエネルギー革命
何物をも戦争遂行につぎ込んだ挙げ句、日本の都市は焼土となり、多くの山は木を失って、ようやく終戦を迎えた。当時の経済安全本部の調査では、生産設備の44%が破壊されており、特に消費関連部門の生産能力の低下が著しかったと報告している。
戦後の復興においては、当時の吉田内閣の主導により「傾斜生産方式」(1946~48年)が取られた。これは、石炭を増産し、これを鉄鋼に傾斜的に配分して鋼材を増産し、鋼材は石炭産業を傾斜配分して、その増産を図るものである。これによって、鉱工業生産水準の相乗的な引き上げが図られた。
1947年には、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)が締結された。戦争によって植民地や勢力圏を失った日本は、国際的な競争に晒されることになる。特に、明治維新後の日本は、繊維製品を輸出し、外貨を獲得してきたが、アジア各国の綿製品自給能力の向上や合成繊維の普及によって、その継続が困難になってきた。そこで、日本は相対的に付加価値の大きい重化学工業製品の生産を重視し、海外からの原材料・燃料を調達し、重化学工業製品を輸出する加工貿易立国を目指すことになる。
1950年には朝鮮戦争が勃発し、特需ブームとなる。これは、わが国の産業に、国際競争の立ち後れを自覚させ、外国技術の積極的な導入による合理化を進める契機となった。
1950年代、世界的にエネルギー革命が進展し、1958年には、当時の西側先進国における石油と石炭のシェアが逆転することになる。日本では、戦後の「炭主油従政策」があり、西側先進国に比べて、エネルギー革命が遅れた。それでも、1958年頃までには重油価格と石炭価格の格差が決定的になり、1962年に日本の石油と石炭のシェアが逆転した 。
(2)第1次産業の工業化
重化学工業を中心とした産業発展が志向される中で、第1次産業も大きく様変わりを見せた。農業では、1950年代前半から工業製品である硫安や過リン酸石灰が化学肥料として普及した。これにより、農家は、人糞の施肥や刈敷(雑木林の下草等を足で踏んで、田にすき込む作業)等の重労働から解放されたが、一方で土地の悪化や病害虫の多発という事態が発生した。このため、DDTやBHC等の農薬が必要となり、化学肥料の投与は農薬の需要を拡大することとなった。また、1953年には「農業機械化促進法」が公布され、動力耕運機やバインダー、田植機、自動コンバイン等の農業機械が普及した。農業機械の普及は、小型エンジンの開発やエネルギー革命の進展に支えられたものである。また、1951年に農業用ビニールが開発され、1955年頃から各県での使用が奨励されるようになった。
こうした“農業の重化学工業化”が進められた時代に、農産物の収穫量も飛躍的に拡大した。例えば、コメの生産量は1946年以降に900万t台で推移したが、1955年には一挙に1,238万tになり、以降その水準を維持することになった。地主から農地を払い下げる農地改革が農民の労働意欲を増大させたこととともに、化学肥料や農薬、農業機械等の普及が農業生産性を向上させたと言える。しかし、“農業の重化学工業化”は、短期的な生産性を向上させたかもしれないが、農産物の安全性や地力の維持等の問題もあり、両刃の剣であることに、当時気づいていた人は少なかったであろう。
また、畜産業においても、大量生産の方法が導入された。1960年には肉専用鶏ブロイラーの原種をアメリカから輸入し、飼料のほとんどを輸入に依存する方法での養鶏が普及した。豚や牛でも輸入飼料が普及したが、一方で流動食によって胃酸過多になった豚は胃潰瘍になり、牛の乳房炎も増えたと言われる。水産業における養殖業も、この頃からスタートした。加温養殖し、育成期間を短縮する方法でのウナギの養殖や、海洋を生け簀で囲って、飼育するハマチの養殖等が始められたのは、1960年代である。
(3)高度経済成長の進展と環境配慮の軽視
第1次産業をも巻き込んで進展した重化学工業化とエネルギー革命によって、日本経済は高度経済成長期へと突入した。1950年代後半に8.8%であった実質経済成長率は、1960年代前半に9.3%、同年代後半に12.4%へと尻上がりに上昇した。国際競争力を得た輸出と産業を高度化させるための設備投資は、相互に増幅し合い、高度経済成長を加速させた。しかし、重化学工業化によって、GNP1単位当たりの汚濁負荷量は高くなり、汚濁発生量は経済成長率以上のスピードで増えていったものと考えられる。
また、第1次産業における変化は、江戸時代に形成され、その後も農山村地域などで継承されていた循環型の様式(①地域資源の徹底的なリサイクル、②バイオマス資源・自然エネルギーへの依存、③複合的な循環システム)を完全に瓦解させるものであった。この結果、農用林や薪炭林として形成されていた雑木林は、放棄され、宅地等の用途に転用されていくことなった。そして、太陽エネルギーや人力を動力源とした生産が、化石燃料を動力源とする生産に移行することで、枯渇性資源に依存する、またエネルギー消費量が大きな生産システムを築き上げることとなった。
また、高度成長期における政策も、経済活動の隘路となる様々な障害を取り除き、成長力を遺憾なく発揮させることを狙いとされた。例えば、限られた予算に依存している政府資本形成は、道路等の産業基盤整備に振り向けられ、下水道、廃棄物処理、都市公園等の生活環境整備には乏しい予算配分しかなされなかった。例えば、高度成長の末期の1970年の公共事業費のうち、約半分が産業関連事業で、生活環境関連事業は公共事業費の約5%に過ぎなかった。これが、公害の拡大を防ぎきれなかった1つの原因といえる。
さらに、高度経済成長期には、地域間の経済発展の不均衡も問題となった。このため、1962年には、全国総合開発計画が策定され、工場の地方分散、拠点における集中的な地域開発が方向づけられた。この政策にそって、いくつかの地方では、最新鋭のコンビナート等が立地した。工場を誘致するための経済的な優遇策等も用意されたが、それらがもたらす公害問題に対する対応が十分に成されなかったため、公害は地方の工業都市にも広がり、産業規模の増大と共に、深刻の度を深めていくことになった。
(4)公害問題の顕在化
チッソ株式会社の前身である日本窒素肥料(株)が、熊本県水俣市に工場を立地したのは、1908年(明治41年)のことである。当時、水俣市は人口1万2千人の小さな町であり、木材やみかん生産、漁業等を生業とする風向明美な地域であった。工場建設は、町の雰囲気を一新し、水俣の地における高度経済成長が進展した。1956年には、市人口は5万人に達した。しかし、工場排水による水質汚濁が同時に進行し、1920年代には早くも漁業補償問題が生じた。1950年代には、水俣湾の魚が海面に浮き出し、カラスや水鳥が空から落ち、ネコが狂死し始めたと言われる。このような中で、1956年に、原因不明の患者の入院が報告され、これが水俣病の公式発見と呼ばれている。水俣病は、工場排水によって汚染された海域に生息する魚介類に蓄積された有機水銀が人体に取り込まれ、その結果起こる中枢神経系の疾患として、世界に知られることになった。
水俣病は、1965年頃、昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水を原因として、新潟県阿賀野川流域でも発生した。また、富山県神通川流域においては、カドミウム、鉛、亜鉛等の金属類による水質や土壌の汚染を原因とするイタイイタイ病が発生した。
一方、エネルギー革命(石炭から石油への転換)が進展する中で、大気汚染も粉じんを中心としたものから、硫黄酸化物を中心とした汚染に形態を変化させ、また広域化してきた。とりわけ、1950年代後半以降に、日本各地で進められた石油コンビナートの形成は、硫黄酸化物による広域的な大気汚染や悪臭、水質汚濁等の問題を引き起こした。石油コンビナートからのばい煙を原因とする三重県四日市市のぜんそくは、当時の水俣病、イタイイタイ病等と並び、典型的な公害病として称された。
また、この時期には瀬戸内海における赤潮の発生や、臨海工業地帯における地下水使用量の急増による地盤沈下等も深刻化した。
このように、高度経済成長期には、重化学工業を中心とした生産活動が、環境影響への備えのないまま活発化し、明治時代から見られた公害がより深刻な被害となって、社会問題化した。また、日本各地での工業拠点の整備は、各地域の経済振興に貢献する反面、日本各地に公害問題を拡散させる結果となった。
(5)公害反対の世論の高まりと住民運動
高度経済成長期における環境問題の多発に伴い、一般市民も含めた「市民パワー」が現れてきた。例えば、1958年の江戸川の製紙工場排水による漁業被害をめぐる漁民と工場との乱闘事件は、水質汚濁対策を促進する契機になった。
この他、1963年から64年にかけて三島・沼津地域で起こったコンビナート建設反対運動は、これまでの農漁民対企業という従来の公害紛争の型を超え、広く一般市民の関心を集めた。高度経済成長政策の主要な柱である臨海コンビナートの立地が計画段階で公害問題を理由に中止されたことは、国や産業界、地方公共団体に大きな衝撃となった。
一方、自然破壊に反対する人々の動きも次第に活発化してきた。1950年代後半頃から国民生活が安定してくるにつれ、都市住民の間にすぐれた自然とのふれあいを求める気持ちが高まる一方、急激に過疎化が進行した農山村地域では、観光開発が進められた。しかし、道路建設等のこれらの観光開発は、自然保護に対する配慮の不十分さ、施工技術の遅れ等により自然破壊をもたらすとともに、自動車の排出ガス等による2次的な自然破壊を引き起こすことにより、結果的には自然の利用者に深い失望を与えることになった。富士スバルラインや石鎚山スカイライン等は批判の対象となった例であり、こうした批判を背景に、尾瀬道路主要地方道沼田田島線等は工事の中止や路線の変更に至った。
公害問題や自然破壊に対する住民の反対運動は、1960年代後半から大きなうねりとなり、環境配慮に係る市場の枠組みづくりに踏み出す1970年代を迎えることになった。
(6)食品公害と消費革命
公害病は、企業の生産活動に伴う環境負荷によって生じる問題であるが、高度経済成長期にはまた製品の使用段階あるいは廃棄段階の問題が顕在化した。特に、食品産業の工業化に伴う多種多様な食品添加物の使用や、農業の重化学工業化に伴う残留農薬問題、プラスチックの安全性やごみ問題等が、社会問題化した。
1955年には、最初の大規模な食品公害として死者133人、中毒患者1万2千人に及ぶ被害を出した森永ヒ素ミルク事件が発生した。これは、森永乳業徳島工場が粉乳の安定剤として混入した第2リン酸ソーダ(アルミ工場の副産物)に大量のヒ素が含まれていたことによるものだと解明された。この他、医薬品によるサリドマイド事件(1962年)、米ぬか油によるカネミ油症事件(1968年)等の、深刻な被害が発生した。
一方、高度経済成長期は、産業の発展とともに国民生活が大きく変動した。例えば、1953年には、国産の電気洗濯機が登場し、「電化元年」と呼ばれたが、その2年後にはテレビ、電気洗濯機と合わせて、電気製品の「三種の神器」が出揃うこととなった。こうした消費構造の変化を、1959年版国民生活白書では、「消費革命」と呼んでいる。
また、流通分野ではスーパーマーケットが登場した。国内最初のスーパーは、1953年に東京・青山にオープンした「紀ノ国屋」とされ、その4年後、現在のダイエーの前身となる「主婦の店ダイエー薬局」が、大阪・千林にオープンした。スーパーでは、商品単価を下げるために、大量流通を前提とする。このため、スーパーの普及に伴って、農産物を大量にかつ安定的に供給するために、特定農産物を集中的に生産する指定産地制度が設けられた。
家電製品の普及や農産物の大量流通等は、技術革新とともに、アメリカ的生活様式に追随する消費者の志向性によるものだと考えられる。高度経済成長期における環境問題は、企業の製造過程や製品における環境配慮があまりに希薄なことによる加害者が特定される問題だと言えるが、今日の環境問題の根本的要因である大量生産・大量消費・大量廃棄構造は、高度経済成長期において雛形がつくられたのである。
4.公害対策と省エネルギーの時代
(1)公害規制の整備と排出源対策
高度経済成長の歪みが大きな社会問題となり、1970年に至っては、「公害メーデー」等の全国規模の公害反対運動が起こり、「公害国会」が開催される等、公害に明け、公害に暮れる一年となった。この年からの世論は、経済成長のマイナスの側面に対する評価がますます厳しくなり、同年のNHKの世論調査では、「公害や物価上昇をもたらし、国民生活が一部の企業や産業の犠牲になってきた」として、経済成長を否定的に捉える人がはじめて55%と過半数を超えた。
また、1971年の総理府の世論調査では、工場全部の排出物を厳しく規制するという考え方に対して90%の人が賛成したことにも見られるように、公害対策の強化は、国民の一致した世論となるに至った。
既に、1967年に「公害対策基本法」、1968年に「大気汚染汚染防止法」が制定されていたが、1970年の「公害国会」ではこれらの法律の改正を含めて、公害関係の14法案の全てが可決・成立した。成立した法案の多くは、規制を強化し、事業者責任を明確化するものであった。
例えば、「公害対策基本法」をはじめとする公害対策の関係法から「経済の健全な発展との調和」を図りつつ公害対策を進めるといういわゆる「調和事項」が削除され、経済優先ではないかという国民の疑念を払拭した。規制については、大気汚染、水質汚濁に係る従来の指定地域制を改め、未汚染地域を含め全国を規制対象地域とするとともに、規制対象物質項目の範囲を拡大する法律が定められた。また、「公害防止事業費事業者負担法」に、事業者責任が規定され、公害防止事業についての事業者の費用負担義務が具体化された。
こうした法制度の整備による規制に追随する形で、企業は公害対策のための設備投資を進め、1970年代の公害防止のための設備投資は1960年代と比較して、飛躍的に増加した。
(2)石油危機による省エネルギー構造への転換
1970年代は、公害規制や係る事業者負担の枠組みが整備されることでスタートしたが、こうした公害規制への対応に加えて、2度の石油危機に遭遇し、経済の体質や環境配慮に係る姿勢が一変することになった。
第1次石油危機が勃発した1974年度には、戦後初のマイナス成長を経験した。1970年度から74年度の累積成長率(実質)は約20%であったが、1970年代後半の同率は約15%に低下し、さしもの高度経済成長も減速傾向を示すことになった。企業では、エネルギーの節約、人員配置の変更等を通じた徹底した減量経営が行われた。
この時代の動きの象徴的な事例を、自動車産業に求めることが出来る。自動車産業は、1960年から70年にかけて、生産量を11倍に伸ばし、1971年には国内の乗用車生産台数がドイツを抜いて、世界第2位まで成長した。しかし、追い風ばかりではなく、1969年には欠陥車問題があり、1970年には新宿区牛込の住民の血中鉛濃度が高いことや、杉並区の光化学スモッグが社会問題化した。
丁度この時期、米国では、マスキー法が制定された。同法は、自動車排ガス中の有害物質の抑制を目的にしたもので、75年型車からCO、HCを70年規制基準の1/10以下とすること、76年型車からNOxを71年型車平均排出量の1/10以下とするという2つの基準を定めた。これに呼応して、日本ではCOとHCを75年規制、NOxを78年規制としたが、米国は結局、石油危機のためにマスキー法の実施が延期され、日本が世界に先駆けることになった。
特に、本田技研工業(株)では、CVCC(複合渦流調速燃焼方式)エンジンを開発し、排ガス規制に対応するトップランナーとなった。このエンジンを持って、本田技研工業(株)の1974年の売り上げは、73年の60%増となっている。また、自動車業界全体でも、石油危機は国際競争力を高める結果となった。これは、ガソリンの高騰に伴って、米国で小型車ブームとなり、わが国の自動車輸出が急増したためである。
以上のように、環境規制の整備や石油危機は、結果としてわが国産業の技術力や国際競争力を高めたとみることが出来る。
(3)技術革新と知識集約化
明治維新後の工業化は、エネルギー革命(石炭から石油へのエネルギー転換)に支えられ、高度経済成長期に飛躍的なものとなったが、1970年代は環境や資源に配慮しなかったツケがわき出した時代であったと言える。
これらのツケ回しが産業界にフィードバックされたのが1970年代だが、以下の3つの側面の努力や変化によって、一定程度、問題を克服することが出来たと言える。
1つは、自動車の低公害型のエンジン開発や触媒開発等の例にみられるような技術革新である。生産性向上にひたすら振り向けられていた技術開発のパワーが、公害対策や省エネルギーに向けられることで、一定程度の環境負荷の抑制を図ることが出来た。これは、生産活動当たりの環境負荷排出原単位やエネルギー消費原単位を減少させるものであった。
2つめは、産業構造の変化である。1971年の通産省産業構造審議会の答申においては、知的活動の集約度が高い産業(知識集約型産業)を中核とし、これを支える基盤的産業やその他の産業における知識集約度の向上を志向することが示された。実際にも、電子計算機産業が育成され、資源・エネルギー多消費型の重化学工業から卓上電子計算機の小型化等に象徴される「軽薄短小型」の産業構造への転換が加速された。
3つめは、景気低迷によって、生産・消費量が抑制されたことである。これは、石油危機による物価高騰という外的要因によるものであり、結果として環境負荷を抑制させたという側面である。
以上のように、1970年代にわき出したツケは、技術革新と知識集約化によってクリアされ、その見返りとして日本の産業は新たな競争力を獲得することが出来た。
(4)農林漁業におけるツケ回しへの対応
工業界では、高度経済成長期におけるツケ回しを技術革新と知識集約化によって、一定程度克服したが、第1次産業はどうだったのか。
まず、農業においては、重化学工業化に巻き込まれて、農業機械の導入や農薬、化学肥料の消費拡大が進行した。農業機械の導入はまだしも、1970年代には農薬や化学肥料による食の安全性の問題がクローズアップされた。その契機となったのは、1964年に日本で翻訳出版されたレイチェル・カーソンの著作「沈黙の春」である。農薬による自然破壊を訴え、水銀を使用する農薬やDDT、BHC等の使用を禁止する引き金となった。1971年には、化学物質に依存した農業からの脱却を目指す「有機農業研究会」が発足した。この研究会は、元農林事務次官を代表幹事に、農学者、医師、協同組合関係者等が中心となって結成されたもので、これに刺激されて、各地域に有機農業が普及することになった。また、1974年には有吉佐和子が朝日新聞に「複合汚染」を連載し、消費者の間にも有機農産物の存在を知らしめることになった。
漁業の分野では、1970年代に商業捕鯨が国際的な非難に晒され、200カイリ水域が設定されることもあって、遠洋漁業から沿岸漁業に回帰する傾向がみられた。しかし、沿岸では、工場排水や赤潮による被害もあり、漁獲生産力はますます減少した。一方、農業と同様に、漁業従事者の減少と高齢化を補うものとして、漁船の性能向上や魚群探知機の進歩、漁網の改良等、設備・技術の高度化が進められた。技術の向上が乱獲によって、水産資源をさらに枯渇させるという悪循環が指摘されたのも、この頃である。資源管理がクローズアップされた1970年代、漁業では国内の漁獲管理や栽培漁業の進行等が図られたが、国内の漁獲高はますます減少し、水産物輸入をますます増大させることとなった。
一方、林業では、高度経済性成長期に大都市への人口流動が活発化し、住宅需要が増大する中で、スギやヒノキ、カラマツを主体とする植林(人工林化)が活発化した。しかし、国内の多くの人工林が伐採適期を迎えるつつあるのは、ようやく近年のことであり、1970年代に国内林業における環境配慮を進める動きは無かったと考えられる。高度経済成長期の日本は、東南アジアのタイやフィリピンから木材輸入を拡大させてきた。例えば、フィリピンでは、1950年代に日本のラワン材の買い付けが始まり、フタバガキ科の原生林の集中的伐採が進んだ。この結果、フィリピンのフタバガキ科の原生林の森林面積は、1969年の466万haから、1988年には99万haまで激減することになった。
以上のように、第1次産業も、公害問題や資源問題のクローズアップされた1970年代の洗礼を受けた。その動きは、農業はまだしも、漁業や林業においては、国内産業の衰退と輸入への依存体質を強めるものであり、環境配慮型への生産技術の向上や構造転換を促すものではなかったと言える。そして、輸入依存性を高めることで、ツケを海外に回し、見えない自然破壊を進める結果となった。