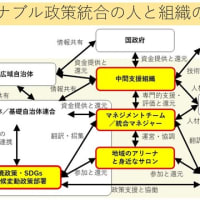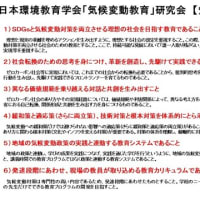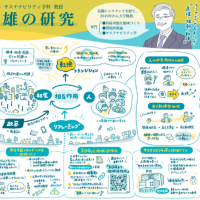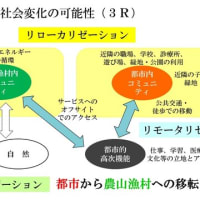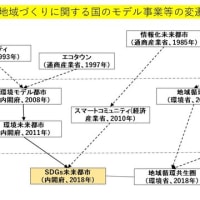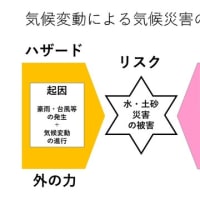1.関連研究の動向
●民俗学における漁労社会の把握
わが国における漁民とその社会に関する研究は、1930年代から1940年代にかけて、組織的にその姿を整えている。この時期は動力船の普及と遠洋漁業への進出、水産加工技術並びに漁獲物の運輸技術等に著しい進展のみられた時期であり、多くの沿岸漁村において近世以来の伝統的生産構造や生活構造が急速に変貌を遂げようとしていた時期であった。
全国の漁村で近世以来の伝統的生産構造が失われようとしている状況の中で、伝承資料を早急かつ組織的に収集する中心的役割を果たしたのが、澁澤敬三等により創設されたアチック・ミューゼアムであった。彼らが1930年後半から1940年代にかけて発刊した刊行物では、①漁村の文書資料の収集刊行、②漁村や漁業に関する社会経済史的研究、③聞書き調査を中心とした、漁村や漁民に関する民俗的研究が報告されていた。
漁撈民俗研究のもう一方の核として、柳田国男が主宰する郷土生活研究所同人による沿海村落の民俗資料の収集活動があった。柳田は1937~1939年、沿海村落の調査を行ない、1949年に『海村生活の研究』として刊行した。漁村民俗全般にわたって、それぞれ生業、社会、人生儀礼、祝祭と信仰、心意、衣食住と満遍なく考察されているが、漁具、漁法等の漁労技術に関してはほとんど欠落していた。また、記載方法は、問題項目別に調査村落を配列するという形をとっているため、特定項目について、全国的に事例を比較するには都合がいいが、逆にそれぞれの項目が特定の村落の中で、いかに有機的に結びつき、民俗的位相を示しているかを理解するには不都合であったとされる。
戦前の研究は、漁民のもつ特異な民俗に注目しつつも、大局においては、農民世界の延長線上に漁民の世界を把握するにとどまった。
近年、伝統的漁民の型を設定することによって、その複雑な存在形態を整理しようと試みる動きがある。その漁民類型化の指標として、a. 漁具・漁法 b. 漁場 c. 漁労形態 d. 漁労の内容と性格 e. 農業依存度と漁期 f. 心意的世界と海の相関が挙げられている。
●漁業の文化地理学
わが国の漁業に関する地理学的研究は、地理学の中でもその歴史は新しい。戦前の草分け的時代を経て、戦後、漁業経済学的研究の発展とともに、1950年代より活発化した。1960年代から1970年代前半にかけては、漁業地理学の内部において、文化地理学的な視点が徐々に見られるようになった。しかし、漁業地理学的研究は、経済地理学の中の小さな領域の一つとして、細々と生きてきたのが実状であった。
地理学の他の分野と比べて、漁業地理学の研究者は少ないにもかかわらず、研究対象は多岐にわたっている。現在でもその研究の方法や方向性は依然として明確にされていないといえよう。
●文化人類学的アプローチ
1970年代後半から、海洋と関連した事象を研究対象として、文化人類学的な研究方法を試みる海洋人類学という分野が生まれた。主なテーマは、人間の海への適応に関する研究、漁業共同体についての研究等である。
2.関連研究から得られる知見
●一本釣
釣漁は網漁と並ぶ主要な漁法であり、設備や道具等が比較的簡単であるから、広い範囲で早くから行なわれていた。釣漁は網漁に比較すると収量の少ないものであるから、それを主として生活をたてて行くには、量は少なくとも高く売れて利益の多いものを釣らなければいけなかった。
また、そういった高級魚の売れる市場に近いところでなければ、専業の釣漁村は成立しなかった。そのため、釣漁村は早くから大きな市場として成立していた大阪に近いところに多く発達し、次第に西瀬戸内海や日本海西部あるいは江戸を中心とする関東の海岸に広がっていったとされる。
西瀬戸内海への釣漁村の発達は、広島の草津、伊予の三津浜に市場ができたことと、生漁船の発達によって大阪・尼崎の市場とつながるようになったこと、そしてテグス(釣り糸)が発達したことによる。
この方法で、生魚を集めるにしてもその範囲は自ら決まってくるもので、日本海西部の本州側、朝鮮海峡に面した辺りまでが限度である。一本釣漁村は九州西辺には見られなかったが、後に優れた技術を持つ瀬戸内海漁民の進出によって、壱岐、対馬、五島辺りに釣漁村が発生している。
●延縄漁
延縄は、一条の幹糸に多くの枝糸を出し、それに何本もの釣り針をつけて一定時間海中に延えておき、引き上げるものである。一本釣りよりも能率的で技術も機械的である。一本釣りが遅れて発達した日本海岸においても、延縄漁は比較的早くから点々と行なわれていた。
佐渡の姫津では、1603年に石見から熟練した漁師を招いて、延縄を伝習したことが初めとされている。これから、石見の海岸では古くから行なわれていたことが分かる。丹後の島津では、1592~96年にタイ延縄をはじめ、1716年に若狭早瀬の漁夫が漂着して麻縄の使用を教え、カズラ縄を麻縄に変えている。近世初期にはかなりの数の延縄漁村が成立していたようだが、日本海一帯に延縄漁が一般化してくるのは幕末から明治にかけてであった。
延縄漁村が集中的に見られたのは、大阪湾沿岸を中心とする瀬戸内海で、和泉佐野の漁師等は既に室町時代の中頃に五島に出漁している。近世においては、室津(兵庫)、牛窓(岡山)、二窓(広島)等が延縄の基地として大きなものであった。淡路島の延縄は二窓から伝えられたものであるが、近世初期には東は志摩から西は日向までの間を往来して漁場を開拓し、日向延岡や鳥羽あるいは紀州南部村等にその技術を伝えた。
関東の延縄も西から伝えられたもので、相模においては1648-52に堺の与七郎という者が真鶴に移り住んでタイ縄を伝えたのが初めてである。安房や伊豆の島々には豊前から伝えられた。
この漁法が一般に広まるには多くの時間がかかった。伊豆の海岸では幕末ごろ、紀州の海岸では、江戸中期~幕末にかけてである。
イカ釣の技術は佐渡、隠岐等で特に発達した。イカを追って、次第に遠くに出るようになり、明治には西は対馬、東北は青森・秋田の海岸まで行くようになり、技術がそれらの地に伝えられた。この結果、日本海岸にも一本釣漁村は増えてきて、イカ釣の出稼漁によって生計のほとんどを支える能登の小木や蛸島のような漁村も出てきている。
●カツオ釣
カツオ釣りも主に一本釣であるが、太平洋岸に独自に発達したものであり、一本釣と区別される。
太平洋岸の釣漁村はカツオを対象として発達したといってもよく、その歴史はきわめて古い。カツオは生魚で供するよりも鰹節にして供給されるのが主であったから、輸送もきき、商品としての価値は古くから高く、早くから貢租物質として貢進されている。カツオの貢進地は、古くからカツオ漁村の成立したところであり、後々まで変わらなかった。主な貢進地としては、以下のものがある。
堅 魚:志摩、駿河、伊豆、相模、安房、紀伊、阿波、土佐、豊後、日向
煮堅魚:駿河
堅魚煎汁:駿河、伊勢
カツオ貢進のない国で、カツオ釣の盛んに行なわれているのは、薩摩・陸奥等がある。カツオは通り魚なので、地域ごとにそれぞれ地先で釣っているために漁場は決まっており、時期も決まっていたので、年間を通してカツオ釣を行なうところは少なかったが、紀伊、伊豆、薩摩では回遊するカツオを追って遠方に出漁していた。カツオ釣漁村が、漁場と密接な関係を持って成立し、発展している。
●近世前期と明治前期の海産物の特徴
海産物は、魚貝類自体の習性の他に、漁法や漁具などの操業技術にも大きく左右される。このため、近世前期の漁はその多くが沿岸の磯漁にとどまっており、漁法の発達した明治前期に比べ漁場が限定していた。例えば、鱈(たら)は越前のみ、海老(えび)は相模と伊勢、鰰(はたはた)は出羽などとなっている。
明治前期になると漁場の拡大に伴い地域性が薄められたが、それでも漁場の地勢や漁獲物販売市場との遠近といった自然的・経済的条件の影響は強く受けていた。
東日本と西日本の漁場では海産物にも多少の相違や特徴があり、東日本は鰊(にしん)・鮭(さけ)・鱒(ます)、西日本は鰤(ぶり)、中間地帯は鯖(さば)・鯛(たい)・鯵(あじ)、太平洋岸一帯は鰹(かつお)と大まかに区分することができる。
烏賊(いか)は東東北や間断的ながら北陸・山陰・肥前・対馬近辺が好漁場であった。より地方性の低い底魚の鱈(たら)は主に東日本の日本海側に、鰰(はたはた)(雷魚)は羽後のみに、鱸(すずき)は日本各地、なかでも南西に多く分布生息している。
参考文献:
宮本常一・川添登 編「日本の海洋民」未来社、1974年
●民俗学における漁労社会の把握
わが国における漁民とその社会に関する研究は、1930年代から1940年代にかけて、組織的にその姿を整えている。この時期は動力船の普及と遠洋漁業への進出、水産加工技術並びに漁獲物の運輸技術等に著しい進展のみられた時期であり、多くの沿岸漁村において近世以来の伝統的生産構造や生活構造が急速に変貌を遂げようとしていた時期であった。
全国の漁村で近世以来の伝統的生産構造が失われようとしている状況の中で、伝承資料を早急かつ組織的に収集する中心的役割を果たしたのが、澁澤敬三等により創設されたアチック・ミューゼアムであった。彼らが1930年後半から1940年代にかけて発刊した刊行物では、①漁村の文書資料の収集刊行、②漁村や漁業に関する社会経済史的研究、③聞書き調査を中心とした、漁村や漁民に関する民俗的研究が報告されていた。
漁撈民俗研究のもう一方の核として、柳田国男が主宰する郷土生活研究所同人による沿海村落の民俗資料の収集活動があった。柳田は1937~1939年、沿海村落の調査を行ない、1949年に『海村生活の研究』として刊行した。漁村民俗全般にわたって、それぞれ生業、社会、人生儀礼、祝祭と信仰、心意、衣食住と満遍なく考察されているが、漁具、漁法等の漁労技術に関してはほとんど欠落していた。また、記載方法は、問題項目別に調査村落を配列するという形をとっているため、特定項目について、全国的に事例を比較するには都合がいいが、逆にそれぞれの項目が特定の村落の中で、いかに有機的に結びつき、民俗的位相を示しているかを理解するには不都合であったとされる。
戦前の研究は、漁民のもつ特異な民俗に注目しつつも、大局においては、農民世界の延長線上に漁民の世界を把握するにとどまった。
近年、伝統的漁民の型を設定することによって、その複雑な存在形態を整理しようと試みる動きがある。その漁民類型化の指標として、a. 漁具・漁法 b. 漁場 c. 漁労形態 d. 漁労の内容と性格 e. 農業依存度と漁期 f. 心意的世界と海の相関が挙げられている。
●漁業の文化地理学
わが国の漁業に関する地理学的研究は、地理学の中でもその歴史は新しい。戦前の草分け的時代を経て、戦後、漁業経済学的研究の発展とともに、1950年代より活発化した。1960年代から1970年代前半にかけては、漁業地理学の内部において、文化地理学的な視点が徐々に見られるようになった。しかし、漁業地理学的研究は、経済地理学の中の小さな領域の一つとして、細々と生きてきたのが実状であった。
地理学の他の分野と比べて、漁業地理学の研究者は少ないにもかかわらず、研究対象は多岐にわたっている。現在でもその研究の方法や方向性は依然として明確にされていないといえよう。
●文化人類学的アプローチ
1970年代後半から、海洋と関連した事象を研究対象として、文化人類学的な研究方法を試みる海洋人類学という分野が生まれた。主なテーマは、人間の海への適応に関する研究、漁業共同体についての研究等である。
2.関連研究から得られる知見
●一本釣
釣漁は網漁と並ぶ主要な漁法であり、設備や道具等が比較的簡単であるから、広い範囲で早くから行なわれていた。釣漁は網漁に比較すると収量の少ないものであるから、それを主として生活をたてて行くには、量は少なくとも高く売れて利益の多いものを釣らなければいけなかった。
また、そういった高級魚の売れる市場に近いところでなければ、専業の釣漁村は成立しなかった。そのため、釣漁村は早くから大きな市場として成立していた大阪に近いところに多く発達し、次第に西瀬戸内海や日本海西部あるいは江戸を中心とする関東の海岸に広がっていったとされる。
西瀬戸内海への釣漁村の発達は、広島の草津、伊予の三津浜に市場ができたことと、生漁船の発達によって大阪・尼崎の市場とつながるようになったこと、そしてテグス(釣り糸)が発達したことによる。
この方法で、生魚を集めるにしてもその範囲は自ら決まってくるもので、日本海西部の本州側、朝鮮海峡に面した辺りまでが限度である。一本釣漁村は九州西辺には見られなかったが、後に優れた技術を持つ瀬戸内海漁民の進出によって、壱岐、対馬、五島辺りに釣漁村が発生している。
●延縄漁
延縄は、一条の幹糸に多くの枝糸を出し、それに何本もの釣り針をつけて一定時間海中に延えておき、引き上げるものである。一本釣りよりも能率的で技術も機械的である。一本釣りが遅れて発達した日本海岸においても、延縄漁は比較的早くから点々と行なわれていた。
佐渡の姫津では、1603年に石見から熟練した漁師を招いて、延縄を伝習したことが初めとされている。これから、石見の海岸では古くから行なわれていたことが分かる。丹後の島津では、1592~96年にタイ延縄をはじめ、1716年に若狭早瀬の漁夫が漂着して麻縄の使用を教え、カズラ縄を麻縄に変えている。近世初期にはかなりの数の延縄漁村が成立していたようだが、日本海一帯に延縄漁が一般化してくるのは幕末から明治にかけてであった。
延縄漁村が集中的に見られたのは、大阪湾沿岸を中心とする瀬戸内海で、和泉佐野の漁師等は既に室町時代の中頃に五島に出漁している。近世においては、室津(兵庫)、牛窓(岡山)、二窓(広島)等が延縄の基地として大きなものであった。淡路島の延縄は二窓から伝えられたものであるが、近世初期には東は志摩から西は日向までの間を往来して漁場を開拓し、日向延岡や鳥羽あるいは紀州南部村等にその技術を伝えた。
関東の延縄も西から伝えられたもので、相模においては1648-52に堺の与七郎という者が真鶴に移り住んでタイ縄を伝えたのが初めてである。安房や伊豆の島々には豊前から伝えられた。
この漁法が一般に広まるには多くの時間がかかった。伊豆の海岸では幕末ごろ、紀州の海岸では、江戸中期~幕末にかけてである。
イカ釣の技術は佐渡、隠岐等で特に発達した。イカを追って、次第に遠くに出るようになり、明治には西は対馬、東北は青森・秋田の海岸まで行くようになり、技術がそれらの地に伝えられた。この結果、日本海岸にも一本釣漁村は増えてきて、イカ釣の出稼漁によって生計のほとんどを支える能登の小木や蛸島のような漁村も出てきている。
●カツオ釣
カツオ釣りも主に一本釣であるが、太平洋岸に独自に発達したものであり、一本釣と区別される。
太平洋岸の釣漁村はカツオを対象として発達したといってもよく、その歴史はきわめて古い。カツオは生魚で供するよりも鰹節にして供給されるのが主であったから、輸送もきき、商品としての価値は古くから高く、早くから貢租物質として貢進されている。カツオの貢進地は、古くからカツオ漁村の成立したところであり、後々まで変わらなかった。主な貢進地としては、以下のものがある。
堅 魚:志摩、駿河、伊豆、相模、安房、紀伊、阿波、土佐、豊後、日向
煮堅魚:駿河
堅魚煎汁:駿河、伊勢
カツオ貢進のない国で、カツオ釣の盛んに行なわれているのは、薩摩・陸奥等がある。カツオは通り魚なので、地域ごとにそれぞれ地先で釣っているために漁場は決まっており、時期も決まっていたので、年間を通してカツオ釣を行なうところは少なかったが、紀伊、伊豆、薩摩では回遊するカツオを追って遠方に出漁していた。カツオ釣漁村が、漁場と密接な関係を持って成立し、発展している。
●近世前期と明治前期の海産物の特徴
海産物は、魚貝類自体の習性の他に、漁法や漁具などの操業技術にも大きく左右される。このため、近世前期の漁はその多くが沿岸の磯漁にとどまっており、漁法の発達した明治前期に比べ漁場が限定していた。例えば、鱈(たら)は越前のみ、海老(えび)は相模と伊勢、鰰(はたはた)は出羽などとなっている。
明治前期になると漁場の拡大に伴い地域性が薄められたが、それでも漁場の地勢や漁獲物販売市場との遠近といった自然的・経済的条件の影響は強く受けていた。
東日本と西日本の漁場では海産物にも多少の相違や特徴があり、東日本は鰊(にしん)・鮭(さけ)・鱒(ます)、西日本は鰤(ぶり)、中間地帯は鯖(さば)・鯛(たい)・鯵(あじ)、太平洋岸一帯は鰹(かつお)と大まかに区分することができる。
烏賊(いか)は東東北や間断的ながら北陸・山陰・肥前・対馬近辺が好漁場であった。より地方性の低い底魚の鱈(たら)は主に東日本の日本海側に、鰰(はたはた)(雷魚)は羽後のみに、鱸(すずき)は日本各地、なかでも南西に多く分布生息している。
参考文献:
宮本常一・川添登 編「日本の海洋民」未来社、1974年