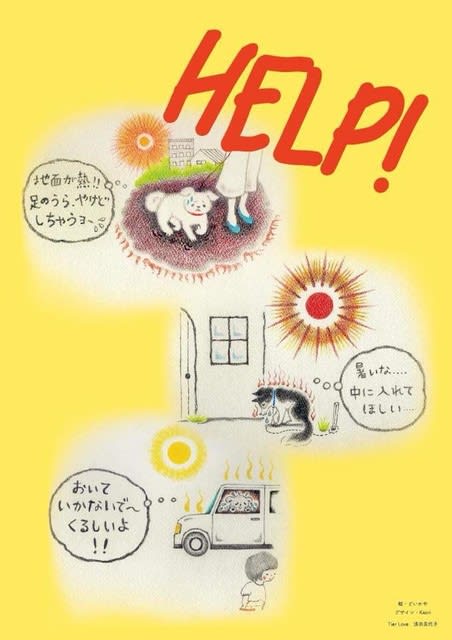杉並区 狂犬病予防定期集合注射の実施などに関するお知らせ
(28年3月21日)
28年度の杉並区狂犬病予防定期集合注射を、
東京都獣医師会杉並支部所属の協力動物病院で実施します。
会場により、接種できる曜日・時間が異なりますので、
個別に送付する「注射のお知らせ」「会場一覧表」をご覧ください。
なお、これから犬の登録をする方は、生活衛生課までお問い合わせください。
 ★狂犬病予防定期集合注射のご案内
4月2日(土曜日)~17日(日曜日)の16日間。
★狂犬病予防定期集合注射のご案内
4月2日(土曜日)~17日(日曜日)の16日間。
•実施する各会場の場所・時間帯は、個別に飼い主あてに送付いたします。
•会場一覧は、下記添付ファイルからもご覧いただけます。
★費用
犬一頭につき、注射料3,100円、注射済票550円(即時交付)。
新規登録の場合は別途、登録料3,000円
「注射のお知らせ」様式が変わります
今年度より、今までのハガキから、A4サイズの色紙「注射のお知らせ」に様式が変わります。
今年度は黄色い用紙ですので、注射当日は、その用紙をご持参ください。
各会場への車での来場はご遠慮ください。
★実施動物病院一覧はコチラから
 ★犬の飼い主の皆さんへ
登録と狂犬病予防注射
★犬の飼い主の皆さんへ
登録と狂犬病予防注射
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬の生涯に一度の登録と、
年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
また、鑑札・注射済票は犬に付けることになっています。
これらを犬に付けておくと、逃げてしまった際に飼い主に連絡がつきやすくなります。
トイレの後始末
散歩に出かけるときは、フンを始末する道具を必ず携帯し、
家に持ち帰り、きちんと処理しましょう。
また尿もそのままにせず、水で流すなどの心遣いをお願いします。
マナーを守ってきれいな街にしましょう。
鳴き声
無駄ぼえをするような場合は、室内へ入れる、散歩に連れていく、
カーテンなどで外からの刺激を遮断する等、ストレスを和らげるよう努め、
近隣への配慮をお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★犬が人をかむ事故(咬傷事故)が増えています
宅配業者や登下校中の児童、また通行人がすれ違いざまに犬にかまれる、
という事故が起きています。
★注意していただきたいこと
•外に出たときは、小型犬でも必ずリードにつなぎ、長さは短めに持ってください。
思わぬ事故を避けるためにも、道路・公園等では周辺との安全な距離を保ち、
すぐに犬を制御できるようにしてください。
•伸縮性リードを使用するときでも、道路や狭い場所など、人が行き交うところでは、
リードを短くロックしてください。
•家の中・敷地内でも、放し飼いにせず鎖等でつなぐか、囲いの中で飼ってください。
門扉の前や玄関で、来訪者や通行人に飛びつかないようにしましょう。
•犬が人をかんでしまったときは、応急処置や医療機関の手配など、
誠意ある対応をお願いします。
また、すぐ保健所にも連絡してください。
(東京都条例により、犬の飼い主には事故の届け出義務があります。)