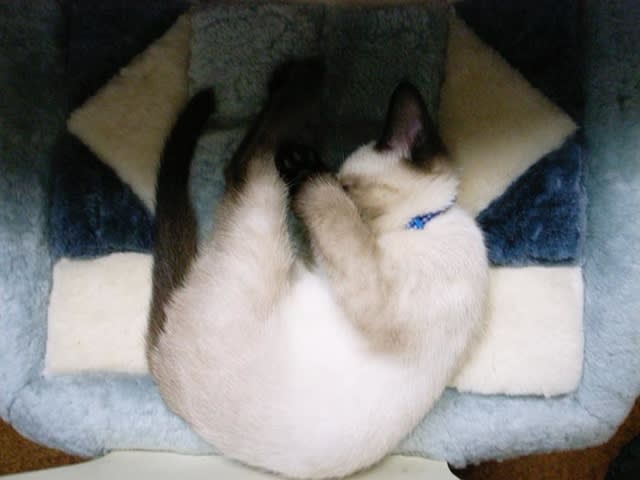肉球ストラップ(ネットより)

肉球の肩たたき(ネットより)
ネコの肉球に癒やされる人は多いですね。
見た目も可愛いですが。その感触がまたたまらなく良いです。
肉球を模した「ネコの手の自撮り棒」「肉球の孫の手」「ネコの手肩たたき」なんかも今はあるそうです。
でもネコにとって、肉球はとても大切なものなのです。
ネコは人のように全身に汗腺を持たないですが、肉球にだけは汗腺があります。
ですから、驚いたり、緊張したりすると肉球が湿ってきます。
ウソ発見器をネコに付けるとしたら、肉球に付けることになるでしょうね。(笑)
ネコの肉球が湿るのは、脚を滑らさないためです。
人間もサルから受け継いで、緊張したりすると手のひらや足の裏に汗をかきます。
木の上で生活していたサルが敵に襲われると大量に手足のひらに汗をかいて、
逃げるときに木から滑らないようにしているのですが、その習性を人間も受け継いでいるのです。
ネコの肉球はそれ以外にクッションの役目をしていて、足音を消すはたらきをしています。
また肉球には神経がたくさん来ていて、脚の置かれている下の状態を敏感に感じることが出来ます。
危なっかしい高いところを平気でスタスタ歩けるのもこの肉球にたくさんある神経のおかげです。
ですから、肉球を触るときには優しく軽く触らないといやがります。
ネコにとって、肉球は人間を癒やすためにあるのではなく、大切なはたらきがあるのですね。