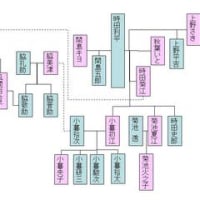日本での死生観に彼岸・あの世・常世がある。神話の世界では道教の神仙思想の蓬莱山、大陸渡来の西方浄土の阿弥陀如来信仰と太陽信仰、浦島太郎の竜宮に象徴される海の向こうを理想国とする思想がある。中世以降には紀州熊野の補陀落信仰があり、臨終に際しては海上の彼方にある補陀洛つまり観音浄土での往生を目指す。熊野地方には徐福伝説があり、熊野地方ではこれらが習合して伝えられる。我が国特有の死生観であると筆者は言う。
大晦日、除夜には異界から神やマレビトが訪れるので徹夜して身を慎む行為がある。一年の罪や穢れを払い新しい生命が甦るという信仰である。庚申信仰は庚申の日の夜に徹夜する信仰である。江戸時代には修験道や仏教、神道とも結びついて全国的に庚申信仰組織が流行することもあった。神道では猿田彦を祀り、仏教では青面金剛を本尊とするが、「見ざる言わざる聞かざる」の三猿の象が祀られるようになった。大晦日というのは冬至=太陽の光が最も弱くなるとき、つまりここからは光明あふれる春に向かう転換点である。除夜に108つの鐘をつくのは中国の風習、日本では煩悩を洗い清めるとされた。
宇治の平等院鳳凰堂は定朝作の阿弥陀像がある。周囲には九品の来迎図が描かれ、眼前には浄土の全容が浮き上がり、さらには外界とつながっている。鳳凰堂は東面、前景には阿字池が南北に広がる。その向こうには宇治川が流れ、その向こうには醍醐山、鷲峰山に連なる山脈が見える。平等院は難波の四天王寺のように、彼岸の中日に平等院の頂上にそびえ立つ二羽の鳳凰を挟んで、真東から昇る太陽を浴びて輝き、やがて真西に沈む太陽は西方浄土への憧憬をかきたてる構造であるという。つまり平等院の来迎図は壁に書かれているのではなくて、こういう平等院全体のなかに位置する建築空間として捉える必要があるという。
日本のお墓は、前方後円墳から五輪塔墓、柱墓へと変遷した。前方後円墳は巨大であり一部貴族が対象。五輪塔墓は平安中期からであり貴族武士階級から一般化した日本独自の形式である。下から四角・円・三角・半円・団(如意輪形)であり地・水・火・風・空の五大要素を意味したインド密教に由来する。宇宙の象徴である。その後の石柱形は五段形式の簡略形であり抽象化したものと考えられる。
観音信仰は法華教の普門品に説かれる観音菩薩の活動に基づく。衆生を救うために33の体に変身すると言われる。救世、千手、馬頭、如意輪などが観音のバリエーションである。南海の補陀落に住むとされ阿弥陀如来の脇侍である。聖徳太子が救世観音を尊崇したことから広まったという。観音信仰はは現世利益であり女性のイメージをもつ。観音信仰は磐座、磐境信仰と結びつくことがあるので山の洞穴に観音像が祀られている所もある。
巡礼にはカミの巡礼、聖者の巡礼、そして庶民の巡礼がある。アマテラスの遍歴はカミの巡礼である。比叡山の千日回峰行は聖者の巡礼、四国88箇所霊場巡りや観音霊場巡りが庶民の巡礼である。巡礼は熊野曼荼羅や那智参詣曼荼羅などになり、江戸時代には富嶽三十六景や東海道53次図絵などを生んだとも考えられる。
大阪の四天王寺は講堂ー金堂ー塔ー中門という南北一直線にならぶ南面構造である。そして東西にも東西の神聖軸があり、西には西大門があり西方極楽浄土を意識している。金堂の内部では南に釈迦、東が薬師、北が弥勒、西が阿弥陀の四仏が祀られる。これをめぐるようにして四天王が南面して並ぶ。沖縄の御嶽は社殿も西南をむいているのはこの聖地の方向を意識しているという。
日本における仏教は日本古来の伝習や言い伝え、その上に道教は神道などが重層的にかぶさり習合していることがよくわかる。