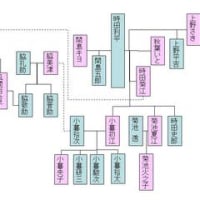沖縄の姓はほとんどが地名からきていて、昔はあちこちに中の字を使った地名があったらしい。ところが、17世紀の後期、第二尚氏・尚益の世子・尚貞が中頭中城間切を世襲し、中城王子を称するのにともなって、姓や村名に「中」の字を使用することが禁止されたのだそうだ。「中は高貴な字であるからして、王家以外の者が使ったらイカン」という布令を出した。これによって、浦添の中間は仲間、沖縄市の中宗根は仲宗根といった具合に改称させられた。沖縄に「仲」が多いのはお上の布令でそうなった。
沖縄にはおよそ1500種類の姓があるといわれているのだが、そのほとんどが内地にない異国風の珍しい姓ばかりで、真栄田・真栄里・仲宗根のように3文字の姓が際立って多いのが特徴。一説には沖縄の姓の半数近くを3文字姓が占めているといわれる。なぜこうした姓が生まれにいたったかというと、薩摩藩の琉球統治政策と深く関係しているらしい。琉球が薩摩藩の侵攻によってその属国になるのは1609年。それ以降、薩摩藩は「異国」を従えていることを権威づけるために、琉球が外国であることを演出するさまざまな政策を遂行する。手始めに服装や髪型を異国風に装わせ、1624年になると今度はさらに「大和めきたる名字」の使用禁止を令達する。これによって、たとえば東という姓は「比嘉・比謝」に、福山が「譜久山」、船越は「富名腰」と表記変えされ、3文字姓が増えた。沖縄の元々の姓は日本のそれに近いものだったかもしれず、沖縄の歴史家・真境名安興は、沖縄の姓は日本の姓に近かったのに、薩摩藩の政策によって「異国的」なものに改称させられたという論文を発表している。
こうした話は沖縄県の歴史にも触れられていなかった重要な史実ではないか。
ドタバタ移住夫婦の沖縄なんくる日和 (幻冬舎文庫)