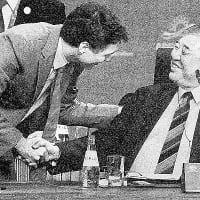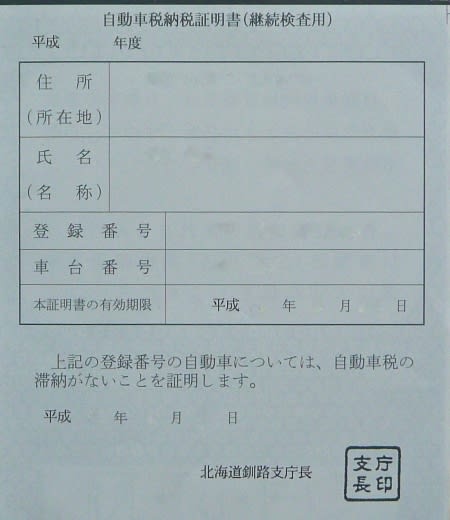
 宮城・岩手・福島三県では、東日本大震災による津波で大量の自動車が流出破壊したため、「車の所有者が自治体に納付する自動車税が今年度で総額110億円程度の減収となる見通し」(8月19日付『讀賣新聞』第1面)だという。
宮城・岩手・福島三県では、東日本大震災による津波で大量の自動車が流出破壊したため、「車の所有者が自治体に納付する自動車税が今年度で総額110億円程度の減収となる見通し」(8月19日付『讀賣新聞』第1面)だという。
自動車税は都道府県の自主財源、軽自動車税は市町村の自主財源としてそれぞれの地方自治体が自由に使途を決めることができる。「4月の地方税法改正で、車を津波で失った被災者が使用不能になった車を廃車にして買い替えた場合、2013年度まで最大3年間非課税となった。非課税分は県の減収となるため、国は交付税で減収分を100%補充する」(同新聞)ことになっているが、被災地では食べるのに精一杯で、車の買い替え需要は伸び悩んでいる。三県の昨年度の自動車登録台数は約二百三十四万台、税収額は合わせて約八百三十三万円というから、前年比10~15%の減収分を補償する長期的対策が必要だろう。 被災地での車の買い替えには、需要の伸び悩みのほかに、非課税及び交付税による補償とは次元の異なる別の問題が存在する。「津波で車を流された被害者が、税金や維持費が安い軽自動車に買い替える動きが加速している」(同新聞・第36面)というのだ。軽自動車税は市町村の収入となるため、県の大震災復興資金がそれだけ減少することになる。
被災地での車の買い替えには、需要の伸び悩みのほかに、非課税及び交付税による補償とは次元の異なる別の問題が存在する。「津波で車を流された被害者が、税金や維持費が安い軽自動車に買い替える動きが加速している」(同新聞・第36面)というのだ。軽自動車税は市町村の収入となるため、県の大震災復興資金がそれだけ減少することになる。
軽自動車の需要は大震災とは関係なく旺盛で、全国軽自動車協会連合会が八月十二日に発表した統計によると、前年度末時点の「全国の軽自動車普及台数が100世帯当たり50.6台と、過去最高を更新」(8月13日付・同新聞・第10面)した。経済性と運転性能向上により普通車から軽自動車に乗り換える傾向が長期的に持続しているところに、大震災で生活資金が限られる被災地の需要が加わったわけだ。県の税務担当者の嘆きは分からないでもないが、普通自動車から軽自動車への流れは今後も続くだろう。復興のための資金は、原発による災害の元である国と東電に面倒を見てもらおうではないか。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事