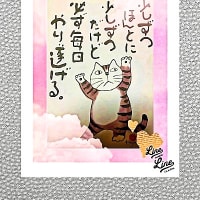現職の時、私は、四十歳ころから退職まで二十数年間、通勤に、鞄ではなく風呂敷を愛用した。たまたま『読売家庭版・ヨミー/プレゴ北海道』通巻517号 (讀賣新聞北海道支社) で、風呂敷の特集を掲載していたので、興味深く読んだ。
私の場合は、特集のタイトル「おしゃれに使いこなそう」などというものではなかった。特別大きな物でない限り、仕事に使う資料・書籍・文房具をほとんど包めるので、利便性を珍重しただけで、包み方や結び方には頓着しなかった。
私が持ち運ぶ資料や書籍は、嵩のわりに重いので、素材は、白峰紬の銘がついたアセテート製。表が青紫で、裏が朱の大きめの二四巾(にしはば)を、女房が常に用意してくれた。
風呂敷包みを脇に抱えて職場に入ると、若い女子職員が不思議そうに眺めるのが常だった。風呂敷など見たこともない年齢だから、「変なおじさん」と思ったのだろう。ま、実際、変なおじさんには違いなかった。
贈答品を包む風呂敷の伝統的な包み方は、平包み・お使い包み・隠し包みの三種類が基本(上掲『読売家庭版』参照)だが、昨今の北海道の一般家庭では、そのような堅苦しい作法は消滅してしまった。私は、少年時代に母の儀礼作法を見て、かすかに記憶に留めているに過ぎない。今の贈答品は、すべて宅配便に取って代わられた。
<上右の写真は、『読売家庭版・ヨミー/プレゴ北海道』通巻517号 (讀賣新聞
北海道支社) からの転写>
最近の「行住坐臥」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事