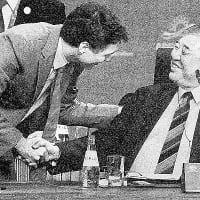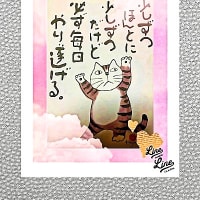米国の「サブプライムローン」関連の証券化商品所有について、渡辺金融相は、11月22日の閣議後の記者会見で、日本の金融システムへの影響に楽観的な見通しを示したが、27日の農林中央金庫の発表(11月28日付『北海道新聞』第8面〈経済〉)で、九月中間決算の損失は千五十七億円に上り、翌年三月末には六千二百六十億円に膨らむと予想している。
米国の「サブプライムローン」関連の証券化商品所有について、渡辺金融相は、11月22日の閣議後の記者会見で、日本の金融システムへの影響に楽観的な見通しを示したが、27日の農林中央金庫の発表(11月28日付『北海道新聞』第8面〈経済〉)で、九月中間決算の損失は千五十七億円に上り、翌年三月末には六千二百六十億円に膨らむと予想している。
12月4日投稿≪サブプライム損失≫で記したように、銀行・証券のほかに、保険関係では、<あいおい損害保険>がトップで、二百五十二億円の損失を計上している。
米欧の金融市場が抱える損失額(OECD発表で、約三十三兆円)と比較すると、日本の損失額は圧倒的に少ないが、米金融大手シティグループの動き次第で、東京市場の株式・為替は乱高下を繰り返し、証券市場は油断できないだろう。
世界的な金融不安を払拭するため、米欧の中央銀行五行は、12月12日に資金の協調供給体制を打ち出した(12月14日付『讀賣新聞』第11面〈経済〉)が、具体的な救済基金の創設は、日本を含む主要各国の金融界の思惑が絡んで難航した。とりわけ米金融界の足並みの乱れが主原因となって、基金創設は断念された。
推進役の米大手三銀行(シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン・チェース)が基金創設を断念したことによって、米欧の金融機関は、「自力再生『いばらの道』」(12月23日付『讀賣新聞』第7面〈経済〉)を歩むことになった。そもそもが、一行当たり50億ドルという巨額の要請に、米欧以外の金融機関が簡単に応じられるわけがない。虫のよい話だったのである。
だからといって、日本の金融界も安穏とはしていられないだろう。しっかりとした金融政策を持って、問題に対処しなければならない。自社の損金処理だけに拘り、世界の金融の流れに目を向けなければ、思わぬ落とし穴にはまりかねない。
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事