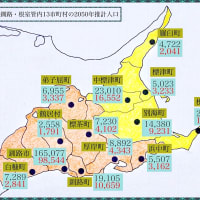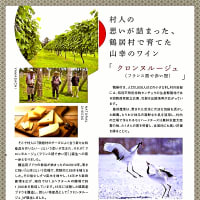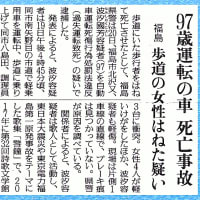市道<雄別阿寒線>のバス停<知茶布>から知茶布林道に入ってすぐ左に、<知茶布隧道跡の地>という記念碑が建立されている。
市道<雄別阿寒線>のバス停<知茶布>から知茶布林道に入ってすぐ左に、<知茶布隧道跡の地>という記念碑が建立されている。
明治三十九年に富山・静岡両県から三十三戸がこの地に入植したが、北辺厳寒の樹海開拓は想像を絶する難行であり、昭和二十三年残存八戸、昭和三十九年全戸離農という結果に終わった。
記念碑は、十四名の若者が昭和二十三年に隧道掘削の難工事に挑んだ二年有余の苦闘を称えて、平成十一年に旧阿寒町が建立した。
 知茶布林道入り口から三㌔奥に、最後に離農した安池家によって、昭和六十三年に建立された記念碑が開墾跡地に立っている。
知茶布林道入り口から三㌔奥に、最後に離農した安池家によって、昭和六十三年に建立された記念碑が開墾跡地に立っている。
祖父の入植から三代、志成らず開拓地を去らざるを得なかった安池家の無念は如何ばかりだったことか。しかし、入植の跡も見極められない開拓地の存在を思えば、記念碑が建立できることは、まだ恵まれているかもしれない。私の父方の祖父は、明治三十年代末に知床半島内部に入植したが、開墾を受けつけない自然環境の厳しさに、三年も持ち堪えられなかった。厳冬期に孤立し、網走村に助けを求めて九死に一生を得たという。
 釧路市の鳥取地区は、明治政府の旧士族俸禄公債化によって生活に窮した旧鳥取藩士が、北辺防備を名目に、旧阿寒川下流地域への入植を認められ、明治五年に鳥取村が開村されたのが基である。
釧路市の鳥取地区は、明治政府の旧士族俸禄公債化によって生活に窮した旧鳥取藩士が、北辺防備を名目に、旧阿寒川下流地域への入植を認められ、明治五年に鳥取村が開村されたのが基である。
一口に、北海道開拓・入植といっても状況は千差万別、旧士族と屯田兵と民間人とで扱いに大きな違いがあったように思われる。釧路市内で、鳥取百年記念館のような豪華な城は他に存在しない。
最近の「社 会」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事