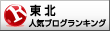何せ、今週中に日蓮はざっと主要箇所を学習して、来週は「浄土真宗」に移りたいのでちょっと急ぎます・・・。
何で?だって、最初に読んでる本がこの2冊だから・・・。深い意味はありません。
本日は「四大法難と折伏について」です・・・。
~四大法難~
1)松葉谷法難(まつばがやつほうなん)
1260年(文応元年)8月、日蓮が「立正安国論」を執権北条時頼に献上したことから、念仏信徒が日蓮を殺そうと鎌倉松葉谷の草庵を焼き討ちにした。日蓮は奇跡的に脱出して下総国(千葉県)に難を避ける。
2)伊豆法難(いずほうなん)
松葉谷法難の翌1261年(弘長元年)5月、日蓮の勢いに危機感をもった念仏信徒らは、日蓮を危険人物として幕府に訴え、日蓮は伊豆に流罪となる。赦免されるまでの1年9ヶ月のあいだに日蓮は「四恩抄」や「教機時国抄」などを著す。
3)小松原法難(こまつばらほうなん)
1264年(文永元年)10月、重病の母を見舞いに郷里小湊に帰ってきた日蓮を地頭東条景信ら数百人の念仏信徒が襲撃。弟子を殺され、眉間に傷を負うが奇跡的に助かる。
4)龍口法難(たつのくちほうなん)
1271年(文永8年)9月、日蓮は再び逮捕される。幕府は佐渡流罪をいいわたすが、護送の途中、鎌倉龍口で処刑する予定だった。ところが、まさに首を斬られる寸前、突如、雷鳴が響き、稲妻が走った。兵士たちは恐れをない、日蓮は処刑されることなく佐渡へ流罪となる。
・・・一口メモ・・・
日蓮と言えば「法華経」ですが、この「法華経」に法難のことが書かれています。
法華経の勧持品第13のなかで、お釈迦様が「三類の強敵」による法難を予言。
三類の強敵とは、俗衆増上慢・道門増上慢・せん聖増上慢の3つで、大衆・僧たち・そうして上人と呼ばれる人物までが「法華経」をひろめようとする者に迫害を加えるとしていると書かれています。
しかし、「法華経」は「仏陀を敬信して忍辱の鎧を着よう。我々は命を惜しまない。ただ無上の道が失われることのみ惜しむ」と邪悪な信仰に染まった人々を救済するためには当然覚悟すべき受難であるとし、命がけで耐え忍べと説く。
このことから日蓮は、法難を覚悟していたと言われている。
~折伏(しゃぶく)とは~
それぞれの宗派の長所を育成して教化するのではなく、相手の欠点を徹底的に論派して正しい信仰に導くことをいう。
なお、他宗教のような穏やかで寛容的な布教法を摂受(しょうじゅ)摂引容受という。
したがって日蓮の他宗派への批判は容赦なく、次の四箇格言が有名。
(念仏無間)
念仏は無間地獄に堕ちる業因。
(禅天魔)
禅は所衣の経典をもたず権力者に取り入ろうとする天魔。
(真言亡国)
真言の祈祷は天変地異の災害に無力な亡国の祈祷。
(律国賊)
貧者を救済するといいながら、慈善事業資金を集める律宗は貧者に犠牲を強いる国賊。
日蓮は末法の世においては、お釈迦様の時代のような仏教のひろめ方は不可能という考えから折伏による「法華経」の布教しかないとした。
念仏信徒との対立は、この折伏に原因があった。
本日はここまで、おおよその要点はこんな感じでしょうか?
「法華経」に関しては、一通り宗派の勉強が終ったら更に掘り下げる意味で再度学習します。
今回は、それぞれの宗派のポイントをつかめれば・・・。と思ってます。
何せ初心者なので・・・。
明日は、日蓮の弟子達にせまります。
何で?だって、最初に読んでる本がこの2冊だから・・・。深い意味はありません。
本日は「四大法難と折伏について」です・・・。
~四大法難~
1)松葉谷法難(まつばがやつほうなん)
1260年(文応元年)8月、日蓮が「立正安国論」を執権北条時頼に献上したことから、念仏信徒が日蓮を殺そうと鎌倉松葉谷の草庵を焼き討ちにした。日蓮は奇跡的に脱出して下総国(千葉県)に難を避ける。
2)伊豆法難(いずほうなん)
松葉谷法難の翌1261年(弘長元年)5月、日蓮の勢いに危機感をもった念仏信徒らは、日蓮を危険人物として幕府に訴え、日蓮は伊豆に流罪となる。赦免されるまでの1年9ヶ月のあいだに日蓮は「四恩抄」や「教機時国抄」などを著す。
3)小松原法難(こまつばらほうなん)
1264年(文永元年)10月、重病の母を見舞いに郷里小湊に帰ってきた日蓮を地頭東条景信ら数百人の念仏信徒が襲撃。弟子を殺され、眉間に傷を負うが奇跡的に助かる。
4)龍口法難(たつのくちほうなん)
1271年(文永8年)9月、日蓮は再び逮捕される。幕府は佐渡流罪をいいわたすが、護送の途中、鎌倉龍口で処刑する予定だった。ところが、まさに首を斬られる寸前、突如、雷鳴が響き、稲妻が走った。兵士たちは恐れをない、日蓮は処刑されることなく佐渡へ流罪となる。
・・・一口メモ・・・
日蓮と言えば「法華経」ですが、この「法華経」に法難のことが書かれています。
法華経の勧持品第13のなかで、お釈迦様が「三類の強敵」による法難を予言。
三類の強敵とは、俗衆増上慢・道門増上慢・せん聖増上慢の3つで、大衆・僧たち・そうして上人と呼ばれる人物までが「法華経」をひろめようとする者に迫害を加えるとしていると書かれています。
しかし、「法華経」は「仏陀を敬信して忍辱の鎧を着よう。我々は命を惜しまない。ただ無上の道が失われることのみ惜しむ」と邪悪な信仰に染まった人々を救済するためには当然覚悟すべき受難であるとし、命がけで耐え忍べと説く。
このことから日蓮は、法難を覚悟していたと言われている。
~折伏(しゃぶく)とは~
それぞれの宗派の長所を育成して教化するのではなく、相手の欠点を徹底的に論派して正しい信仰に導くことをいう。
なお、他宗教のような穏やかで寛容的な布教法を摂受(しょうじゅ)摂引容受という。
したがって日蓮の他宗派への批判は容赦なく、次の四箇格言が有名。
(念仏無間)
念仏は無間地獄に堕ちる業因。
(禅天魔)
禅は所衣の経典をもたず権力者に取り入ろうとする天魔。
(真言亡国)
真言の祈祷は天変地異の災害に無力な亡国の祈祷。
(律国賊)
貧者を救済するといいながら、慈善事業資金を集める律宗は貧者に犠牲を強いる国賊。
日蓮は末法の世においては、お釈迦様の時代のような仏教のひろめ方は不可能という考えから折伏による「法華経」の布教しかないとした。
念仏信徒との対立は、この折伏に原因があった。
本日はここまで、おおよその要点はこんな感じでしょうか?
「法華経」に関しては、一通り宗派の勉強が終ったら更に掘り下げる意味で再度学習します。
今回は、それぞれの宗派のポイントをつかめれば・・・。と思ってます。
何せ初心者なので・・・。
明日は、日蓮の弟子達にせまります。