本日、第96回 米国アカデミー賞の授賞式があり、日本の「ゴジラ-1.0」が視覚効果部門を受賞されました。
この賞はその時代を代表する先進的な映像作品、特にSF作品に贈られてきた賞であり、今回アジア初の快挙です。
また、先日には第47回日本アカデミー賞の最優秀作品賞を含む8冠も受賞され、このゴジラ70年、古希の慶節にこの上ない栄誉を得られた事、心からお慶び申し上げます。
そして当宮では、令和6年2月3日からゴジラ御守を授与しております。
この御守は、令和3年(2021)。当宮で男の子向けの新しい御守を検討していた頃、当宮の氏子さんでもある東宝㈱さまで恒例の神事があり、当宮とは長年のお付き合いもある事から、男の子向けのキャラクターについてご相談させて頂いたところ、ゴジラ御守の構想が出て来たのがそもそもの始まりでした。しかし、その時点では半分冗談のように考えておりましたが、
令和4年(2022)2月24日に、ロシアがウクライナに侵攻した際、核兵器の使用の危機という話が聞こえてくるにつれて、核兵器の落し子ともいうべき初代ゴジラを生み出した、当時の方々に思いを致し、まさに今の世にこそゴジラが必要なのではと心を後押しし、
また、ちょうど、劇中でゴジラが大阪梅田・茶屋町にやってきた作品「ゴジラVSメカゴジラ(平成5年(1993)公開)」の公開から令和5年12月で30周年である事に気づき、またこの作中でゴジラは我が子であるベビーゴジラを大切にする描写がある事から、子供向けの御守を模索していた当宮としては、これもやはり何かのご縁かと思い立ち、そこから本格検討に入り、ゴジラ御守の奉製に着手する事になりました。
しかし、時期がちょうどコロナの真っ只中でしたので、中々一気には進められない状況ではありましたが、その中で、ゆっくりとしか動かせないのであれば、品質を高める時間にすべきだと思い、
平成11年(1999)に公開された、「ゴジラ2000 ミレニアム」で本物のゴジラをデザインされた、西川伸司先生にゴジラの絵をお願いし、不躾なお願いにも関わらず、先生には大変丁寧にお進め頂き、素晴らしいゴジラ(通称:ラドゴジ)を一から描き起こして頂きました。 ちなみに当宮で当時お手伝いを頂いていた巫女さんが、西川先生が特任教授を務められている嵯峨美術大学・短期大学の学生さんだった事も西川先生にお願いする一つのきっかけになりました。
御守の裏面には、「ゴジラVSメカゴジラ」で、ゴジラが梅田・茶屋町にやってきた時、一緒に映像に映り込んでいた、当宮の御旅社と、茶屋町アプローズタワー、MBS(毎日放送)を織り込み、また梅田の代名詞ともなっているHEPの赤い観覧車と、梅田の梅の字の由来にもなった当宮の梅を配したデザインを整え、令和5年12月に奉製を開始しました。
令和6年2月2日。当宮の御祭神である、天神さまこと菅原道眞公が梅田に到来された日と同じ日にゴジラ御守は当宮にお納めされ、同日、困難打破、身体健康、子供愛護、往来安全の祈念を込め、翌、2月3日、ゴジラ御守の授与を開始しました。
その初回授与の際は、想像以上のゴジラ人気を目の当たりにする事になり、当宮側の準備不足もあって、あっという間にご用意した先行分の御守は出体終了となってしまい、後からお参り頂いた方々には申し訳ない形となってしまいましたが、
それから御守の奉製職人の皆様にはご無理を言って、大急いで奉製を進めて頂き、3月8日の日本アカデミー賞で「ゴジラ-1.0」が最優秀作品賞を含む8冠受賞の慶報を受けた翌日の、3月9日に第2回目授与を開始。初回授与の時よりも大変多くの参拝者で賑わい、通行される方が驚かれるほどでした。
そして本日の米国 アカデミー賞の受賞を受け、本当にゴジラ御守の奉製を思い立ってから今日まで間、大神さまが次から次へとご縁を繋いでくださって、いまの核戦争危機への警鐘と、そして未来を担う子供たちへのご加護を感じずにはおられませんでした。
このゴジラ御守をお受けになられた皆様が、核の惨禍の無い平和を享受し、ゴジラのような力強さで困難を打ち破り、己の足の歩みで、健康に、そして我が子だけでなく、様々な次世代を育む心の一助となりましたら、何よりも嬉しい思いでございます。
なお、まだゴジラ御守の方、数に限りがある事から、暫くは土日13~17時限定で、お1人さま1体のみの授与となります。今後奉製体制が落ち着いて参りましたら、平日御朱印受付日などに合わせて、平日授与や、複数体の授与も検討して参ります。正式には当宮のX(Twitter)でご案内致しますので、そちらもご覧下さいませ。

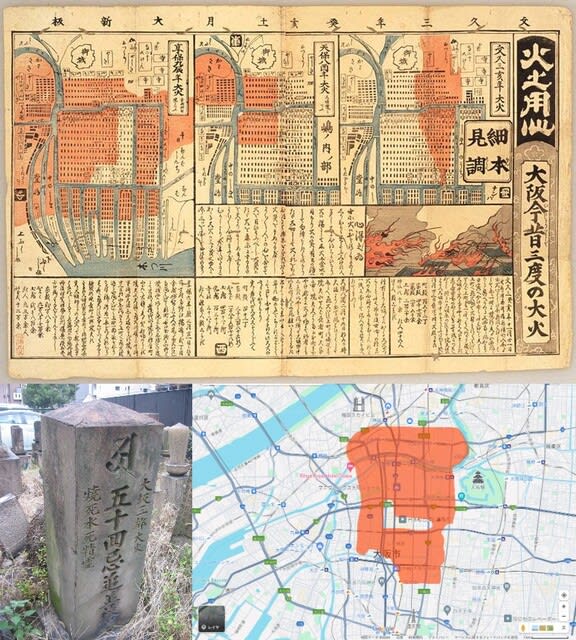















 古代大阪の地形図
古代大阪の地形図 難波の堀江推定地(現在の大川)
難波の堀江推定地(現在の大川)
 難波津の想像図
難波津の想像図 難波の堀江で仏像を見つけた本田善光
難波の堀江で仏像を見つけた本田善光 現在の八軒家浜(大川南岸)
現在の八軒家浜(大川南岸) 現在の大川(難波堀江推定地・令和5年10月撮影)
現在の大川(難波堀江推定地・令和5年10月撮影) 現在の大川にかかる噴水(令和5年10月撮影)
現在の大川にかかる噴水(令和5年10月撮影)


