昨夜テレビで「ぶっちゃけ寺」という番組をやっていた
今調べたら、これからレギュラー番組になるそうで
毎週月曜、テレ朝夜7時だそうだ
何だか一見世俗的そうな僧が出ていたけれど、
何で日本のお坊さんって、あんなに聖職者風ではないのか、と思う
簡単に書くけれど、昨日の坊さんの修行、若いお坊さんだけど
掃除が修行というのは、一石二鳥でいいなぁ、と思うけれど
何であんなに過激に掃除をしなければならないのか
何故あんなに忙しく床を拭かなければならないのだろうか?
ああいう掃除のどこが修行なのかさっぱり納得が行きません
この間書いた「永平寺」の修行は静謐でいいとか書いたけれど
それも、似た部分はあった
階段の拭き掃除の過激な事
若くなければ出来ません、っておかしくないですか?
体力を鍛える事が仏教の修行であるのなら
体育系の運動部とさして違いはないじゃないですか?
前にも書いたけれど、千日何とかという修行の阿闍梨というのもそう
山を駆けまわっての体力修行
それでは、いかに尊いお坊さんとて、体力がなければ下位なんですか?とか思う
果たして仏陀がそんなことを修行と言ったのか?
例えば音を立てずにご飯を食べること
なるべく早く食べ終えること

その為に昨日のお坊さん
ご飯を噛まずにほぼ丸呑み
あれ、一生やってられますか?って思います
一生修行と称してご飯を噛まずに食べる事は出来ないでしょうが?
おかしいですよ
納得行きません
誰か教えて下さいまし
今調べたら、これからレギュラー番組になるそうで
毎週月曜、テレ朝夜7時だそうだ
何だか一見世俗的そうな僧が出ていたけれど、
何で日本のお坊さんって、あんなに聖職者風ではないのか、と思う
簡単に書くけれど、昨日の坊さんの修行、若いお坊さんだけど
掃除が修行というのは、一石二鳥でいいなぁ、と思うけれど
何であんなに過激に掃除をしなければならないのか
何故あんなに忙しく床を拭かなければならないのだろうか?
ああいう掃除のどこが修行なのかさっぱり納得が行きません
この間書いた「永平寺」の修行は静謐でいいとか書いたけれど
それも、似た部分はあった
階段の拭き掃除の過激な事
若くなければ出来ません、っておかしくないですか?
体力を鍛える事が仏教の修行であるのなら
体育系の運動部とさして違いはないじゃないですか?
前にも書いたけれど、千日何とかという修行の阿闍梨というのもそう
山を駆けまわっての体力修行
それでは、いかに尊いお坊さんとて、体力がなければ下位なんですか?とか思う
果たして仏陀がそんなことを修行と言ったのか?
例えば音を立てずにご飯を食べること
なるべく早く食べ終えること

その為に昨日のお坊さん
ご飯を噛まずにほぼ丸呑み
あれ、一生やってられますか?って思います
一生修行と称してご飯を噛まずに食べる事は出来ないでしょうが?
おかしいですよ
納得行きません
誰か教えて下さいまし



















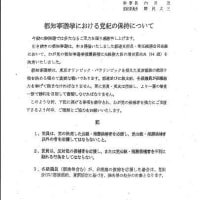








中庸で考えたら「噛まずに飲み込む」ってのは止めた方がいいレベルの苦行だと思います。
一方で「口臭のもと」を避ける五葷のように人に不愉快な思いをさせないようにしようという考え方も重要で、食事中にはあんまり酷い音を立てるべきでは無いと思います。
修行は人それぞれというのが正解です、その人にとってちょっと負荷がある程度が適切です。
柔軟体操で人の背骨を折る体育会系のノリは仏教の修行では有ってはならない事です、釈尊が否定したヒンズー式荒行です。
とはいえ本来スポーツのトレーニングは体を壊さない適切な負荷を掛けるのが正しい姿ですから「体育会系のノリ」そのものが誤った体育指導だと思います。
自分の基準を他人に押し付けるというのは仏教で絶対にやっちゃいけない事ですね。
一番知りたかったのは、釈尊がどう言っていたか、でした。
釈尊は、それを肯定していたわけではなかったとわかり、安堵しました。
>自分の基準を他人に押し付けるというのは仏教で絶対にやっちゃいけない事ですね。
ですが、今までも見てきましたように、お寺の戒律というのでしょうか、決まりでしょうか、私の好きな永平寺の修行も同様に、摩訶不思議な修行なるものをさせています。それらをこなさないと、何らかの資格でしょうか、卒業でしょうか、修行の証をいただけないのではないかというように見えます。まず、あの質素過ぎる食事だけでは、若い僧はみな脚気になると言ってました。つまり、釈尊の教えをそのまま伝承するのではなく、後世の人達が「勝手に決まりを作り」これが仏教の教えなのだと言っているのだとしたら、ゆがんでいるように思えてならないのです。仏教が釈尊の教えを離れ、仏教という別のものを作っていると解釈すればいいのか、と?キリスト教もイスラム教も同じようなものなのでしょうか、という疑問はあります。納得がいきません。
どうも、有り難うございました。お教えいただき、感謝します。