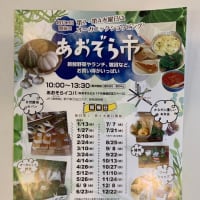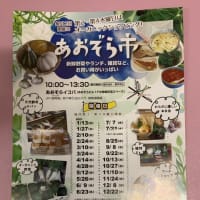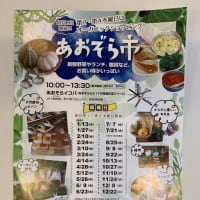22:00~2:00が睡眠のゴールデンタイムといわれ、細胞の修復、ホルモンの生成と分泌などが行われるため、この時間に睡眠を取るのが理想という説があります。中医学では、日の出から日の入りは陽の時間、日の入りから日の出までは陰の時間と… twitter.com/i/web/status/9…
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:27
太陽が上り始めると同時に、自然界の陰の気が収束し、陽気が徐々に強くなり始め、動植物は活動を始めます。太陽が沈むとともに、自然界の陰の気が強くなり始め、陽気は収束に向かいます。これが一日のサイクル。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:32
【陽】昼・動・熱・陽気=熱エネルギー+エネルギー・機能
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:35
【陰】夜・静・寒・陰血=体液+血液・物質
陽の時間である昼間は活発に活動し、陰の時間である夜は必要なものを温存し、休める時間です。実際、日中、人体を構成する気血は体表近くまで行き渡りますが、夜は体内で静かに休みます。
同じ夜でも、起きている時と同じ服装をしているのに、眠る時はお布団を掛けないとかぜをひいいたり、寝冷えしたりします。これは、体表のバリアのエネルギーも一部が体内で休むため、体表の護りが手薄になって、寒さなどの邪気が容易に体内に侵入できてしまうための現象です。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:38
エネルギー不足だと夕方以降元気になってつい×2就寝時刻が遅くなってしまいます。体液や血液の不足があると、精神を養ったり、落ち着けたりすることができないので入眠しにくくなります。どちらの場合も、不足があるにもかかわらず、それを休めたり、温存したりできないので更に不足が進みます。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:40
自然界に目を向けると。江戸時代までのように、日が暮れたら寝る準備を始め、日の出とともに起き出して活動するのが心身の健康維持にはよいと考えられます。しかし。現代社会では難易度高すぎ。エネルギー不足でも、体液&血液不足でも、その日のうちに就寝することが重要になります。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:46
エネルギー不足タイプは、元気でも夜に頑張り過ぎないこと。余力を残して就寝することで、エネルギーを温存でき、温存したエネルギーもゆっくり休ませることで、翌朝の寝覚めや午前中のパフォーマンスがよくなります(*^_-)b
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:48
体液&血液不足タイプは、入眠できない、夢が多い、眠りが浅いなどの症状が出やすいのですが、横になっていることはできます。睡眠は体と脳つまり精神の両方を交互に休めているので、入眠できなくても、横になっていれば取り敢えず体は休まるので、横になっていることが大事ですミ☆
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:49
もちろん。脳が休まらないと寝た気がしないなどの症状が現れることがあります。でも。体が休まっていれば、人体を養い、潤す体液&血液は温存できるので、その内精神も落ち着いて脳も休まるようになります。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:51
不足があるタイプでは、お腹が空いていて不足が加速し、入眠できないこともしばしば。就寝の3時間前には飲食を済ませるというのも一理ありますが、却って必要なものが足りなくて眠れなくなることもあるので、お腹が空いて眠れない場合は、消化がいいものをちょっと摂るのもいい睡眠のカギだったり。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:53
春は心身の活動のスイッチをONにするため、エネルギーも血液も体液も冬より必要になりますが、冬にそれらを充分ストックできてなかったり、季節のせいでだだ漏れしていることもあるので、不足があればその分しっかり補うことも必要です。
— 大川真有美@泰生堂薬局 (@ookawa_taiseido) 2018年2月17日 - 21:55
塩辛いものを食べ過ぎると血脈を滞らせる。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 09:08
苦いものを食べ過ぎると皮膚が乾燥する。
甘いものを食べ過ぎると骨が痛み、髪の毛が抜け落ちる。
辛いものを食べ過ぎると、筋が堅くなり、爪が乾燥する。
酸っぱいものを食べ過ぎると、肉が硬く厚くなる。
「甘いものを食べ過ぎると禿げる」
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 09:08
五行論で、酸味は肝に、苦味は心に、甘味は脾に、辛味は肺に、鹹味(塩辛い)は腎に行きます。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 09:10
そして五行論では、肝は脾を、心は肺を、脾は腎を、肺は肝を、腎は心を抑制します。
肝は筋、心は脈、脾は肉、肺は皮毛、腎は骨とと関係している… twitter.com/i/web/status/9…
羽生結弦くんのフィギュアをまた朝から録画みてます。足の怪我、疲労の回復は大切なんだなあと思いました。
— 土屋幸太郎@山形漢方 (@tutiyak) 2018年2月18日 - 08:55
さて、疲労に太谿たいけいのツボ。内くるぶしの頂点とアキレス腱の間にある大きなくぼみ。生命力をつかざどる腎じんにつながるツボ、全… twitter.com/i/web/status/9…
【ふくらはぎマッサージでモミモミ】
— 土屋幸太郎@山形漢方 (@tutiyak) 2018年2月18日 - 09:05
ふくはぎは第二の心臓です。重力に逆らって心臓まで血液を戻すには、ふくらはぎのポンプ力が大切です。
お風呂上がりや寝る前や、気がついたときにモミモミして、むくみや冷え性を解消します。
冬で溜… twitter.com/i/web/status/9…
羽生結弦選手が足の裏が悲鳴を上げたと言っているのを聞いて、フィギュアスケートは足の裏に疲労が溜まるんだなあと思いました。
— 土屋幸太郎@山形漢方 (@tutiyak) 2018年2月18日 - 09:12
足の指を曲げたときにできるくぼみが湧泉です。土踏まずあたりを気持ちのよい強さで押していきます。
疲労回復… twitter.com/i/web/status/9…
— 若石リフレ初級プロ養成スクール&サロン (@jakuseki) 2018年2月18日 - 09:39
口の状態が良くない、例えば、唇カサカサ、口角が切れる、口の周りに吹き出物がでる、口内炎、口が乾く、食欲が異常にあるなどなどは、消化を担う脾胃(ひい)の調子が悪いかもしれない、と中医学では考えます。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 14:48
口角が切れる、口の周りに吹き出物がでるのは、胃の粘膜の荒れ。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 14:50
「胃熱」という状態です。まず小食にして、さっぱり味で、脂っこいもの、辛いもの控えるようにしましょう。
涼性のハト麦、大根、そば、しめじ、大根、小松菜、イチゴ、三つ葉なども良いですよ。でも冷たいのは控えてね。
食欲が異常にある、食べても食べても満足できないのも、「胃熱」。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 14:51
口が乾燥して冷たいものを欲しがる症状も併発することが多いです。
脂っこい、甘い、味が濃いものは避けて、よく噛み、海藻類、きくらげ、かんきつ類、大根、小松菜、スイカ、キュウリ、豆腐、おくらなどを。緑茶やニガウリも。
唇かさかさは、体液バランスが崩れた状態です。熱が出てたり、前出の胃熱、糖尿病などでも体液バランスが崩れます。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 14:57
そのほか、加齢や過労でも潤い不足になります。その時は口の中も渇きます。
空気が乾燥して無いのに、唇が乾くのは身体の中… twitter.com/i/web/status/9…
「陰気(体内のエネルギーと養分の元)は水穀(飲食物)の五味から生成する。五味は臓器を養うが、摂りすぎは臓器を傷つける。」と古典にあります。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:36
五味とは、酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味(かんみ:しおからい)の五つの味を指します。
で… twitter.com/i/web/status/9…
酸味
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:37
収斂といって、汗、尿、便を必要以上に排出させない作用を持ち、多汗、寝汗、夜間尿、頻尿、下痢などを改善します。
また、肝に働き、イライラ、怒りっぽい、憂鬱、不安、悪夢を改善します。
摂りすぎると脾(消化系)を傷つけ、筋肉を委縮させます。
苦味
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:39
鎮静、利尿、消炎、解毒、解熱などの作用があり、血のめぐりをよくし、循環器の働きを良くします。
高血圧や赤ら顔、皮膚の炎症、怒りっぽい、多夢、不眠などを改善します。
摂りすぎると、肺を傷つけ、カゼをひきやすくなったり、肌の乾燥や呼吸器トラブル、便秘などにつながります。
甘味
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:40
甘味には、滋養強壮の力があり、脾(消化系)の働きを良くします。
痛みを和らげる作用もありますが、摂りすぎると逆に脾を弱め、胸やけを起こし、顔色が黒くなり、腎を傷つけ骨を弱め、髪を痛めます。
辛味
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:42
発汗解熱の作用があり、気血のめぐりを良くします。
呼吸器系にも働き、水分代謝も改善します。しかし摂り過ぎは、熱を生じ、精気を消耗し、肝を傷つけ、筋を弱めて爪や目を痛めます。
鹹味
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:42
しおからい味は、泌尿器、生殖器肝、ホルモンの働きを良くして、精力を高めます。
新陳代謝を良くしてガングリオンやいぼなどの塊を縮小させる力がありますが、摂り過ぎると血のめぐりを悪くし、腰の骨が痛むようになります。
これら酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味の五味をバランスよく食べることで、「骨格が堅固し、筋肉は柔軟になり、気血が良くめぐり、皮膚のきめが細かくなる」と古典には書かれています。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:43
そのためには、青(緑)、赤、黄、白、黒の食材をバランスよく食べるのが大事です。
更に詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。
— 櫻井大典@漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2018年2月18日 - 18:44
3部作でながいですよ。誤字も多いかもw
薬膳Part1 食事で体を元気にする基礎知識 - ミドリ薬品 店長ブログ - ミドリ薬品 | 北海道北見市 | 漢方専門 | 皮膚病 不妊症など… twitter.com/i/web/status/9…