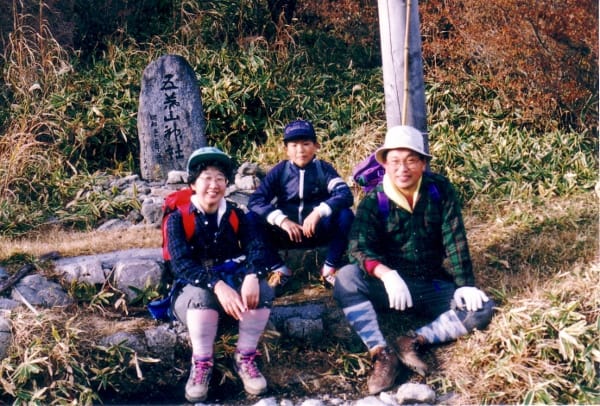わが町をふくむ東北北部も「梅雨明け」となった。昨日は、強い日差しが照りつけ田んぼでの作業はまたたくまに汗みどろの状態となり、したたる汗でパンツまでびしょぬれ状態。今朝は朝の4時ころからヒグラシが鳴き、「夏が来たよ」といっているようだ。それでも今朝は、雲が出てお日様は顔を出していない。
夏の訪れを告げるように、山林の中などでオオウバユリの花が咲きはじめた。オオウバユリは北海道と本州の中部以北にユリ科の植物で、花が咲いた時に下部の葉(歯)が欠けているのを「姥」に例えたともいわれる。それにしても「オオウバ」は少し気の毒な気がする。色合いも地味で、ユリの仲間では目立たない存在である。
写真は、わが家の庭に咲いたものである。
夏の訪れを告げるように、山林の中などでオオウバユリの花が咲きはじめた。オオウバユリは北海道と本州の中部以北にユリ科の植物で、花が咲いた時に下部の葉(歯)が欠けているのを「姥」に例えたともいわれる。それにしても「オオウバ」は少し気の毒な気がする。色合いも地味で、ユリの仲間では目立たない存在である。
写真は、わが家の庭に咲いたものである。