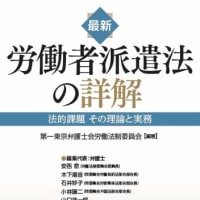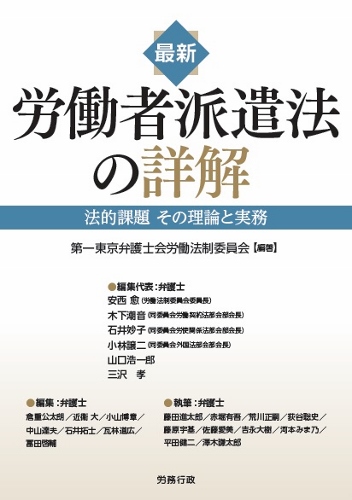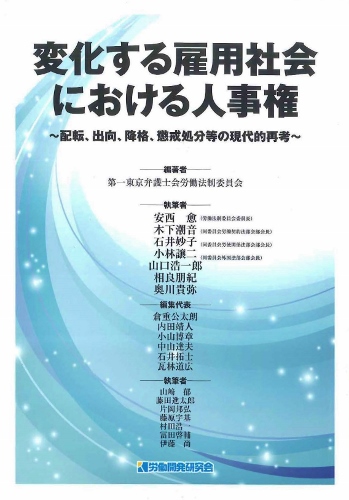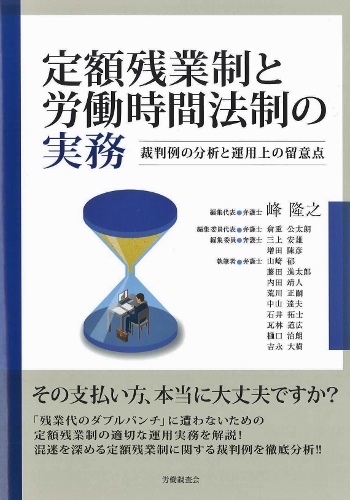Q9 就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。
就業時間外に社外で社員が刑事事件を起こしたとしても,それだけでは直ちに懲戒処分に処することができるわけではありません。
まずは,本人の言い分をよく聞き,記録に残しておくべきでしょう。
本人が犯行を否認しており,犯罪が行われたかどうかが明らかではない場合は,犯行があったことを前提に懲戒処分をすることはリスクが高いので,懲戒処分は慎重に行う必要があります。
逮捕勾留されたことにより,社員本人と連絡が取れなくなり,無断欠勤が続くこともあり得ますが,まずは家族等を通じて,連絡を取る努力をすべきです。
家族等から,欠勤の連絡等が入ることがありますが,懲戒解雇等の処分を恐れて,犯罪行為により逮捕勾留されていることまでは報告を受けられない場合もあります。
年休取得の申請があった場合は,年休扱いにするのが原則です。
年休取得を認めずに欠勤扱いとした場合,欠勤を理由とした解雇等の処分が無効となるリスクが生じることになります。
痴漢,傷害事件等,被害者のある刑事事件における弁護人の起訴前弁護の主な活動内容は,早期に被害者と示談して不起訴処分を勝ち取ることです。
不起訴処分が決まれば,逮捕勾留は解かれ,出社できる状態となります。
刑事事件を犯したことを会社に知られずに出社できた場合は,弁護人としていい仕事をしたことになります。
起訴休職制度を設けると,有罪判決が確定するまで解雇することができないと解釈されるおそれがありますので,そのような事態を避けるためには起訴休職制度は設けず,個別に対応するという選択肢もあり得ます。
また,社員が起訴された事実のみで,形式的に起訴休職の規定の適用が認められるとは限らず,休職命令が無効と判断されることもあります。
休職命令を出す際は,その必要性,相当性について検討してからにする必要があります。
懲戒解雇は紛争になりやすく,懲戒解雇が無効と判断されるリスクもそれなりにありますので,慎重に検討する必要があります。
会社の社会的評価を若干低下させたという程度では足りません。
「就業時間外に社外で行われた刑事事件が会社の社会的評価に重大な悪影響を与えたこと」を理由とする懲戒解雇の可否の判断にあたっては,「当該行為の性質,情状のほか,会社の事業の種類・態様・規模,会社の経済界に占める地位,経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断して,右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」に該当するかどうかを検討することになります(日本鋼管事件最高裁第二小法廷昭和49年3月15日判決)。
例えば,タクシーやバスの運転業務に従事している社員が飲酒運転した場合は,懲戒解雇が有効とされやすい傾向にあります。
ただし,「酒気帯び状態であれば,仮にそのまま運転していれば道路交通法違反で検挙されることになりかねない程度の非違行為があったものとして解雇に値することが明らかだが,そこまでの断定ができない者についても当然に解雇とすることが社会一般の常識であると評価することには躊躇を感じる」として,バス運転手の飲酒運転を理由とした諭旨解雇を無効とした裁判例(京阪バス事件京都地裁平成22年12月15日判決)もあり,事案ごとの判断が必要となります。
その他,電鉄会社社員等,痴漢を防止すべき立場にある者が痴漢したような場合は,比較的懲戒解雇が認められやすいといえるでしょう。
懲戒解雇が無効とされるリスクがある事案については,より軽い懲戒処分にとどめた方が無難かもしれません。
結果として,社員が自主退職することもあります。
最初に刑事事件を起こした際に,懲戒解雇を回避してより軽い懲戒処分をする場合は,書面で,次に同種の刑事事件を起こしたら懲戒解雇する旨の警告をするか,次に同種の刑事事件を起こしたら懲戒解雇されても異存ない旨記載された始末書を取っておくべきでしょう。
これで万全というわけではありませんが,同種の犯罪を犯した場合の懲戒解雇が有効となりやすくなります。
懲戒解雇事由に該当する場合を退職金の不支給・減額・返還事由として規定しておけば,懲戒解雇事由がある場合で,当該個別事案において,退職金不支給・減額の合理性がある場合には,退職金を不支給または減額したり,支給した退職金の全部または一部の返還を請求したりすることができます。
退職金の不支給・減額・返還の合理性の有無は,退職金の性格の中に功労報奨金的要素の占める度合いがどの程度か等,様々な要素を考慮して判断されることになりますが,賃金の後払い的要素の強い退職金についてその退職金全額を不支給とするには,横領や背任等のように,それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要となります。
そこまで重大な不信行為がない場合は,懲戒解雇が有効だったとしても,退職金全額を不支給とすることができるとは限らず,例えば,本来の退職金の支給額の30%とか50%とかいった金額の支払が命じられることがあります。
弁護士 藤田 進太郎
就業時間外に社外で社員が刑事事件を起こしたとしても,それだけでは直ちに懲戒処分に処することができるわけではありません。
まずは,本人の言い分をよく聞き,記録に残しておくべきでしょう。
本人が犯行を否認しており,犯罪が行われたかどうかが明らかではない場合は,犯行があったことを前提に懲戒処分をすることはリスクが高いので,懲戒処分は慎重に行う必要があります。
逮捕勾留されたことにより,社員本人と連絡が取れなくなり,無断欠勤が続くこともあり得ますが,まずは家族等を通じて,連絡を取る努力をすべきです。
家族等から,欠勤の連絡等が入ることがありますが,懲戒解雇等の処分を恐れて,犯罪行為により逮捕勾留されていることまでは報告を受けられない場合もあります。
年休取得の申請があった場合は,年休扱いにするのが原則です。
年休取得を認めずに欠勤扱いとした場合,欠勤を理由とした解雇等の処分が無効となるリスクが生じることになります。
痴漢,傷害事件等,被害者のある刑事事件における弁護人の起訴前弁護の主な活動内容は,早期に被害者と示談して不起訴処分を勝ち取ることです。
不起訴処分が決まれば,逮捕勾留は解かれ,出社できる状態となります。
刑事事件を犯したことを会社に知られずに出社できた場合は,弁護人としていい仕事をしたことになります。
起訴休職制度を設けると,有罪判決が確定するまで解雇することができないと解釈されるおそれがありますので,そのような事態を避けるためには起訴休職制度は設けず,個別に対応するという選択肢もあり得ます。
また,社員が起訴された事実のみで,形式的に起訴休職の規定の適用が認められるとは限らず,休職命令が無効と判断されることもあります。
休職命令を出す際は,その必要性,相当性について検討してからにする必要があります。
懲戒解雇は紛争になりやすく,懲戒解雇が無効と判断されるリスクもそれなりにありますので,慎重に検討する必要があります。
会社の社会的評価を若干低下させたという程度では足りません。
「就業時間外に社外で行われた刑事事件が会社の社会的評価に重大な悪影響を与えたこと」を理由とする懲戒解雇の可否の判断にあたっては,「当該行為の性質,情状のほか,会社の事業の種類・態様・規模,会社の経済界に占める地位,経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断して,右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」に該当するかどうかを検討することになります(日本鋼管事件最高裁第二小法廷昭和49年3月15日判決)。
例えば,タクシーやバスの運転業務に従事している社員が飲酒運転した場合は,懲戒解雇が有効とされやすい傾向にあります。
ただし,「酒気帯び状態であれば,仮にそのまま運転していれば道路交通法違反で検挙されることになりかねない程度の非違行為があったものとして解雇に値することが明らかだが,そこまでの断定ができない者についても当然に解雇とすることが社会一般の常識であると評価することには躊躇を感じる」として,バス運転手の飲酒運転を理由とした諭旨解雇を無効とした裁判例(京阪バス事件京都地裁平成22年12月15日判決)もあり,事案ごとの判断が必要となります。
その他,電鉄会社社員等,痴漢を防止すべき立場にある者が痴漢したような場合は,比較的懲戒解雇が認められやすいといえるでしょう。
懲戒解雇が無効とされるリスクがある事案については,より軽い懲戒処分にとどめた方が無難かもしれません。
結果として,社員が自主退職することもあります。
最初に刑事事件を起こした際に,懲戒解雇を回避してより軽い懲戒処分をする場合は,書面で,次に同種の刑事事件を起こしたら懲戒解雇する旨の警告をするか,次に同種の刑事事件を起こしたら懲戒解雇されても異存ない旨記載された始末書を取っておくべきでしょう。
これで万全というわけではありませんが,同種の犯罪を犯した場合の懲戒解雇が有効となりやすくなります。
懲戒解雇事由に該当する場合を退職金の不支給・減額・返還事由として規定しておけば,懲戒解雇事由がある場合で,当該個別事案において,退職金不支給・減額の合理性がある場合には,退職金を不支給または減額したり,支給した退職金の全部または一部の返還を請求したりすることができます。
退職金の不支給・減額・返還の合理性の有無は,退職金の性格の中に功労報奨金的要素の占める度合いがどの程度か等,様々な要素を考慮して判断されることになりますが,賃金の後払い的要素の強い退職金についてその退職金全額を不支給とするには,横領や背任等のように,それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要となります。
そこまで重大な不信行為がない場合は,懲戒解雇が有効だったとしても,退職金全額を不支給とすることができるとは限らず,例えば,本来の退職金の支給額の30%とか50%とかいった金額の支払が命じられることがあります。
弁護士 藤田 進太郎