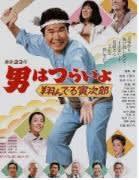「オペラ座の怪人」 2004年 アメリカ / イギリス

監督 ジョエル・シューマカー
出演 ジェラルド・バトラー
エミー・ロッサム
パトリック・ウィルソン
ミランダ・リチャードソン
ミニー・ドライヴァー
シアラン・ハインズ
ストーリー
1919年のパリ。
今や廃墟と化したオペラ座で、かつて栄華を極めた品々がオークションにかけられていた。
そこには、老紳士ラウル・シャニュイ子爵(パトリック・ウィルソン)と年老いたバレエ教師、マダム・ジリー(ミランダ・リチャードソン)の姿があった。
やがて、謎の惨劇に関わったとされるシャンデリアが紹介され、ベールが取り払われると、ふたりは悲劇の幕開けとなった1870年代当時へと一気に引き戻される。
1870年代のパリ。
オペラ座では奇怪な事件が続いていた。
オペラ「ハンニバル」のリハーサル中、プリマドンナのカルロッタ(ミニー・ドライヴァー)の頭上に背景幕が落下し、腹を立てたカルロッタは役を降板。
代役を務めたのは、バレエダンサーのクリスティーヌ(エミー・ロッサム)だった。
喝采を浴びた彼女は、幼馴染みのラウルと再会。
だが、その喜びも束の間、仮面をかぶった謎の怪人・ファントム(ジェラルド・バトラー)にオペラ座の地下深くへと連れ去られてしまうが、そこには怪人の憎しみと哀しみがあった。
クリスティーヌは、ファントムを亡き父親が授けてくれた‘音楽の天使’だと信じてきたが、地下の隠れ家で仮面をはぎ、その正体を知ってしまうと同時に彼の孤独な心と自分に対する憧れにも気づくのだった。
その頃、オペラ座の支配人たちは、オペラ「イル・ムート」の主役にクリスティーヌを据えよというファントムからの脅迫状を受け取っていたが、その要求を無視してカルロッタを主役に立てた舞台は大混乱。
ついに殺人事件が起きてしまう・・・。
寸評
冒頭はモノトーンで描かれるオペラ座でのオークション場面だ。
男女の老人二人がオークションに参加しているが、過去に何かしらの因縁が有り顔見知りのようである。
そのようなちょっとした謎を秘めてシャンデリアの覆いが取り除かれると、物語は1870年当時のシーンに移行するのだが、この場面はCGを駆使した映画らしいダイナミックな演出で、廃墟のオペラ座が一気にゴージャスな全盛期に戻る様子は圧巻だ。
モノトーンの画面に描かれるオペラ座の劇場内に積もった埃が吹き飛ばされていくと、カラーに変わっていき全盛時のオペラ座が出現する。
ミュージカル映画が好きな僕ではあるが、このシーンで一気に引き込まれてしまった。
ストーリーなど知らなくても映画の世界に誘ってくれる秀逸なシーンで、まさに映画を感じさせる。
モノトーンの現在から、カラーの過去へと切り替わるシーンでは同じような手法が使われているが、それもなかなかスムーズで映画らしい演出だ。
しかし、視覚的効果を狙ったものなのか、怪人の仮面というかメイクは綺麗すぎたように思う。
そのために、怪人がヒロインに感じる純愛の切なさ、かなわぬ恋の哀れといったテーマが弱くなってしまっていたようだ。
ビジュアル的にもそうだが、怪人がどのようにしてクリスティーヌに恋するようになったのかの説明がないことが第一の原因だった。
劇場内を飛び回るカメラワークや、ゴージャスな衣装、凝りに凝ったセットなど、見た目の派手さはかなりのものがあっただけに残念だ。
アンドリュー・ロイド=ウェバーの主題曲は耳にしたことがあるが、その他の曲は僕には馴染み深いものではない。それでも曲がうたわれるシーンでの、その歌声はを聞かせるに十分なもので存分に楽しめる。
怪人ファントム役のジェラード・バトラーの歌唱がもう少し迫ってくるようなパワーのあるものだったらもっと良かったのに・・・。
クリスティーヌは催眠術にかかっているかのように怪人のもとへ行ってしまう。
それは音楽による呪縛で、彼女のプリマドンナとしての技量は怪人によってもたらされたものであることを自覚していたからだと思うし、プリマドンナの地位を失いたくない気持ちもあったのかもしれない。
ラウルへの愛とプリマドンナの地位の間で揺れ動くクリスティーヌが描かれたならもっと奥深かっただろうなと思ったのだが、テーマはそんなところにはない作品のようだし、それは僕の無い物ねだりであった。
怪人は結局ふたりの愛を見守り続けたのだろうし、今もクリスティーヌへの愛を抱き続けているのだろう。
クリスティーヌの墓前に添えられた黒いリボンのバラの花がそれを物語っていた。
ミュージカルなので話の大筋は単純だ。
言ってしまえばクリスティーヌをめぐって繰り広げられる、音楽の師である怪人と幼馴染で憧れの人であった男との三角関係を描いただけのものである。
それでもやはり、怪人が捧げた愛の切なさはもう少し感じたかったなあ・・・。

監督 ジョエル・シューマカー
出演 ジェラルド・バトラー
エミー・ロッサム
パトリック・ウィルソン
ミランダ・リチャードソン
ミニー・ドライヴァー
シアラン・ハインズ
ストーリー
1919年のパリ。
今や廃墟と化したオペラ座で、かつて栄華を極めた品々がオークションにかけられていた。
そこには、老紳士ラウル・シャニュイ子爵(パトリック・ウィルソン)と年老いたバレエ教師、マダム・ジリー(ミランダ・リチャードソン)の姿があった。
やがて、謎の惨劇に関わったとされるシャンデリアが紹介され、ベールが取り払われると、ふたりは悲劇の幕開けとなった1870年代当時へと一気に引き戻される。
1870年代のパリ。
オペラ座では奇怪な事件が続いていた。
オペラ「ハンニバル」のリハーサル中、プリマドンナのカルロッタ(ミニー・ドライヴァー)の頭上に背景幕が落下し、腹を立てたカルロッタは役を降板。
代役を務めたのは、バレエダンサーのクリスティーヌ(エミー・ロッサム)だった。
喝采を浴びた彼女は、幼馴染みのラウルと再会。
だが、その喜びも束の間、仮面をかぶった謎の怪人・ファントム(ジェラルド・バトラー)にオペラ座の地下深くへと連れ去られてしまうが、そこには怪人の憎しみと哀しみがあった。
クリスティーヌは、ファントムを亡き父親が授けてくれた‘音楽の天使’だと信じてきたが、地下の隠れ家で仮面をはぎ、その正体を知ってしまうと同時に彼の孤独な心と自分に対する憧れにも気づくのだった。
その頃、オペラ座の支配人たちは、オペラ「イル・ムート」の主役にクリスティーヌを据えよというファントムからの脅迫状を受け取っていたが、その要求を無視してカルロッタを主役に立てた舞台は大混乱。
ついに殺人事件が起きてしまう・・・。
寸評
冒頭はモノトーンで描かれるオペラ座でのオークション場面だ。
男女の老人二人がオークションに参加しているが、過去に何かしらの因縁が有り顔見知りのようである。
そのようなちょっとした謎を秘めてシャンデリアの覆いが取り除かれると、物語は1870年当時のシーンに移行するのだが、この場面はCGを駆使した映画らしいダイナミックな演出で、廃墟のオペラ座が一気にゴージャスな全盛期に戻る様子は圧巻だ。
モノトーンの画面に描かれるオペラ座の劇場内に積もった埃が吹き飛ばされていくと、カラーに変わっていき全盛時のオペラ座が出現する。
ミュージカル映画が好きな僕ではあるが、このシーンで一気に引き込まれてしまった。
ストーリーなど知らなくても映画の世界に誘ってくれる秀逸なシーンで、まさに映画を感じさせる。
モノトーンの現在から、カラーの過去へと切り替わるシーンでは同じような手法が使われているが、それもなかなかスムーズで映画らしい演出だ。
しかし、視覚的効果を狙ったものなのか、怪人の仮面というかメイクは綺麗すぎたように思う。
そのために、怪人がヒロインに感じる純愛の切なさ、かなわぬ恋の哀れといったテーマが弱くなってしまっていたようだ。
ビジュアル的にもそうだが、怪人がどのようにしてクリスティーヌに恋するようになったのかの説明がないことが第一の原因だった。
劇場内を飛び回るカメラワークや、ゴージャスな衣装、凝りに凝ったセットなど、見た目の派手さはかなりのものがあっただけに残念だ。
アンドリュー・ロイド=ウェバーの主題曲は耳にしたことがあるが、その他の曲は僕には馴染み深いものではない。それでも曲がうたわれるシーンでの、その歌声はを聞かせるに十分なもので存分に楽しめる。
怪人ファントム役のジェラード・バトラーの歌唱がもう少し迫ってくるようなパワーのあるものだったらもっと良かったのに・・・。
クリスティーヌは催眠術にかかっているかのように怪人のもとへ行ってしまう。
それは音楽による呪縛で、彼女のプリマドンナとしての技量は怪人によってもたらされたものであることを自覚していたからだと思うし、プリマドンナの地位を失いたくない気持ちもあったのかもしれない。
ラウルへの愛とプリマドンナの地位の間で揺れ動くクリスティーヌが描かれたならもっと奥深かっただろうなと思ったのだが、テーマはそんなところにはない作品のようだし、それは僕の無い物ねだりであった。
怪人は結局ふたりの愛を見守り続けたのだろうし、今もクリスティーヌへの愛を抱き続けているのだろう。
クリスティーヌの墓前に添えられた黒いリボンのバラの花がそれを物語っていた。
ミュージカルなので話の大筋は単純だ。
言ってしまえばクリスティーヌをめぐって繰り広げられる、音楽の師である怪人と幼馴染で憧れの人であった男との三角関係を描いただけのものである。
それでもやはり、怪人が捧げた愛の切なさはもう少し感じたかったなあ・・・。