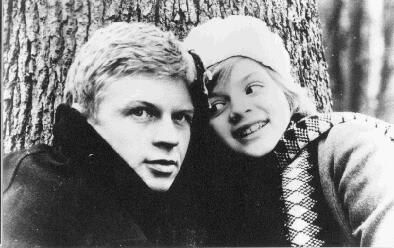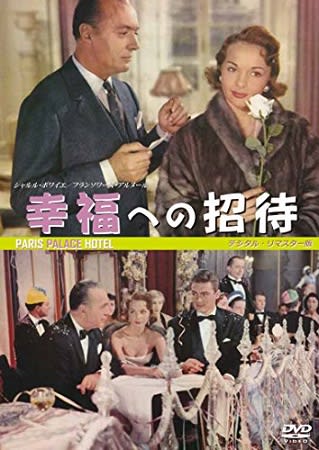今日はアカデミー賞について、『嫌われごと』を述べてみようと思います。
私も映画と真剣に対峙するまではハリウッド発のアカデミー賞に関心を持っていたものです。
しかし、アカデミー賞自体がハリウッドの一大宣伝イベントにすぎないと悟ってからは一切興味がありません。
内外のマスコミは映画界最高の栄誉としてもてはやしますが、ハリウッド映画を全世界にばらまくための商業手段で、
マスコミやファンが騒げば騒ぐほどハリウッドが儲かる仕組みとなり、これは戦略的な営業イベントそのものです。
さらにアカデミー賞は、ハリウッド内の権威争いの場でもあります。
受賞することによって、制作者をはじめ、監督・役者から衣裳デザイン・音楽に至るまでその映画に携わった
あらゆる人たちの地位と名声が後々の映画界において保証されます。
個人の演技に対する賞を受けた俳優は一躍スターダムに、その後の出演には莫大な出演料を約束されます。
映画製作会社としては、賞の肩書で全世界に売り込みが容易となりその映画の興業収入が確保されます。
そのために、関係者は自らの作品を受賞させるための醜い暗躍を繰り返しています。
( 一例を挙げれば駄作としか思えない『風と共に去りぬ』におけるデヴィッド・O・セルズニックの言動 )
裏側のそんな泥臭い銭闘のために 見る側が踊らされては たまったものじゃありません。
さらに、主演男優賞など(主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞) もナンセンスの極みでしょう。
私の友人である Amore-mioさんの父上が仰っていた言葉、
「役者の演技が上手いというけれど、そうではない。その演技をさせた監督が上手いのだ」
まったく同感です。
将棋でたとえるならば、棋士は監督で俳優は将棋の駒にすぎません。
まともな映画作品は監督の‘一貫した思い’を映像化するものです。
その作品は監督の"生産物"であって 主演俳優の"物"ではありません。
一介の俳優が作品の制作進行にあたって、自分の考えで監督の指示に従わずに勝手に演技したり、
監督に注文を出すということは、作品が監督のものであることを否定することであり許されるものではありません。
俳優が思い上るのはハリウッドの悪産物であるスター主義の最大の弊害でしょう。
俳優はあくまでも監督の意思に従って動かされる意思を持たない将棋の駒なのです。
逆に言えば、監督の意思に従って監督の思い通りの演技をこなすのが俳優という職業です。
娯楽目的の作品やテレビドラマ級の作品ならともかく、俳優は監督の指図に絶対であるべきでしょう。
役者の演技が上手かったと感じたならば、それは演出の"腕"です。
棋士を称えるべきであって駒を称えることはありえないことです。
したがって、主演男優賞など俳優に与えられる賞には何の価値感も持てません。
そういう理由なのか、賞を辞退した勇気ある俳優もいたようですが、これには大きな拍手を送ります。
アカデミー賞はナンセンス。
不快に思われる方もおられるでしょうが、これが私の持論です。