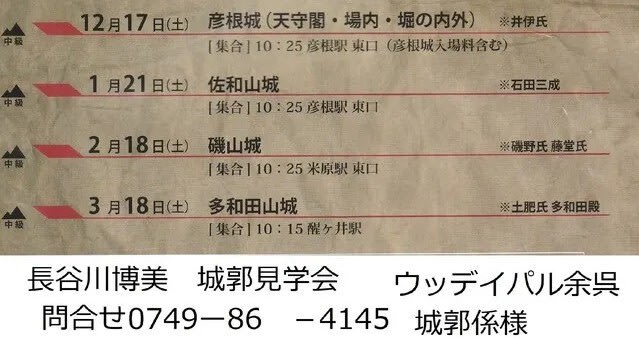
加賀百万石の金沢城のビイスタ工法
◆対談者
今日本全国では城郭ビイスタ
論で話題騒然となっています。
加賀前田侯は織田信長家臣と
して安土城に伝前田利家邸が
残っていますが前田家とは?
この頃よりビイスタ工法を
安土城で自分の屋敷設計に
扇型ビイスタ工法を使って
いたのですか?御教示下を!
▼主君 織田信長 安土城ビイスタ工法
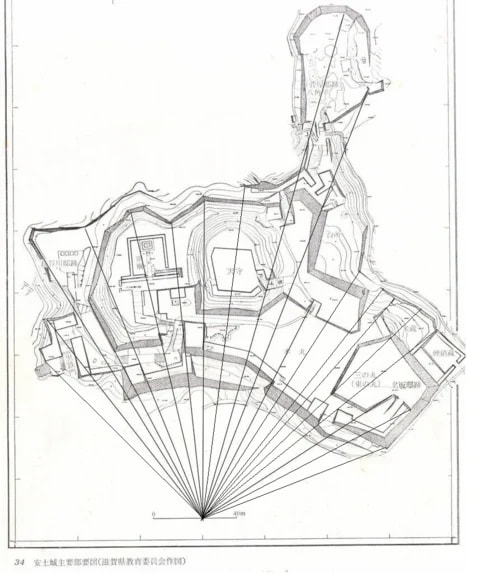
▼主君 信長安土城天主中央ビイスタ工法

◆長谷川
伝前田利家邸の殿舎配置は
明らかに主君信長の安土城
と類似した扇型ビイスタを
駆使した配列を前田家では
施工したと推定されますが
▼家臣 伝前田利家邸 安土城内
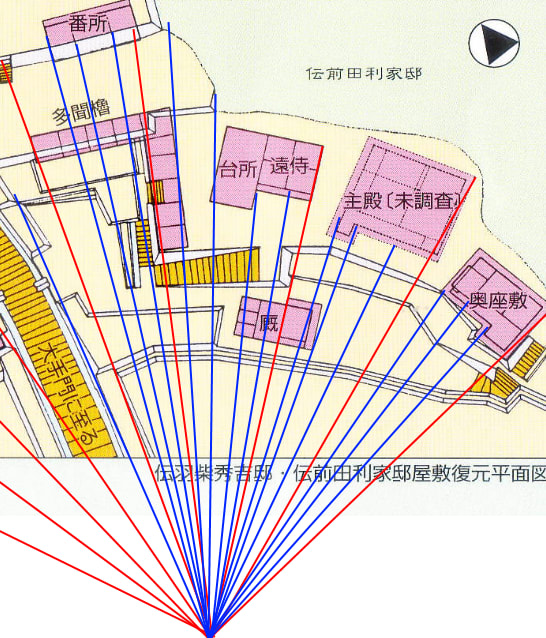
◆質問者
信長は天正10年1582年本能寺
の変で亡くなります。この時
前田利家と前田利長は何処の
城主だったのでしょうか?
◆長谷川
父 利家は能登小丸山城主
子 利長は越前府中の城主
柴田勝家与力的大名でした
◆質問者
天正11年1583年賤ケ岳の
戦いの陣城玄番尾城には
ビイスタ工法が施されま
したか?
◆長谷川
織田信長の北陸方面師団長
だった重臣柴田勝家は織豊
系大名です壮大なビイスタ
工法を駆使して玄番尾城を
縄張して築城しております。
▼玄番尾城 天守台 写真

▼玄番尾城ビイスタ工法 長谷川博美図

◆質問者
柴田勝家の甥 佐久間盛
天正11年築城の近江余呉
の行市山陣城 ビイスタ
工法ありますか?
◆長谷川
存在致します。

◆質問者
織豊系大名越中の佐々成正の
富山城には柴田勝家玄番尾城
と類似した馬出のある城です
か?またビイスタ工法は?
◆長谷川
後に前田家の持ち城ともなった
越中富山城は典型的ビイスタで
重複型ビイス工法の様式です。
▼富山城 重複型ビイスタ工法

◆質問者
同じく前田利家、前田利長親子
の陣城、別所山城はビイスタの
工法を使っているのですか?
◆長谷川
別所山陣城は扇型ビイスタ
工法を駆使し築城してます。


◆質問者
都市計画の技術者として
キリスタン大名として世
に名の通った高山右近の
賤ケ岳合戦時の大岩山陣
は城はビイスタ工法使用
しておりますか?
◆長谷川
緻密な幾何学的ビイスタ
工法を駆使築城してます。
▼滋賀県長浜市余呉町岩崎山陣城図


◆観光客
別所山陣城と岩崎山陣城の
御城印何処で販売されてる?
◆長谷川
余呉観光館
ウッデイパル余呉
木之本駅おかん 3カ所
◆質問者
前田利長の富山高岡城って
ビイスタ工法使ってます?
◆長谷川
高岡城も岩崎山城も相対型
ビイスタ工法駆使してます。
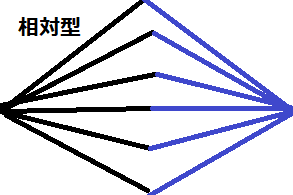
◆枝吉城ウィツキペデイアより引用
とされている(『采邑私記』)。しかし、高山右近が直接
船上城へ入城したと記されている研究[3]や、右近に関して
触れていない研究もある[2]。これらの事から「枝吉城に入
ったという確実な史料もなく、枝吉城に右近がいたかどうか
は分からない」[4]としており右近が城主となったかどうか
については不明と記している。▼枝吉城相対型ビイスタ

▼高岡城ビイスタ工法「相対型」

▼高岡城天守は重複型ビイスタです。

▼長谷川博美 ビイスタ工法一覧表
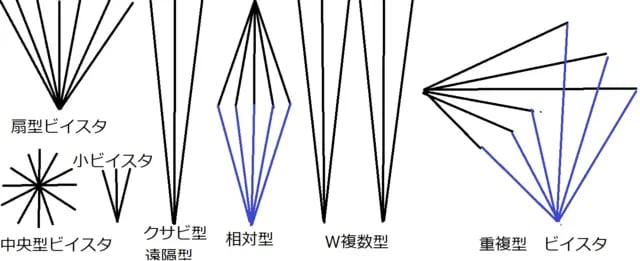
◆質問者
さて日本最大の外様大名
加賀百万石の金沢前田家
の居城の『金沢城』には
城郭ビイスタあります?
◆反論者
絶対に100%存在しない!
長谷川城郭ビイスタ論な
ど絶対に信用しません!
城郭ビイスタ論動画は
絶対に見ないで下さい!
◆対談者
長谷川先生!是非とも
金沢城更なる発展の為
日本の城郭研究の大道
の為に是非御教示を!
◆長谷川
先ず金沢城とは真宗の
「尾山御坊」が存在
しました真宗北陸布教
の為の重要拠点尾山が
金沢城の原形と言う事
になり文献『信長公記』
で大阪石山本願寺城の
事を「 抑も大坂は凡日本
一の境地也。(中略)
加賀国より城作を召寄、
方八町に相構」と
『信長公記』巻十三
天正八年にも記載されて
加賀国城作の文言が気に
なるところであります。
天文元年(1532年)期
の蓮如上人の京都山科
本願寺の縄張は城郭史
から見ても異常な進歩
性が見られ我々の常識
を超えるビイスタ工法
を用いた秀逸なる寺院
城郭であった事が確実
▼山科本願寺クサビ型ビイスタ

▼山科本願寺中央型ビイスタ
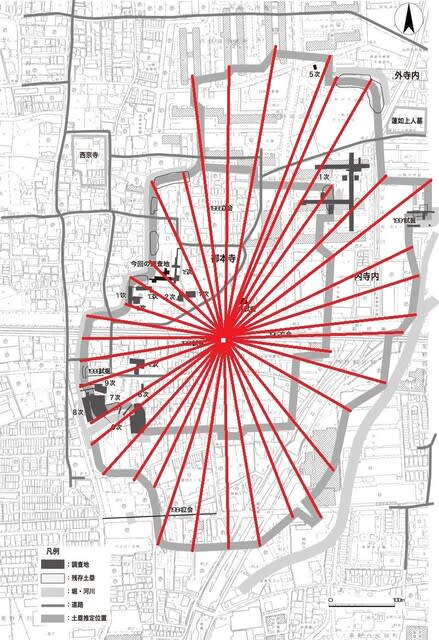
以下ウイッキペデイアより引用
文明10年(1478年)から造営され、約6年間で建設
されたと言われている。山科盆地の中央より西側に
あり、四ノ宮川と山科川(旧音羽川)の合流地点で、
当時は山城宇治郡に属する。この地域は東海道から
宇治街道へ抜ける分岐点、交通の要所であった。
天文元年(1532年)の『経厚法印日記』によると
「山科本願寺ノ城ヲワルトテ」と記載が見受けら
れることから、当時より城として呼称されていた。
寺院が城に変化できたのは加賀より城造り人夫を
呼び寄せて本格的な城郭に仕上がったのでないか
と思われている。
◆長谷川
金沢城は尾山御坊佐久間盛政の
居城そして前田候による累代の
普請工事によって築城された城
ですがビイスタ工法を検討しま
す。先ず大手方面からビイスタ
真に息を飲む見事なビイスタ!

金沢城二の丸居館部を中心の
次これも見事な中央ビイスタ

石川門方面から二の丸へ
向けたビイスタ工法あり

▼金沢城主要部図

整合性のある金沢城の
重複型ビイスタの存在
▼金沢城 重複型ビイスタ工法

▼織豊系城郭 富山城の重複ビイスタ

▼三の丸中心のビイスタ工法
これは石川門口と大手門位置
を決定する最重要測量起点。

◆対談者
長谷川先生!スゴ過ぎです!
金沢城加賀侯隠然たる力量!
▼天正大坂城「石山本願寺跡」豊臣秀吉

▼大津城ビイスタ 織豊系城郭
















