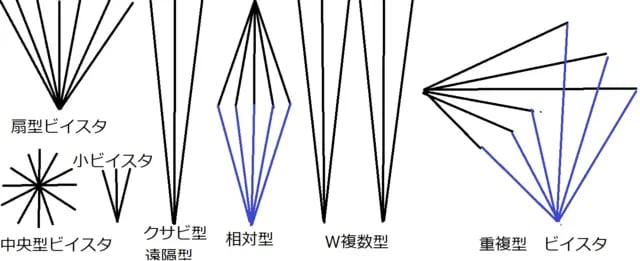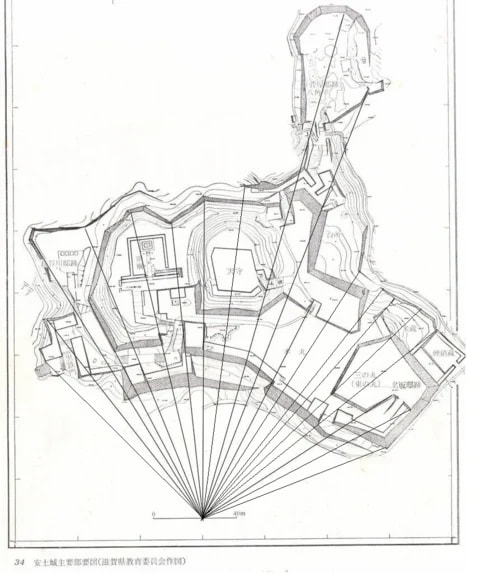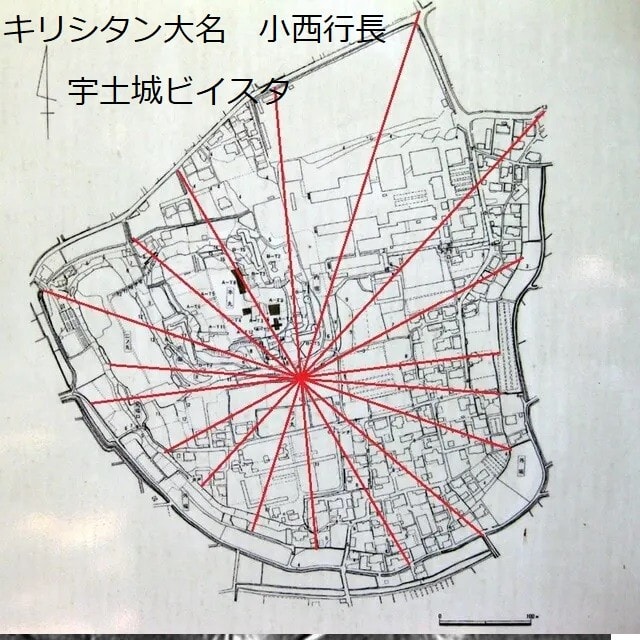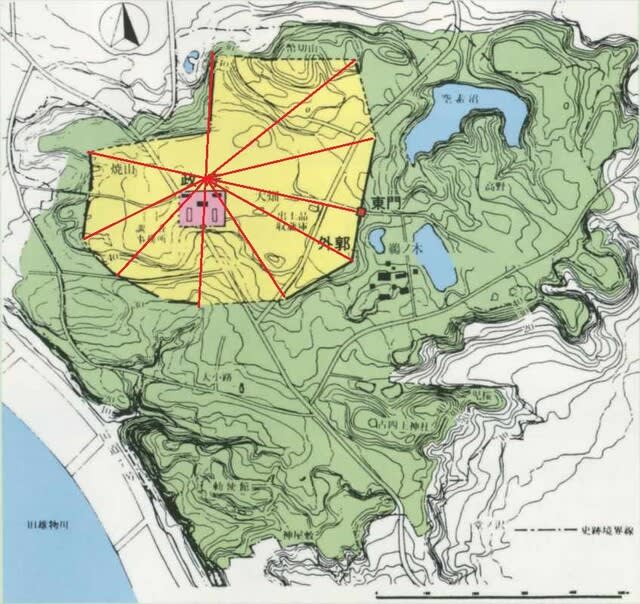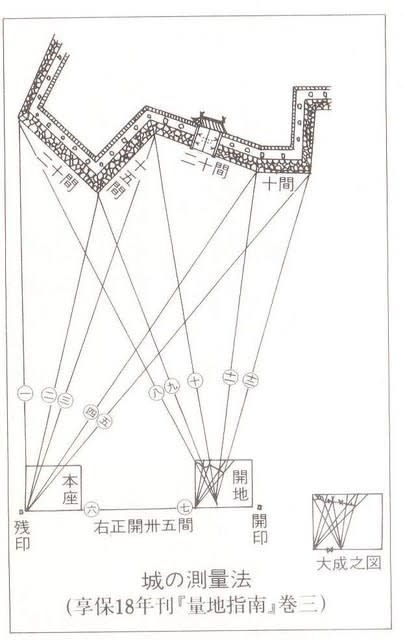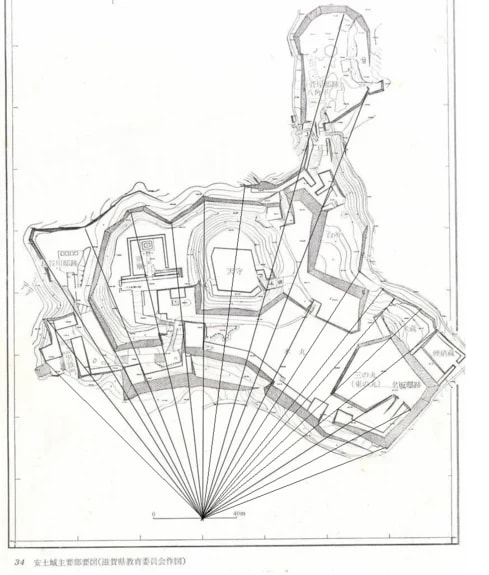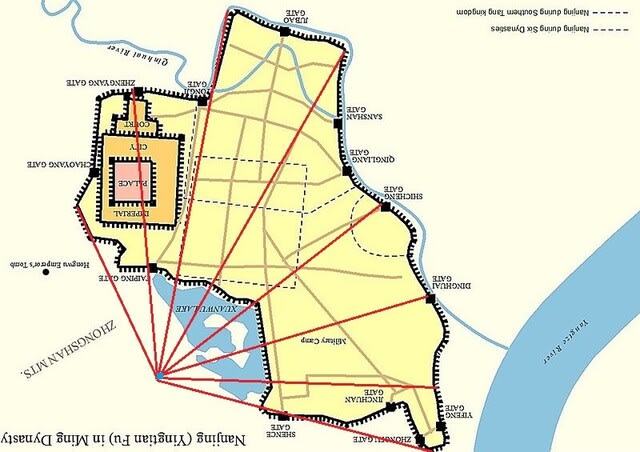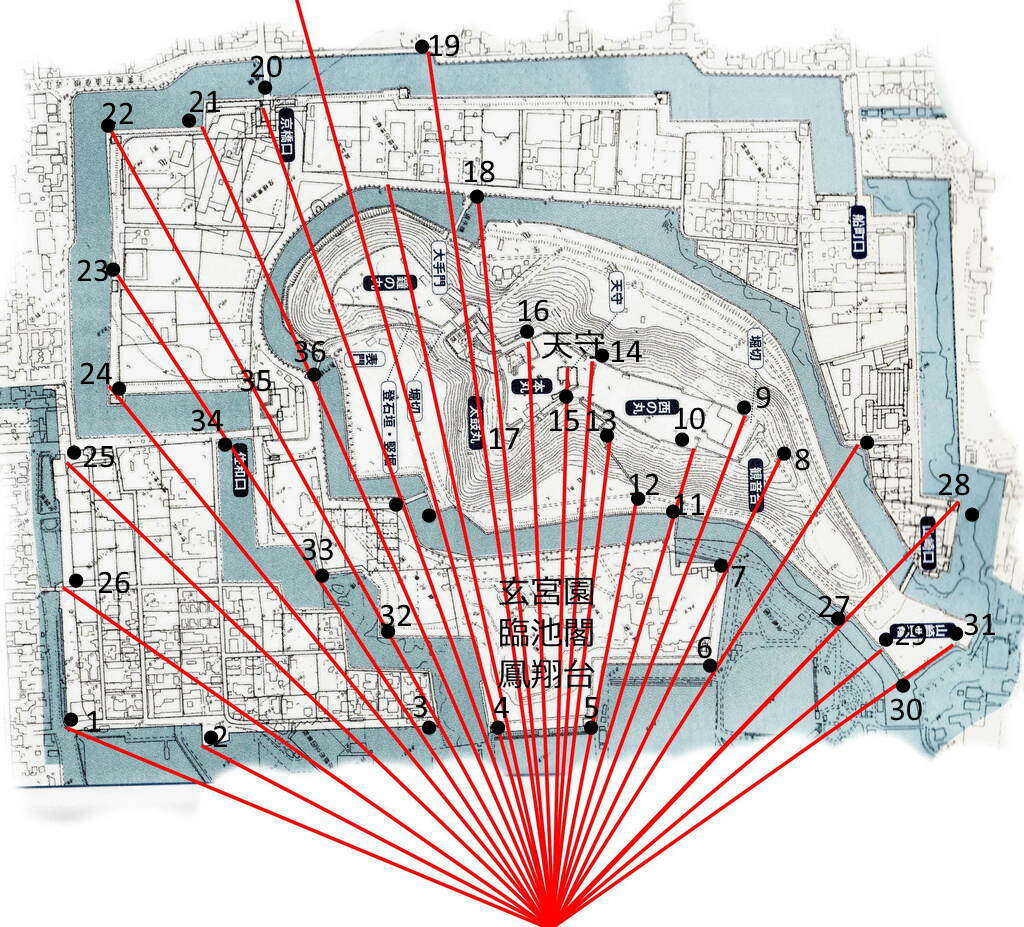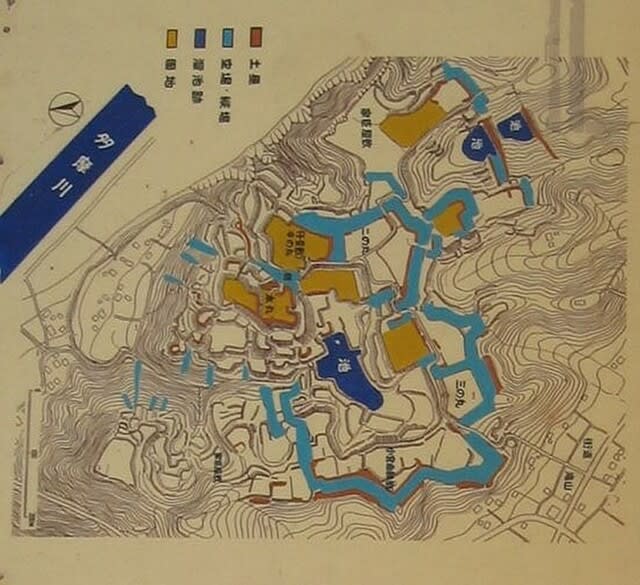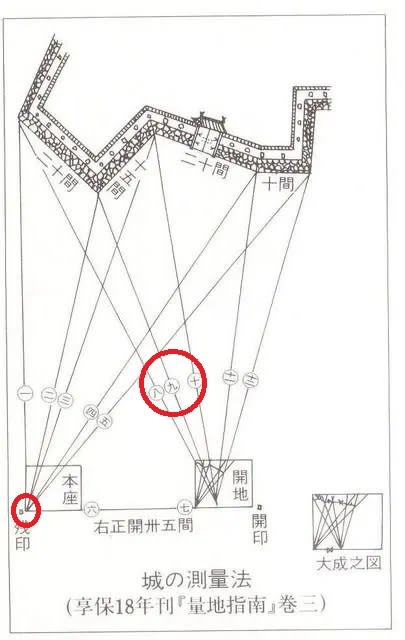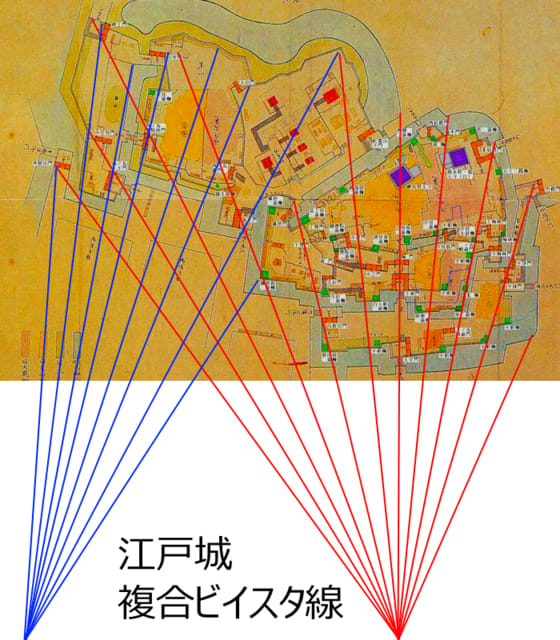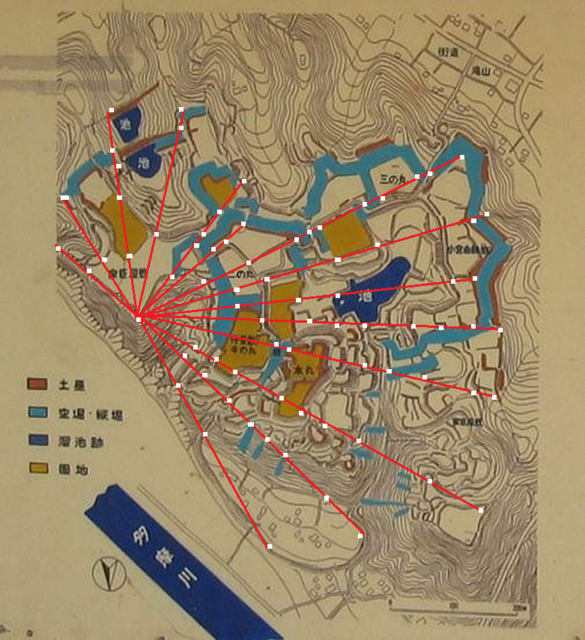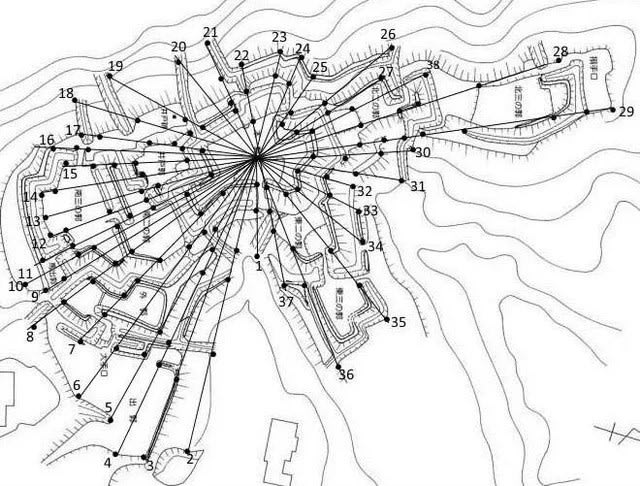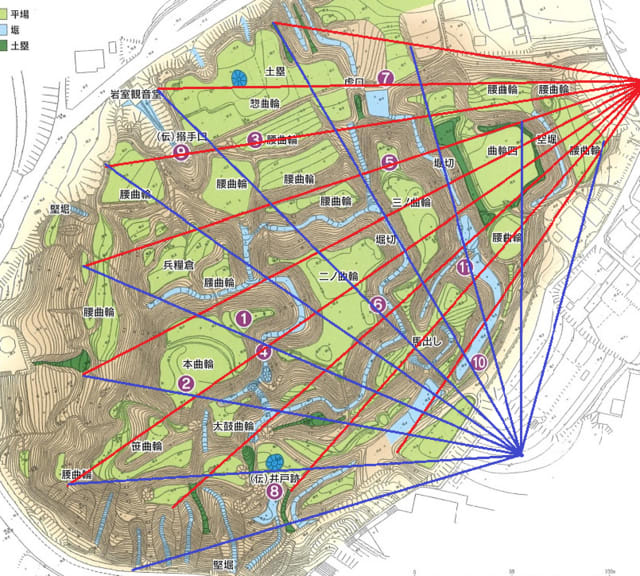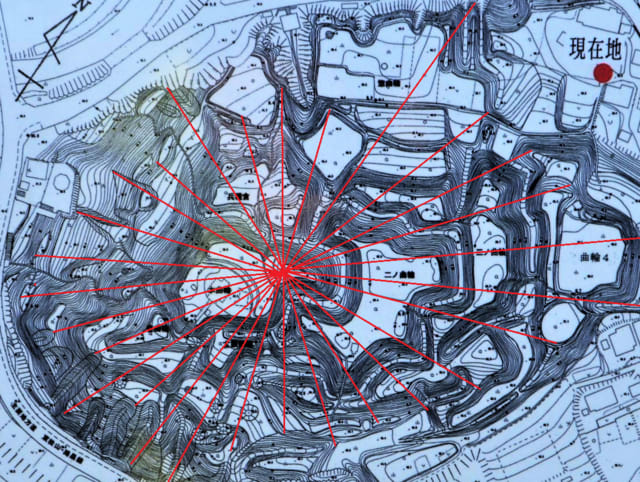◆山田城と深大寺城の幾何学設計
◆関東人
武蔵深大寺城などは古様の
関東城郭で言うイメージ所謂
ふるき郭の印象あがりますが?
天文1537年上杉朝定は難波田
弾正広宗に命じて深大寺城を
増築したとされてますからね!
▼深大寺城 主郭中央ビイスタ

◆長谷川
縄張図などの印象から古様な
る坂東の城の印象を受けます
が私は深大寺城の中核部とは
かなり高い測量技術を用いた
繊細な縄張であると考えてい
ます。本丸には中央ビイスタの
測量痕跡を読み取れまた主郭
副郭にも幾何学的な放射測量
を実施していると感じる城です。
▼深大城扇型ビイスタ工法

◆関東人
おっつと!そんな城郭研究手法
私は生まれて初めて聞く違和感
そして斬新性や研究の進歩性も
同時に感じているところですよ!
希代の城郭研究家とか隠れ氷山
の長谷川氏と一部で評価が高い
長谷川さんから見て関東の城で
高度な縄張技術を感じる関東の
城とは何城なのでしょうか?
◆長谷川
栃木県矢板市の山田城です。
この城は寒けがする程縄張の
レベルが高い緻密な城郭です
▼栃木山田城図

◆関東人
違うな!まったく私の感性主観
と長谷川さんの主観と切り口が
異なりその意見の断層に驚く!
例えば栃木山田城に中央から
計測した縄張技術あるのかね?
◆長谷川
山田城にも深大寺城にも両城
中央ビイスタが存在致します。
▼深大寺城 中央ビイスタ

▼山田城 中央ビイスタ

◆関東人
しかし山田城は原形を欠損
してるし 両城の縄張自体
が類似してるとは考えられな
い研究視点と言うかアンタの
平面図形咀嚼力がスゴイよ?
まあ構図的には類似してる。
◆関東人
まさかまさか?山田城には扇型
ビイスタ工法なんてシヤレた技
使ってないよね!?山田城は
俺なんかスゴイ城の部類には
入ってねえんだよなこの城は
◆長谷川
いいえ
北赤色ビイスタ
南黄色ビイスタ
とかなり巧妙な
設計技術です。

◆長谷川
これ相対型ビイスタと言います。
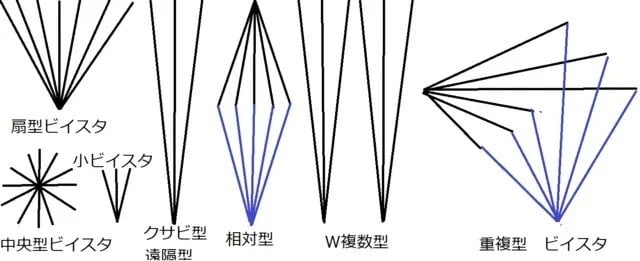
◆関東人
もうそれでビイスタは無いよね?
◆長谷川
いいえ
それが
東西からも赤青で測量して
内郭を縄張しておりまして
山田城には中央ビイスタ1
相対型ビイスタを複数で
使っていると言えますね。

下総根戸城のビイスタ工法