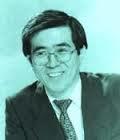表題は放送大学の「教育心理学概論」(主任講師 学習院大学大学院教授 太田信夫
先生)からの引用です。
この講義で印象に残ったものは
・向社会的(援助、分配、救済等の思いやりのある)行動を育てるしつけ
①愛情の除去タイプ:子どもが不適切な行動をした際には、無視したり
愛情を与えたりするのを控え、不安をあたえるしつけ。
②力によるしつけ:子どもの考えや行動を力づくで抑えようとする。とき
に、体罰や怒鳴りつけるなどの方法をとり、子どもの恐怖心、怒りを
あおることによるしつけ。
③説明によるしつけ:子どもの行動がなぜ不適切かを説明し、他者に
どのような影響を及ぼすのかを教えていくしつけ。
①と②は、即自的効果はあるが①は親の愛情ほしさに、②は親が怖いから
従うということになり、長い目で子どもの内面に思いやりや道徳性を芽生え
させることができない。
③のように、子どもが理解できるように説明していくしつけは何度も繰り
返さなければならないが、縦断的研究では、もっとも道徳性を成熟させる
という結果がみられている。
・自己効力感とは「自分にはある行動をうまくやり遂げることができる」と
いう自信のようなものである。これを味あわせるには、小分割された目標を
クリアしていくうちに、自然と大目標に到達できるような計画を作成する
ことが有効である。
・記憶方略
①符号化
語呂合わせ等
②イメージ化
新しい知識と意味の豊富な画像(イメージ)をペアにして記憶する
③言語的援助 イメージ化できない抽象的理論的知識には因果関係などの
言語的情報とともに記憶する
④分散効果
連続して反復するより時間間隔を空けて反復する方が効果的である
⑤処理水準効果
設問を想定しながら教科書を読む等
⑥生成効果
与えられた情報よりも、学習者自身が生成した情報のほうが記憶されやすい
・文科省の平成10年度の調査では、自然体験や生活体験が豊富な子どもほど
道徳心や正義感が強いことが示されている。
・状況的学習論
学習とは、1人で行うのではなく、社会やコミュニティやクラスに参加し、
そきでのやりとりを通じてなされるものだという立場をとる。