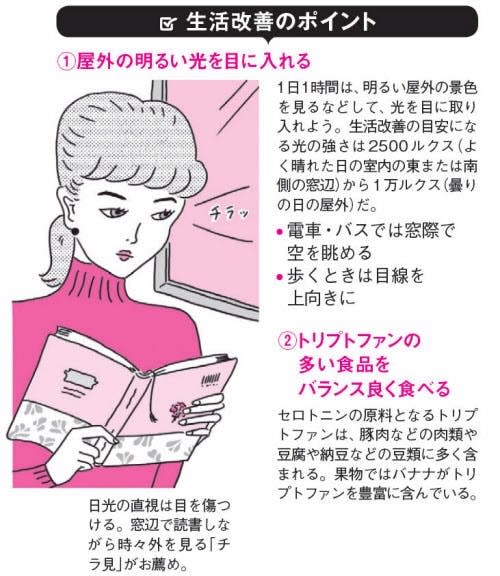少し前の話題になりますが、
2016年に発表された「うつ病治療ガイドライン」(日本うつ病学会)の問題点が2024年に修正された、
という記事が目に留まりました。
(はて、どういうこと?)
と気になり読んでみました。
その内容は「引用文献(原著論文)を読み込まないまま引用」に尽きるようです。
これは、一般の医学論文でも時々見かける現象です。
一つの論文を作成するためには、
参考にした文献を添付する必要があります。
それが結構膨大な量になり全部に目を通す余裕がないため端折る、
ということ。
後々残る資料ですから、許されないことですが。
とくにアカデミズムの集約である学会が発効するガイドラインでは、
あってはならぬこと。
学会への信頼性が大きく揺らいだことは否めません。
▢ 日本うつ病学会治療ガイドラインの修正版が公表うつ病治療ガイドラインの疑義は晴れたのか「修正によって治療方針を変更する必要が生じるものではない」、だが…
三和 護=医学ジャーナリスト
(2024/06/27;日経メディカル)より一部抜粋(下線は私が引きました);
日本うつ病学会は2024年3月11日、理事長名で「日本うつ病学会ガイドライン修正についてのお知らせ」を公表した。『日本うつ病学会治療ガイドライン II.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害2016』(以下、うつ病治療ガイドライン2016)の引用文献に対する疑義が発表されたのを機に、同学会が検証した結果、対象の文献157件のうち37.6%に問題ありと判断された。この影響でステートメントの削除・修正が39カ所で行われる事態に発展。学会は「修正によって治療方針を変更する必要が生じるものではない」とするが、傷付いた学会ガイドラインの信頼性をどうやって取り戻すかは今後の課題となる。
▶ 引用文献の約4割に問題、ステートメント削除・修正は39カ所
これまでの経緯を振り返っておきたい。2023年、福井大学医学部精神医学准教授の大森一郎氏らは、ステートメントと引用文献の内容とに食い違いがあると研修医が気付いたことを機に、『うつ病治療ガイドライン2016』の内容について批判的吟味を行った。その結果、第3章「中等症・重症うつ病」で65カ所、第4章「精神病性うつ病」で26カ所に、それぞれ「適切とは考えにくい引用文献」が確認され、第119回日本精神神経学会学術総会と第20回日本うつ病学会総会で発表した(関連記事:うつ病治療GLで「適切とは考えにくい引用文献」を指摘、うつ病治療ガイドラインに投げかけられた疑問符)。
これらの指摘を重く受け止めた日本うつ病学会は、学会外部メンバーを含めた検証ワーキンググループで議論を重ね、その結果を2024年3月11日に公表した1-5)。それによると、「問題あり」と判断された引用文献は、検証対象157件のうち37.6%に相当する59カ所に及んだ。
次に検証ワーキンググループは、問題が判明した引用文献を根拠とするステートメントについて、修正の必要性を検討。その結果、ステートメントの全文削除が8カ所(文末の表1、2)で、文言修正が31カ所でそれぞれ行われた。引用文献の修正のみ(削除、差し替え、追加など)は、15件だった(図1)。なお、こうした修正を反映させた『うつ病治療ガイドライン2016』は、3月1日付で公表されている6)。
これらの指摘を重く受け止めた日本うつ病学会は、学会外部メンバーを含めた検証ワーキンググループで議論を重ね、その結果を2024年3月11日に公表した1-5)。それによると、「問題あり」と判断された引用文献は、検証対象157件のうち37.6%に相当する59カ所に及んだ。
次に検証ワーキンググループは、問題が判明した引用文献を根拠とするステートメントについて、修正の必要性を検討。その結果、ステートメントの全文削除が8カ所(文末の表1、2)で、文言修正が31カ所でそれぞれ行われた。引用文献の修正のみ(削除、差し替え、追加など)は、15件だった(図1)。なお、こうした修正を反映させた『うつ病治療ガイドライン2016』は、3月1日付で公表されている6)。
・・・こうした全文削除や文言修正の理由については、公開された検証シート(「第3章 中等症・重症」3)、「第4章 精神病性」4))の中で説明されている。
なぜ「不適切な引用文献」が多発したのか。一般論ではあるが、2つの段階で問題があったのではないか。一つは引用文献の探索の段階で、原著論文を読み込まないまま引用してしまった可能性だ。もう一つは引用文献の確認の段階で、ダブルチェックが不十分だった点。さらに、こうしたミスを長年にわたって放置してきた学会のチェック機能の不備も重なったことになる。
なぜ「不適切な引用文献」が多発したのか。一般論ではあるが、2つの段階で問題があったのではないか。一つは引用文献の探索の段階で、原著論文を読み込まないまま引用してしまった可能性だ。もう一つは引用文献の確認の段階で、ダブルチェックが不十分だった点。さらに、こうしたミスを長年にわたって放置してきた学会のチェック機能の不備も重なったことになる。
▶ 「おわびして修正いたしました」
今回の修正を受けて日経メディカルでは、日本うつ病学会に対して、修正率37.6%の評価、うつ病の臨床現場および今後の学会活動への影響などについて見解を求めた。その結果、6月19日までに、日本うつ病学会理事長の渡邊衡一郎氏(杏林大学)とガイドライン検討委員会委員長の馬場元氏(順天堂大学)の連名で文章による回答を得た。以下に抜粋する。
Q 修正率37.6%という数字をどのように評価しているのか。また、引用文献に問題があったためステートメントの削除・修正が行われたが、その臨床現場への影響をどのように考えているのか。
A 検証の結果、第3章および第4章において多数のステートメントの修正・削除がなされました。これだけ多くの修正・削除があったことを当学会としては大変重く受け止めており、「お知らせ」にも記載した通り、おわびして修正いたしました。この結果は、臨床現場において診療にあたる医師や、患者さんご本人、ご家族など当事者の方々に不安や混乱を与えたものと思われます。一方で今回の修正・削除は、本ガイドラインに記載されている治療の推奨を変更するものではありませんでした。これも「お知らせ」に記載しました通り、このガイドライン自体がMinds 診療ガイドライン作成マニュアルに沿って作成されてはおらず、当時のエキスパートらのコンセンサスを基本とした治療の推奨となっております。このため今回の修正によって推奨そのものが変わるようなことはございません。つまり今回の修正によって治療方針を変更する必要が生じるものではないと考えております。
Q こうした訂正が実現できたことは、今後の日本うつ病学会の活動にどのようなプラスの影響をもたらすと考えるか。
A 今回の指摘とそれに基づく修正が実現できたことは、ガイドライン作成の方法論を見直す機会となり、より精度の高いガイドライン作成に向けての重要な経験になったと考えております。今回の事態をプラスに捉え、うつ病に関わる全ての人々にとって有用な、質の高いガイドラインを作成していきたいと思います。
Q 修正率37.6%という数字をどのように評価しているのか。また、引用文献に問題があったためステートメントの削除・修正が行われたが、その臨床現場への影響をどのように考えているのか。
A 検証の結果、第3章および第4章において多数のステートメントの修正・削除がなされました。これだけ多くの修正・削除があったことを当学会としては大変重く受け止めており、「お知らせ」にも記載した通り、おわびして修正いたしました。この結果は、臨床現場において診療にあたる医師や、患者さんご本人、ご家族など当事者の方々に不安や混乱を与えたものと思われます。一方で今回の修正・削除は、本ガイドラインに記載されている治療の推奨を変更するものではありませんでした。これも「お知らせ」に記載しました通り、このガイドライン自体がMinds 診療ガイドライン作成マニュアルに沿って作成されてはおらず、当時のエキスパートらのコンセンサスを基本とした治療の推奨となっております。このため今回の修正によって推奨そのものが変わるようなことはございません。つまり今回の修正によって治療方針を変更する必要が生じるものではないと考えております。
Q こうした訂正が実現できたことは、今後の日本うつ病学会の活動にどのようなプラスの影響をもたらすと考えるか。
A 今回の指摘とそれに基づく修正が実現できたことは、ガイドライン作成の方法論を見直す機会となり、より精度の高いガイドライン作成に向けての重要な経験になったと考えております。今回の事態をプラスに捉え、うつ病に関わる全ての人々にとって有用な、質の高いガイドラインを作成していきたいと思います。
▶ 批判的吟味の呼び掛けが信頼回復の第一歩に
回答にあったように日本うつ病学会は現在、日本医療機能評価機構のMinds 診療ガイドライン作成マニュアルに沿った新しい『うつ病診療ガイドライン』を作成中だ。7月に開かれる第21回日本うつ病学会総会で、ガイドラインの草稿を発表する運びとなっている。
一方、問題のあった『うつ病治療ガイドライン2016』は、エキスパートコンセンサスに基づいて作られたものになる。今回の修正によって「治療方針を変更する必要が生じるものではない」というコメントは救いになろうが、多くの修正・削除が行われた学会ガイドラインの信頼性をどうやって取り戻すかは今後の課題だ。全く新しいガイドラインになるからといって、信頼性が全面的に回復するとは限らない。一つの解決策は、修正のきっかけとなった研究を主導した大森氏らの「批判的吟味」(下記「大森氏のコメント」参照)という視点を、学会員のみならずガイドラインを利用する全ての医療関係者が持ち続けることではないだろうか。そのことを学会自らが呼び掛けることは、信頼回復の第一歩になるに違いない。
一方、問題のあった『うつ病治療ガイドライン2016』は、エキスパートコンセンサスに基づいて作られたものになる。今回の修正によって「治療方針を変更する必要が生じるものではない」というコメントは救いになろうが、多くの修正・削除が行われた学会ガイドラインの信頼性をどうやって取り戻すかは今後の課題だ。全く新しいガイドラインになるからといって、信頼性が全面的に回復するとは限らない。一つの解決策は、修正のきっかけとなった研究を主導した大森氏らの「批判的吟味」(下記「大森氏のコメント」参照)という視点を、学会員のみならずガイドラインを利用する全ての医療関係者が持ち続けることではないだろうか。そのことを学会自らが呼び掛けることは、信頼回復の第一歩になるに違いない。
▶ 日経メディカルに寄せられた大森氏のコメントから
「明確な臨床疑問を持ち、適切な論文を見つけ、批判的に読む。その結果を目の前の患者の診療にどう生かすかについて、経験を踏まえて考える。患者の意向を最大限尊重する。今回の批判的吟味の取り組みは、そうしたプロセスの大切さを改めて考えるきっかけになりました。ともに学ぶ福井大学の若い医師が、この取り組みを通じて『ガイドラインをうのみにすることはできない。原著論文をきちんと読まなければならない』という実感を持ってくれたことは、私にとって大切なアウトカムの一つです」
「明確な臨床疑問を持ち、適切な論文を見つけ、批判的に読む。その結果を目の前の患者の診療にどう生かすかについて、経験を踏まえて考える。患者の意向を最大限尊重する。今回の批判的吟味の取り組みは、そうしたプロセスの大切さを改めて考えるきっかけになりました。ともに学ぶ福井大学の若い医師が、この取り組みを通じて『ガイドラインをうのみにすることはできない。原著論文をきちんと読まなければならない』という実感を持ってくれたことは、私にとって大切なアウトカムの一つです」