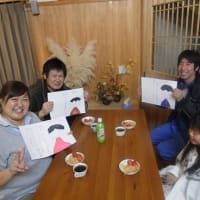エヴァホームの浅井です。
今日は待ちに待った、新富町現場の地鎮祭。
昨年暮れから図面作成に入っていましたが、長期優良住宅に対応するため着工が延びていました。
先週末にようやく適合審査の認定、そして建築許可が下りてきました。
後は現地行政庁の承認を得て、着工となります。
地鎮祭の今朝はいつものように、6時前から竹やぶに入って竹取り。
そして、地鎮祭用具一式を軽トラに積み込んで新富町現場に到着したのが9時半。
早速、棟梁の楠見さんとスタッフの森山と私の三人で設営開始しましたが・・
「普段したことのない、私と森山の肉体労働の結果は?」
最初のテントの建て込みだけで私と森山はヘロヘロ状態。
1時間ほどかかって、建物の位置を出す「縄張り」が終わったころには眩暈でクラクラ。
祭事の行われている間にようやく一息つきました。

祭事の後は、縄張りの確認。
敷地境界線と建物の位置を建築許可の図面を使って、お施主様に確認してもらいます。

1.<読書>
私の読んでいる本はWeb本棚にあります。
「うそうそ」 畠中恵 新潮文庫
「しゃばけ」シリーズが340万部突破と帯にかかれています。
最近「畠中恵」を知った私は、本当によく読まれているのだとようやく理解できました。
とにかく忙しかった8月。なかなか読む時間も取れずにようやく一冊。
その「しゃばけ」シリーズの第五弾。
日本橋の大店の若だんな・一太郎は、摩訶不思議な妖怪に守られながら、今日も元気に(?)寝込んでいた。
その上、病だけでは足りず頭に怪我まで負ったため、主に大甘の二人の手代、兄・松之助と箱根へ湯治に行くことに!
初めての旅に張り切る若だんなだったが、誘拐事件、天狗の襲撃、謎の少女の出現と、旅の雲行きはどんどん怪しくなっていき…。
2.<住宅情報>
住宅関連ニュース
1. 共有名義について確認しましょう
住宅を取得した場合に、不動産登記を単独名義にするか共有名義にするかは、
将来の売却や相続のことも含めて慎重に判断する必要があります。
共有名義のメリットとしては、たとえば、税制上、夫婦の出資割合と持分が一致していないと、
贈与税がかかりますが、共有持分を出資割合と一致させることで、贈与税の課税をさけることができます。
また、居住用財産の特別控除(3,000万円特別控除)や、居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が、共有にすることで、夫婦それぞれ受けることができます。
一方で、デメリットとしては、共有持分は相続の対象となるので、共有者の方が亡くなると、
相続税の課税対象となる場合があります。
相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人数)を超える相続財産がある場合は、注意が必要です。
また、夫婦共働きで住宅ローンを連帯債務で借りて共有名義にした場合に、
住宅ローンを完済する前に妻が退職すると、出資割合(住宅ローンの負担割合)が持分と合わなくなり、
贈与税の課税対象となる可能性があります。
○ 詳しくはこちら
http://www.jhf.go.jp/jumap/navi/build/step52.html
2. 日本建築学会が木造禁止を巡り「美味しんぼ」に反論
日本建築学会は、1959年に同会が「木造禁止」を提起した際の経緯などを解説する文章を公表した。
小学館が発行する「ビッグコミックスピリッツ」で連載中の人気マンガ「美味しんぼ」のなかの、
「日本の家屋で国産材の使用率が著しく低い一因は、日本建築学会が59年に木造建築を否定したため」という
趣旨の記述に関して、読者から事実を確認する問い合わせが2件、寄せられたためだ。
日本建築学会は、「木造禁止」という言葉がひとり歩きすると、本来の意味や同会の
活動に対する誤解を招くことになるとして、7月にホームページ上で解説を掲載。
これによると、「木造禁止」の提起に至った経緯やその後の取り組みは次のようなものだった。
59年9月の伊勢湾台風では、5000人以上が死亡または行方不明となり、約15万棟の住宅が全壊または半壊した。
これを受けて同年10月、火災や風水害防止を目的とした「建築防災に関する決議」で「木造禁止」を提起した。
60年には中央行政庁に対して災害危険区域の指定などを、地方公共団体に対して建築物の制限などを要望した意見書を提出。
さらに、61年には対策について詳しく記述した「伊勢湾台風災害調査報告」を刊行した――。
日本建築学会は「木造建築全般の禁止を一律に求めたものではなく、危険の著しい地域を
防災地域として指定し、この地域における建築制限の一つとして、木造禁止を提起した」と説明する。
また、木造建築に関する技術書の発行などを継続的に行ってきたと主張している。
「木造禁止」について冒頭のように記述した「美味しんぼ」が掲載されたのは、
「ビッグコミックスピリッツ」の10年5月3日号だ。
この中には「一級建築士の試験では木造について一切扱わないし、大学でも木造建築を教えない」との記述もあった。
3.<今日の現場>
4.<音楽> 今日、こんな歌を聴きました。
休みをもらって帰っていた長女も千葉に帰っていきました。
次女も火曜日には東京の大学に帰ります。
夏休みが少なくなった子供たちにこの歌をおくります。
夏休み よしだたくろう
今日は待ちに待った、新富町現場の地鎮祭。
昨年暮れから図面作成に入っていましたが、長期優良住宅に対応するため着工が延びていました。
先週末にようやく適合審査の認定、そして建築許可が下りてきました。
後は現地行政庁の承認を得て、着工となります。
地鎮祭の今朝はいつものように、6時前から竹やぶに入って竹取り。
そして、地鎮祭用具一式を軽トラに積み込んで新富町現場に到着したのが9時半。
早速、棟梁の楠見さんとスタッフの森山と私の三人で設営開始しましたが・・
「普段したことのない、私と森山の肉体労働の結果は?」
最初のテントの建て込みだけで私と森山はヘロヘロ状態。
1時間ほどかかって、建物の位置を出す「縄張り」が終わったころには眩暈でクラクラ。
祭事の行われている間にようやく一息つきました。

祭事の後は、縄張りの確認。
敷地境界線と建物の位置を建築許可の図面を使って、お施主様に確認してもらいます。

1.<読書>

私の読んでいる本はWeb本棚にあります。
「うそうそ」 畠中恵 新潮文庫
「しゃばけ」シリーズが340万部突破と帯にかかれています。
最近「畠中恵」を知った私は、本当によく読まれているのだとようやく理解できました。
とにかく忙しかった8月。なかなか読む時間も取れずにようやく一冊。
その「しゃばけ」シリーズの第五弾。
日本橋の大店の若だんな・一太郎は、摩訶不思議な妖怪に守られながら、今日も元気に(?)寝込んでいた。
その上、病だけでは足りず頭に怪我まで負ったため、主に大甘の二人の手代、兄・松之助と箱根へ湯治に行くことに!
初めての旅に張り切る若だんなだったが、誘拐事件、天狗の襲撃、謎の少女の出現と、旅の雲行きはどんどん怪しくなっていき…。
2.<住宅情報>
住宅関連ニュース
1. 共有名義について確認しましょう
住宅を取得した場合に、不動産登記を単独名義にするか共有名義にするかは、
将来の売却や相続のことも含めて慎重に判断する必要があります。
共有名義のメリットとしては、たとえば、税制上、夫婦の出資割合と持分が一致していないと、
贈与税がかかりますが、共有持分を出資割合と一致させることで、贈与税の課税をさけることができます。
また、居住用財産の特別控除(3,000万円特別控除)や、居住用財産の買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が、共有にすることで、夫婦それぞれ受けることができます。
一方で、デメリットとしては、共有持分は相続の対象となるので、共有者の方が亡くなると、
相続税の課税対象となる場合があります。
相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×相続人数)を超える相続財産がある場合は、注意が必要です。
また、夫婦共働きで住宅ローンを連帯債務で借りて共有名義にした場合に、
住宅ローンを完済する前に妻が退職すると、出資割合(住宅ローンの負担割合)が持分と合わなくなり、
贈与税の課税対象となる可能性があります。
○ 詳しくはこちら
http://www.jhf.go.jp/jumap/navi/build/step52.html
2. 日本建築学会が木造禁止を巡り「美味しんぼ」に反論
日本建築学会は、1959年に同会が「木造禁止」を提起した際の経緯などを解説する文章を公表した。
小学館が発行する「ビッグコミックスピリッツ」で連載中の人気マンガ「美味しんぼ」のなかの、
「日本の家屋で国産材の使用率が著しく低い一因は、日本建築学会が59年に木造建築を否定したため」という
趣旨の記述に関して、読者から事実を確認する問い合わせが2件、寄せられたためだ。
日本建築学会は、「木造禁止」という言葉がひとり歩きすると、本来の意味や同会の
活動に対する誤解を招くことになるとして、7月にホームページ上で解説を掲載。
これによると、「木造禁止」の提起に至った経緯やその後の取り組みは次のようなものだった。
59年9月の伊勢湾台風では、5000人以上が死亡または行方不明となり、約15万棟の住宅が全壊または半壊した。
これを受けて同年10月、火災や風水害防止を目的とした「建築防災に関する決議」で「木造禁止」を提起した。
60年には中央行政庁に対して災害危険区域の指定などを、地方公共団体に対して建築物の制限などを要望した意見書を提出。
さらに、61年には対策について詳しく記述した「伊勢湾台風災害調査報告」を刊行した――。
日本建築学会は「木造建築全般の禁止を一律に求めたものではなく、危険の著しい地域を
防災地域として指定し、この地域における建築制限の一つとして、木造禁止を提起した」と説明する。
また、木造建築に関する技術書の発行などを継続的に行ってきたと主張している。
「木造禁止」について冒頭のように記述した「美味しんぼ」が掲載されたのは、
「ビッグコミックスピリッツ」の10年5月3日号だ。
この中には「一級建築士の試験では木造について一切扱わないし、大学でも木造建築を教えない」との記述もあった。
3.<今日の現場>
4.<音楽> 今日、こんな歌を聴きました。
休みをもらって帰っていた長女も千葉に帰っていきました。
次女も火曜日には東京の大学に帰ります。
夏休みが少なくなった子供たちにこの歌をおくります。
夏休み よしだたくろう