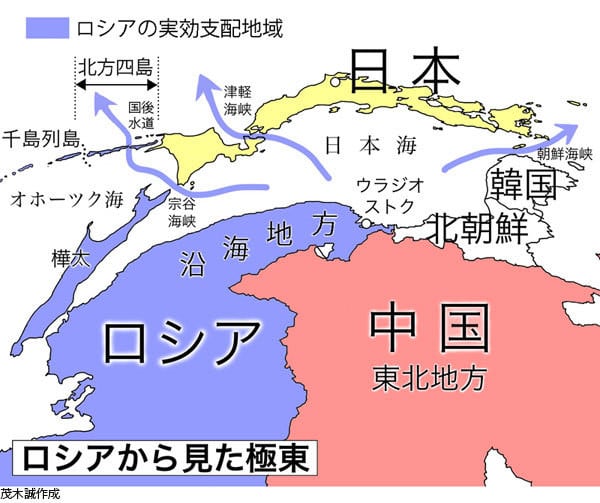記事投稿日:2020/02/24 11:00 最終更新日:2020/02/24 11:00
「女性自身」2020年3月3日号 掲載
「母の認知症の症状は、突然出たんです。だから最初の1年は、私自身、どう過ごしていたか、よく覚えていない。記憶が飛んでいるっていうかね、それほど混乱していましたね」
女優・松島トモ子さん(74)
<>松島 トモ子(まつしま ともこ、本名;松島 奉子[1](ともこ)、1945年7月10日 - 74歳。)は、日本の女優、歌手、タレント[2]。日本芸術専門学校特別講師。現在、毒蝮三太夫が所属する、まむしプロダクションと業務提携をしている。
巣鴨プリズン慰問[編集]
1950年11月19日、舞踏家の石井漠らと共に巣鴨プリズン所長・鈴木英三郎に、刑務所近くにある米軍専用の劇場に招かれた。司会者は、三井物産のタイのハジャイ出張所所長であった松島の父・高橋健が満州奉天で召集をうけたのちシベリアに抑留され生死も不明で、松島は母と二人でかろうじて帰国したと紹介し、会場は静まり返った(その後父はナホトカ郊外の収容所で1945年10月29日に死亡していたことが判明)。続いて法被姿に鉢巻をしめ大きな目をした5歳の松島が現れ、洋舞「かわいい魚屋さん」を踊った。並んだ約1千名の戦犯らは涙を流して深く感動し、何度もアンコールし、彼女もそれに応えた。
2度の猛獣襲撃事故[編集]
1986年には日本テレビ『TIME21』の撮影でケニアを訪れて、10日の間にライオンとヒョウに立て続けに2度襲われ、帰国後にギブス姿で記者会見して話題になった[4]。1月28日にジョイ・アダムソン(『野生のエルザ』の作者)の夫であるジョージ・アダムソンと共にナイロビのコラ動物保護区でエルザの子孫でジョージによりラクダの肉で餌付けされ人に慣れた雌ばかり7頭のライオンの群れと接触し子ライオンと戯れていたところ、ジョージがキャンプとの無線で松島とライオン達から目を離した隙にその子ライオンの母親に襲われ、松島は宙に飛び10メートルほど引きずられサファリスーツはズタズタ、首や太腿に全治10日の怪我を負う[5](目を離していたジョージは耳が遠く助けに行くのが遅れた)。その際にジョージにより松島は助けられた。このとき周りには複数のライオンがいたが、攻撃を加えたのは一頭のみである。
10日の入院予定だったが3日で退院して仕事を再開[5]、再び別の動物保護区を訪れ、万全の態勢でロケに挑むが、10日後の2月7日に保護区のスタッフで責任者のトニー・フィッツジョンと共にこの保護区で飼育されている雌ヒョウの「コムンユ」を見に、周りを高い柵で囲われた施設に行った。施設の外に出たところ、そのヒョウが夜陰に乗じて柵を跳び越えて待ち伏せており、迂闊にも目を合わせてしまった松島に体当たりで襲いかかった。奇襲を受けて地に倒された松島はそのまま首を噛み付かれ、なおかつ持ち上げられた。このとき骨がガリガリと囓られる音が聞こえ[5]、「死んだ」と思ったという。これは、松島の隣にいたこのヒョウの飼い主のトニーが、松島と親しくしているように見えたためヒョウが嫉妬したと考えられている。また、松島の目が大きいのも襲われる理由だと後で言われた[5]。
この後、松島は救助隊に救急ヘリを要求したが、夜間の飛行は危険であるとして拒否されてしまう。結局、朝まで止血しながら耐える羽目になり、その後、朝になり救急ヘリが到着し、ようやく病院に運ばれ、第四頚椎粉砕骨折[注釈 1]という診断を受けたが、ヒョウの噛む位置があと1ミリずれていたら松島は間違いなく死んでいただろうとされる[5]。第四頚椎粉砕骨折は後遺症も無く生還するのが奇跡と言われており(高確率で死亡。良くても首から下が動かなくなる程の後遺症が残る)、松島の症例はニューヨークの学会で発表されたほどである[5][注釈 2]。
ヒョウに襲われた後も撮影を続けて、2月17日に帰国、コルセットをつけて記者会見に臨み「それでも動物が好き」とコメントした[6]。このときに撮影された映像は3月31日に「それでも私はライオンが好き」と題して『TIME21』で放送された[7]。
この事故が発生する前、1986年の元日に松島からアナウンサーの伊藤勉に送られてきた年賀状には、仕事でアフリカに行く予定であることが書かれていると同時に、「ライオンに食べられないように祈って下さいませ。またお目にかかれますように」とも書かれていた。後年、この件について伊藤は「まさか本当にあんな事件が起こるとは思ってませんでしたから、笑って軽く読み流したんです。あの時は本当に私の祈りが足らなかったのではないかと悔やみました」と語った。一方、松島本人は、年賀状の効果はなかったのではないかと問われた際に「いいえ、ありましたよ。あれを書いていなかったら命があったかどうか。皆さんの祈りが通じて、噛まれただけですんだんだと思います」と返答している[5]。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B3%B6%E3%83%88%E3%83%A2%E5%AD%90
<>
は母・志奈枝さん(99)が突然、認知症を発症した日から始まった介護の日々を一気に振り返る。
「母の親しいお友達を招いて、都内の中華料理店で95歳の誕生会を開いていました。でも、母の様子が明らかにおかしい。いつもは、好奇心旺盛な母が、人の話を聞こうともせずガツガツと料理を食べ続けていたんです。私は、母に合図を送るつもりでテーブルの下から母のヒザに手をやりました。そしたら、母が失禁していた。もうあのときは、頭が真っ白になってしまって」
帰宅してからが地獄でした。ふだんから私とも敬語で話していた母が、罵詈雑言の嵐。『年寄りを虐待してアンタは楽しいのか!なんて言っては、周りのものを手当たり次第投げつけてくる。いつも綺麗でレディだった母が、180度変わってしまった。
「真夜中になると、『トモ子に殺される!』と大声で叫びながら外に飛び出すんです。母は短距離の選手でしたから、徘徊というより、まるで“遁走”。速い、速い。とても追いつけません。だから私、夜は母の部屋の前に布団を敷いて、洋服を着たまま寝ていました」
それでも、松島さんは自宅介護を続けた。そこには、ずっと松島さんを守り、4歳でデビューしてからもつきっきりでマネージャーを務めてくれた母への思いがあったからだという。
松島さんは、45年に旧満州の奉天(現在の中国・瀋陽市)に生まれた。
「奉天は、三井物産の商社マンだった父の赴任先でした。母も、三井物産の社員の娘で、幼い頃は香港のイギリス系女子校で学んだお嬢さま」
そんな両親の元に生まれた松島さんは、なに不自由ない生活を送るはずだった。しかし、45年4月。父に召集令状が届く。松島さんが誕生する、わずか2カ月前のことだった。
「父は、私が生まれるのを心待ちにして、戦地から何通も母にはがきを送っていたそうです。最後に届いたはがきには、〈待っていてくれ! 必ず無事でいてくれ〉と書かれていました」
父が出征してから3カ月後、日本は敗戦――。
「ソ連が進駐してくるなか、母は生後1カ月の私を必死で守ったそうです。でも、待てど暮らせど父は帰ってこなかった。翌46年5月、突然決まった引き上げ。母は私を抱きかかえて、ぎゅうぎゅう詰めの屋根のない“無蓋列車”で奉天を出発。その後、引揚船で命からがら帰国しました。『赤ん坊を船に乗せたら死んでしまう。(中国に)置いていけ』と何度も言われたそうですが、母は、『この子を無事に連れて帰れたら、もう一生、自分自身の望みごとはしません』と神様に祈って、決心を変えなかった。同じ船で生き残った乳飲み子は、私を含め2人だけでした」
その後、父はシベリアで亡くなったことが判明する。
親子の長い旅路が始まった。それからも、松島さんと志奈枝さんは、常に一緒だった。
「(認知症が)発症して1カ月後、とうとう私は慣れない介護の疲れとストレスで倒れてしまった。診断はストレス障害。体重も40キロから33キロになって。周りからは『共倒れになるから介護施設に入れたほうがいい』と言われました。でも母は昔、旧満州から幼い私を抱えて命がけで日本に戻ってきてくれた。それを思うと、今度は私が恩返しをする番じゃないかって。でも、何がいいかは、ご家庭で違います。施設に預けたほうがいいこともありますからね」
大変な日々が続くからこそ、母と過ごすなんでもない平凡な1日が幸せ、と思うようになった、と語った松島さん。完璧な母親のまま亡くなっていたらきっと立ち直ることができなかった、と言葉を続けた。
二人で暮らすことが、いつだって守ってくれた母への恩返しだ――。