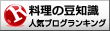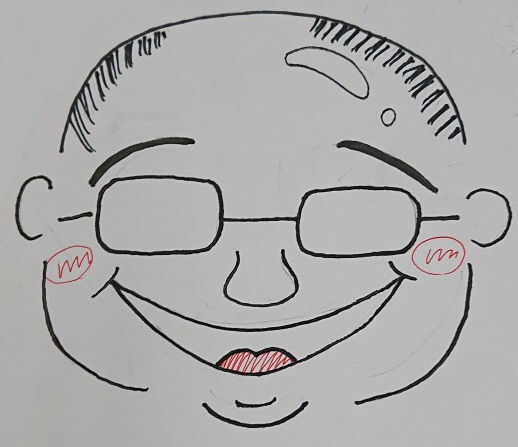【10月4日は何の日】イワシの日
【10月5日は何の日】みそおでんの日
【10月6日は何の日】メロンの日
【10月7日は何の日】生パスタの日
【前の答え】箸の持ち方
Q1,箸の数え方は何でしょうか?
a,一杯 b,一膳 c,一玉 d,一包
→b,一杯はイカやタコ、一玉はキャベツ、一包は粉薬の数え方です。
Q2,「つまらぬことまで口やかましく小言を言うこと」を何というでしょうか?
→箸の上げ下ろし
Q3,「どうにもこうにも手が付けられず、取り扱いに困ること」を何というでしょうか?
→箸にも棒にもかからぬ
【脳トレの答え】バナナ
【正しく読むと?の答え】荒ぶ →すさぶ
【空欄にチャレンジの答え】〇△っ▢▽ー →ぶろっこりー
【今日の話】
ナイフ、フォーク、スプーンのように、
それぞれが切る・刺す・すくうという一つの機能しか持たない道具なのに対して、
箸は「つまむ、はさむ、押さえる、すくう、裂く、のせる、
はがす、ほぐす、くるむ、切る、運ぶ、混ぜる」といった12もの機能をもっています。
ほとんどのことができるので、指先と同じ感覚なのですよね。
他人に自分の箸を使われるのを嫌うのは、
箸が指先以上の働きをしているととらえる民族性が今も受け継がれているからではないでしょうか。
さて、箸以外のマナーについてもみていきましょう。
ご飯は左に、汁物は右に、主菜は右奥に、小さな副菜(漬物など)は真ん中に、
小さな副菜(サラダなど)は左奥に置きます。
汁物にふたがある場合、ふたは裏返して右側に置きましょう。
はじめに食べるのは汁物です。
汁物は持って食べていますよね。
汁物を最初に食べることでお腹が温まり、食べ物を消化しやすくします。
また、箸を湿らせることで、
粘り気のある米が箸にくっつくことを防ぐことができます。
汁物を最初に食べたら、
そのあとは「味が薄いもの→味が濃いもの」の順番に食べます。
しょう油やソースなどを使った味が濃いおかずを先に食べてしまうと、
ご飯や野菜のおひたしなどの薄い味付けのものが物足りなく感じます。
しかし、はじめて食べるものは、どんな味なのかわからないですよね。
そんな時は「汁物→ご飯→おかず」の順番に食べればOKです。
そしてまた「汁物→ご飯→おかず」の順番を繰り返します。
日本の食事では「きれいに食べること」が重視されます。
そのため、見た目が悪かったり、汚してしまったりするのはマナー違反になります。
そして、嫌い箸というものもあります。つい、してしまうこともあるんですよね。
「洗い箸」汁物などで箸を洗うこと。
「移り箸」いったん取りかけてから他の料理に箸を移すこと。
「刺し箸」お箸を食べ物に突き刺して食べること。
「返し箸・逆さ箸」料理を取り分ける際、箸を上下逆さにして使うこと。
神仏と食事を共にするという信仰的見地からは、
上は神仏が使う側になるので、取り箸を使うのがマナーです。
「掻き箸」食器の縁に口を当てて、箸で掻き込むこと。
「重ね箸」ひとつの料理ばかり食べ続けること。
「咥え箸」箸をくわえること。
「探り箸」料理を箸でかき回し、自分の好きなものを探り出して取ること。
「指し箸」箸で人やものを指すこと。
「刺し箸」箸を料理に突き刺して食べること。
「直箸」取箸があるのに使わず、自分の箸で大皿の料理を取ること。
「せせり箸」箸を爪楊枝代わりにすること。
「揃え箸」箸を食器やテーブルに突き立てて揃えること。
「たたき箸」箸で食器を叩き音を出し人を呼ぶこと。
「立て箸」箸をご飯に突き刺して立てること。
「ちぎり箸」箸を両手に1本ずつ持って料理をちぎること。
「ねぶり箸」箸をなめること。
「箸渡し」箸から箸へ料理を受け渡すこと。
「迷い箸」どの料理を食べようかと、料理の上で箸をあちこちと動かすこと。
「持ち箸」箸を持った手で同時に器も持つこと。
「横箸」箸を二本揃えて持ち、スプーンのようにすくい上げること。
「寄せ箸」箸で遠くの食器を手元に引き寄せること。
「渡し箸」食事の途中で箸を食器の上に渡し置くこと。「もういりません」という 意味になります。
たくさんありますが、私も意識していきたいと思います。
Q1,食器を置くときに( )を立てる
Q2,( )顔やテーブルを拭く
Q3,テーブルに( )をついて食べる
Q4,お椀や皿を持たずに( )を料理に近づけて食べる
【今日のひと言】意識の方法を変える
【今日の脳トレ】

【正しく読むと?】浅薄
【空欄にチャレンジ】〇な△め△゛
【今日の地名】菰野町
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
こものちょう
三重県。昔、マコモ(真菰:イネ科の多年草)や
クサヨモギなどが生い茂る原野が広がっていたことから名づけられたそうです。
【10月5日は何の日】みそおでんの日
【10月6日は何の日】メロンの日
【10月7日は何の日】生パスタの日
【前の答え】箸の持ち方
Q1,箸の数え方は何でしょうか?
a,一杯 b,一膳 c,一玉 d,一包
→b,一杯はイカやタコ、一玉はキャベツ、一包は粉薬の数え方です。
Q2,「つまらぬことまで口やかましく小言を言うこと」を何というでしょうか?
→箸の上げ下ろし
Q3,「どうにもこうにも手が付けられず、取り扱いに困ること」を何というでしょうか?
→箸にも棒にもかからぬ
【脳トレの答え】バナナ
【正しく読むと?の答え】荒ぶ →すさぶ
【空欄にチャレンジの答え】〇△っ▢▽ー →ぶろっこりー
【今日の話】
ナイフ、フォーク、スプーンのように、
それぞれが切る・刺す・すくうという一つの機能しか持たない道具なのに対して、
箸は「つまむ、はさむ、押さえる、すくう、裂く、のせる、
はがす、ほぐす、くるむ、切る、運ぶ、混ぜる」といった12もの機能をもっています。
ほとんどのことができるので、指先と同じ感覚なのですよね。
他人に自分の箸を使われるのを嫌うのは、
箸が指先以上の働きをしているととらえる民族性が今も受け継がれているからではないでしょうか。
さて、箸以外のマナーについてもみていきましょう。
ご飯は左に、汁物は右に、主菜は右奥に、小さな副菜(漬物など)は真ん中に、
小さな副菜(サラダなど)は左奥に置きます。
汁物にふたがある場合、ふたは裏返して右側に置きましょう。
はじめに食べるのは汁物です。
汁物は持って食べていますよね。
汁物を最初に食べることでお腹が温まり、食べ物を消化しやすくします。
また、箸を湿らせることで、
粘り気のある米が箸にくっつくことを防ぐことができます。
汁物を最初に食べたら、
そのあとは「味が薄いもの→味が濃いもの」の順番に食べます。
しょう油やソースなどを使った味が濃いおかずを先に食べてしまうと、
ご飯や野菜のおひたしなどの薄い味付けのものが物足りなく感じます。
しかし、はじめて食べるものは、どんな味なのかわからないですよね。
そんな時は「汁物→ご飯→おかず」の順番に食べればOKです。
そしてまた「汁物→ご飯→おかず」の順番を繰り返します。
日本の食事では「きれいに食べること」が重視されます。
そのため、見た目が悪かったり、汚してしまったりするのはマナー違反になります。
そして、嫌い箸というものもあります。つい、してしまうこともあるんですよね。
「洗い箸」汁物などで箸を洗うこと。
「移り箸」いったん取りかけてから他の料理に箸を移すこと。
「刺し箸」お箸を食べ物に突き刺して食べること。
「返し箸・逆さ箸」料理を取り分ける際、箸を上下逆さにして使うこと。
神仏と食事を共にするという信仰的見地からは、
上は神仏が使う側になるので、取り箸を使うのがマナーです。
「掻き箸」食器の縁に口を当てて、箸で掻き込むこと。
「重ね箸」ひとつの料理ばかり食べ続けること。
「咥え箸」箸をくわえること。
「探り箸」料理を箸でかき回し、自分の好きなものを探り出して取ること。
「指し箸」箸で人やものを指すこと。
「刺し箸」箸を料理に突き刺して食べること。
「直箸」取箸があるのに使わず、自分の箸で大皿の料理を取ること。
「せせり箸」箸を爪楊枝代わりにすること。
「揃え箸」箸を食器やテーブルに突き立てて揃えること。
「たたき箸」箸で食器を叩き音を出し人を呼ぶこと。
「立て箸」箸をご飯に突き刺して立てること。
「ちぎり箸」箸を両手に1本ずつ持って料理をちぎること。
「ねぶり箸」箸をなめること。
「箸渡し」箸から箸へ料理を受け渡すこと。
「迷い箸」どの料理を食べようかと、料理の上で箸をあちこちと動かすこと。
「持ち箸」箸を持った手で同時に器も持つこと。
「横箸」箸を二本揃えて持ち、スプーンのようにすくい上げること。
「寄せ箸」箸で遠くの食器を手元に引き寄せること。
「渡し箸」食事の途中で箸を食器の上に渡し置くこと。「もういりません」という 意味になります。
たくさんありますが、私も意識していきたいと思います。
Q1,食器を置くときに( )を立てる
Q2,( )顔やテーブルを拭く
Q3,テーブルに( )をついて食べる
Q4,お椀や皿を持たずに( )を料理に近づけて食べる
【今日のひと言】意識の方法を変える
【今日の脳トレ】

【正しく読むと?】浅薄
【空欄にチャレンジ】〇な△め△゛
【今日の地名】菰野町
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
こものちょう
三重県。昔、マコモ(真菰:イネ科の多年草)や
クサヨモギなどが生い茂る原野が広がっていたことから名づけられたそうです。