こんにちは腎臓サポートチャンネルへようこそ 看護師のザキです
本日は血糖値スパイクを防ぐ最強のお茶を7つご紹介していきたいと思います。
血糖値スパイクは血管にものすごくダメージを与えます。
注意:
①カリウムの多いお茶なのでカリウム制限がない方に有効です。
カリウム制限のある方は主治医の指導の元よろしくお願いします。
②もちろんお茶なので、劇的に血糖値スパイクを防ぐというものではありません。
基本は食事の工夫が必要になります。
動画の目次⇩
00:00動画のポイント
00:20皆さんへの質問
00:47血糖値スパイクなぜよくなのか
01:16血糖値スパイクを防ぐ方法
02:04参考資料の紹介
02:30今回の注意点
03:16血糖値上昇を緩やかにするお茶①
04:47血糖値上昇を緩やかにするお茶②
06:08血糖値上昇を緩やかにするお茶③
07:32血糖値上昇を緩やかにするお茶④
10:00血糖値上昇を緩やかにするお茶⑤
10:41血糖値上昇を緩やかにするお茶⑥
11:27血糖値上昇を緩やかにするお茶⑦
12:30看護師ざきが愛用するお茶(動画のテーマとは関係ありません)
12:51こやま園 丹波なた豆茶
13:41 お茶屋いちえ(長野県伊那市 オンラインショップより画像引用)
14:40GreenTea SEN (長野県茅野市 インスタグラムより画像引用)
慢性腎臓病の食事について⇩ 黒豆の腎臓病予防効果
腎臓病の悪化を防ぐ食べ物 https://youtu.be/SmwO7PENhKk
めかぶを食べると腎臓が強くなる https://youtu.be/9HqwmoOIGkw
腎臓に良い飲み物9選 https://youtu.be/HcN9ed0S-IQ
腎臓に良い食べ物10選 https://youtu.be/U9nqWvaq838
純玄米黒酢の腎不全予防効果 https://youtu.be/uS15xfbK7F4
腎不全リスクを大きく下げるタンパク質の選び方https://youtu.be/JpYqQW9GQa4
超加工食品と慢性腎臓病 https://youtu.be/NFlChVczDfY
ビオフェルミンと林檎酢の効果 https://youtu.be/iuzF5LF-pm4
コーヒー摂取で腎不全予防 https://youtu.be/_6dj2JxGLHs
ミトコンドリア機能と慢性腎臓病 https://youtu.be/nw2vq-sExlc
カリウム管理の新常識 https://youtu.be/oyPOu6SAakM
セブンイレブンのお勧め商品 https://youtu.be/F3qClTSEgc8
腎臓リハビチテーションの基礎編https://youtu.be/n_al9aikvxw
なた豆茶の腎臓保護効果 https://youtu.be/M5-sMAl1pzI
老化と腎機能低下の原因はリンにあった https://youtu.be/954s5YydXXw
亜鉛と慢性腎臓病 https://youtu.be/KA4IintQym0
腎臓がいい人だけやっている秘密 https://youtu.be/A3WP0-BDoeo
腎臓病に向いている水は軟水か硬水か https://youtu.be/XEba6ww-Kl4
腎臓病にお勧めな神食品3選 https://youtu.be/kJbLGMpBVSc
夏に注意したい腎機能低下 https://youtu.be/v6OSrAFqawc
食物繊維の腎臓を守るすごい効果 https://youtu.be/dEqwBl1kMqE
乳酸菌の腎臓を守るすごい効果 https://youtu.be/YtDPIkZW0fs
ビタミンDの腎臓を守るすごい効果 https://youtu.be/t38JehFlntk
慢性腎臓病にお勧めな蛋白質 https://youtu.be/s-DdZknMDcc
慢性腎臓病にお勧めな果物 https://youtu.be/zBXKwYZQTSU
腎臓を綺麗にする食べ物 https://youtu.be/RsTrjfjEyZU
フレイルを感じたら始めるべきこと
老化スピードを大きく変える「社会活動」への参加
【65歳・75歳・85歳 どうすれば年齢の壁を越えられるか】
現在、世界中で「高齢者」というと65歳以上ということになっています。
わが国も然りで、65~74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と呼んでいます。
この分類に医学的な根拠はありません。
「人生100年」などと言って、実際にも寿命が延びている現在、
65歳で高齢者は早すぎるとさえ言われています。
しかし、医者としての経験上、やはり65歳は1つの大きな区切りではないかと思います。
個人差はありますが、65歳を超えると老化の傾向がはっきりしてくるからです。
日本老年学会、日本老年医学会などの調査データを見ると、
歩行速度、握力などの運動機能、活動能力指標で見た生活機能など
多くの身体機能が、昔に比べて5歳以上は若返っています。
もはや昔の基準である「還暦」(60歳)の意味はあまりありません。
しかし、65歳は現代人にとっての大きな節目です。
なぜなら、平均寿命より重要な健康寿命は、
現在男性が72・68年、女性が75・38年だからです。
つまり、あと7~10年ほどしか健康でいられないのです。
よって、65歳の壁を乗り越え、その後の10年を健康で過ごすためには、
ただ、漫然と生きていてはいけません。
高齢者になると、なりやすい病気はある程度決まっています。
高血圧▽心筋梗塞▽不整脈▽心不全▽動脈硬化▽脳梗塞▽脳卒中▽認知症
▽糖尿病▽胃がん▽前立腺がん▽大腸がん▽肺がん▽肝臓がんなどです。
言うまでもありませんが、その多くが生活習慣病です。
「がん」も生活習慣病に含まれるという見方もあります。
つまり、これらの病気の前兆があれば、
生活習慣を見直すことで未然に防げる可能性があります。
自身の経験も含めて言うと、65歳前後で初めて息切れを意識しました。
走るとすぐに息が切れるのです。また、ちょっとした段差でつまずいたり、
片足立ちが長くできなくなったりするのです。これは明らかな運動機能の低下で、
最近の言葉で言うと「フレイル」(虚弱)です。
いまや「フレイル健診」も始まるなど、
65歳はフレイルを初めて意識する年齢と言っていいでしょう。
医療・健康業界は商魂たくましく、次々に新語を広めるなと感心しますが、
いちおう、フレイルには基準があります。
①体重減少(意図しない年間4・5キロまたは5%以上の体重減少)
②疲れやすい(なにをするのも面倒だと週に3~4日以上感じる)
③歩行速度の低下
④握力の低下
⑤身体活動量の低下
――の5つです。 このうち、②と③は65歳になれば必ず該当するでしょう。
では、フレイルを予防するにはどうするのか?
当たり前ですが、「バランスのいい食生活」「適度な運動」「十分な睡眠」、
そして「社会活動への参加」です。
私の場合、糖尿病なので食生活はとくに気をつけています。
運動はジムに通って積極的に筋トレをやるなどの必要はそれほどなく、
1日1万歩程度のウオーキングが目安です。
私は、「10、8、6の法則」を提唱しています。
10は睡眠で、十分に取る。8は食事で「腹八分」。
6が運動で、運動量は「若い頃の6割」がメドということです。
最近の老化の研究で最も注目されているのは、「社会活動」です。
ボランティア、地域活動、再就職などに参加していない人の老化スピードは、
している人に比べてはるかに早いのです。
よって、間違っても65歳で社会生活からリタイアなどしてはいけません。
なんらかの活動は絶対に続けるべきです。
■富家孝(ふけ・たかし) 医師、ジャーナリスト。1947年大阪府生まれ。
72年東京慈恵会医科大学卒業。病院経営、日本女子体育大学助教授、
新日本プロレスリングドクターなど経験。
『不要なクスリ 無用な手術』(講談社)ほか著書計67冊。










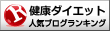

 </picture>
</picture>



