みなさん、ハローです。ホディです。
「きっかけは、フジテレビ!」
ということで、今日もフジテレビネタで唸ります。
「ライブドアVSフジテレビ メディアはどうなる?」を日曜日の静かな午後をつぶして見てしまいました・・・
裏では、センバツの東邦VS育英の熱戦が繰り広げられていたと言うのに・・・
残念!!!
正直な感想を言うと、時間の無駄でした。
事実、コメンテーターの話が退屈で途中寝てしまっていた時間もあります。
なぜ?
要は、テレビなどの既存メディアが生命線である既得権者のコメンテーターでは目新しい話はできない。
しかも、せっかく視聴者から意見をもらっても、キチンとフィードバックできないと意味ないですよね?
あの放送時間にいろいろな意見を紹介するなんて、そもそも不可能でしょう。。。
(フジテレビのホームページを探しても出てこなかった・・・)
これじゃ、インターネットとテレビの融合を急ぐべきと言う意見も良く分かります。
と・・・
今日はこのような話をしたいのではなくて、
「敵対的買収」への対策ばかりが先行して、本来の議論が疎かになっているんのではないか?
「会社は誰のものなのか?」「会社はどうあるべきなのか?」
を考えたいと思いました。
書生論で恐縮ですが、原点に立ちかえって。
「会社は誰のものなのか?」という議論をしても結論はないですが、
理想論で言えば、
経営者は株主利益(例えば株価)を最大にすることを目標とすべきだし、
上場している以上は現在の株価以上で買い手が現れた場合は、
株主自身が自分たちの社会的責任のもとで売却するかどうかを判断すべき。
なんでしょうが・・・
それにしても、敵対的買収の防止策だけが先走りすぎているような気がします。
もっと株式会社の適正なガバナンスや、経営者のレベルアップ、株式市場の成熟、
そして株主のレベルアップと株主の社会的責任のあり方の議論を行うべきと考えます。
※そもそも日本に株式会社の概念は定着しないと言ったら言いすぎ???
※先週からこんな事を考えていたら、ちょうど日経朝刊の経済教室に『会社支配を考える』ということで、連載がありましたので、その内容もキーワードだけピックアップして若杉教授と小幡教授のレポートを取り急ぎ参考までに入れておきます。
<会社支配を考える>
●若杉敬明 東京経済大学教授(株主価値追求が責任)
・株式会社は法人として人格が認められているため、株式会社自体に法的な所有者は存在しない
・株主が所有者であるというのは、法制度ではなく、経済的な実態である
・株主は自分で直接会社の経営はしないが、取締役を選任できるという意味でガバナンスを有している
・株主から企業を預かった経営者は、株主価値の増大を目指して経営を行う
(株主価値最大化経営)
・コンプライアンスのもとで、株主価値を追求することが企業の社会的責任である
・上記のような経営を実現するようにガバナンスを行使するのが株主の社会的責任である
・M&Aは株主のガバナンスが移動することにより、効率の悪い企業を生産性の高い企業に
変身させたり、新たに価値のある事業を生み出したりして価値の創造に貢献する
・株主のガバナンスが確立していないと、1980年代の米国のようにM&Aの仲介業者に
踊らされて、株主価値を生まないM&Aが行われることになる
●小幡績 慶應義塾大学助教授(資源配分機能の重視を)
・日本では、会社に対する貢献の対価としてお金を得る点では同じなのに、なぜ、知恵と
労働を提供した従業員は賞賛され、資金を提供した投資家は感謝されないのだろうか
・上記の理由は日本の平等主義に由来すると考える
・従業員の能力、労働力は移転することができないから、従業員ごとにある程度の差はつくが、
能力と時間には限界があるからその差は無限には広がらない
・一方、富は移転可能であるため、偏在するようになり、その偏在が固定化し際限なく拡大する
可能性がある
・お金という財の力を独占するように見える資本家、投資家は世の中の攻撃を受け、その結果、
「会社は誰のものか」という問いが金持ちが多い株主に対して投げかけられ、
「会社は株主のものではない」という回答がなされるのである
・株式会社が上場するということは、その株式に対して市場で常に値段がつくことであり、
一番高い値段を払った人が株主になるというメカニズムを選択することである
・つまり、誰が株主になってもかまわない、美術品のオークションと一緒で、最も価値を認めて
くれる人が所有権を得るという仕組みである
・資金提供者が意思決定権を持つのは、資本が人的資源に比べて低いコストで企業間を移動し、
各企業の価値増加機会について中立的に判断できるからである
・「会社は誰のものか」という問いは、この問い自体が誤りであり、会社は誰のものでもなく、
有機体でもない。会社はビジネスを行う上で便利で役立つ箱である
「きっかけは、フジテレビ!」
ということで、今日もフジテレビネタで唸ります。
「ライブドアVSフジテレビ メディアはどうなる?」を日曜日の静かな午後をつぶして見てしまいました・・・
裏では、センバツの東邦VS育英の熱戦が繰り広げられていたと言うのに・・・
残念!!!
正直な感想を言うと、時間の無駄でした。
事実、コメンテーターの話が退屈で途中寝てしまっていた時間もあります。
なぜ?
要は、テレビなどの既存メディアが生命線である既得権者のコメンテーターでは目新しい話はできない。
しかも、せっかく視聴者から意見をもらっても、キチンとフィードバックできないと意味ないですよね?
あの放送時間にいろいろな意見を紹介するなんて、そもそも不可能でしょう。。。
(フジテレビのホームページを探しても出てこなかった・・・)
これじゃ、インターネットとテレビの融合を急ぐべきと言う意見も良く分かります。
と・・・
今日はこのような話をしたいのではなくて、
「敵対的買収」への対策ばかりが先行して、本来の議論が疎かになっているんのではないか?
「会社は誰のものなのか?」「会社はどうあるべきなのか?」
を考えたいと思いました。
書生論で恐縮ですが、原点に立ちかえって。
「会社は誰のものなのか?」という議論をしても結論はないですが、
理想論で言えば、
経営者は株主利益(例えば株価)を最大にすることを目標とすべきだし、
上場している以上は現在の株価以上で買い手が現れた場合は、
株主自身が自分たちの社会的責任のもとで売却するかどうかを判断すべき。
なんでしょうが・・・
それにしても、敵対的買収の防止策だけが先走りすぎているような気がします。
もっと株式会社の適正なガバナンスや、経営者のレベルアップ、株式市場の成熟、
そして株主のレベルアップと株主の社会的責任のあり方の議論を行うべきと考えます。
※そもそも日本に株式会社の概念は定着しないと言ったら言いすぎ???
※先週からこんな事を考えていたら、ちょうど日経朝刊の経済教室に『会社支配を考える』ということで、連載がありましたので、その内容もキーワードだけピックアップして若杉教授と小幡教授のレポートを取り急ぎ参考までに入れておきます。
<会社支配を考える>
●若杉敬明 東京経済大学教授(株主価値追求が責任)
・株式会社は法人として人格が認められているため、株式会社自体に法的な所有者は存在しない
・株主が所有者であるというのは、法制度ではなく、経済的な実態である
・株主は自分で直接会社の経営はしないが、取締役を選任できるという意味でガバナンスを有している
・株主から企業を預かった経営者は、株主価値の増大を目指して経営を行う
(株主価値最大化経営)
・コンプライアンスのもとで、株主価値を追求することが企業の社会的責任である
・上記のような経営を実現するようにガバナンスを行使するのが株主の社会的責任である
・M&Aは株主のガバナンスが移動することにより、効率の悪い企業を生産性の高い企業に
変身させたり、新たに価値のある事業を生み出したりして価値の創造に貢献する
・株主のガバナンスが確立していないと、1980年代の米国のようにM&Aの仲介業者に
踊らされて、株主価値を生まないM&Aが行われることになる
●小幡績 慶應義塾大学助教授(資源配分機能の重視を)
・日本では、会社に対する貢献の対価としてお金を得る点では同じなのに、なぜ、知恵と
労働を提供した従業員は賞賛され、資金を提供した投資家は感謝されないのだろうか
・上記の理由は日本の平等主義に由来すると考える
・従業員の能力、労働力は移転することができないから、従業員ごとにある程度の差はつくが、
能力と時間には限界があるからその差は無限には広がらない
・一方、富は移転可能であるため、偏在するようになり、その偏在が固定化し際限なく拡大する
可能性がある
・お金という財の力を独占するように見える資本家、投資家は世の中の攻撃を受け、その結果、
「会社は誰のものか」という問いが金持ちが多い株主に対して投げかけられ、
「会社は株主のものではない」という回答がなされるのである
・株式会社が上場するということは、その株式に対して市場で常に値段がつくことであり、
一番高い値段を払った人が株主になるというメカニズムを選択することである
・つまり、誰が株主になってもかまわない、美術品のオークションと一緒で、最も価値を認めて
くれる人が所有権を得るという仕組みである
・資金提供者が意思決定権を持つのは、資本が人的資源に比べて低いコストで企業間を移動し、
各企業の価値増加機会について中立的に判断できるからである
・「会社は誰のものか」という問いは、この問い自体が誤りであり、会社は誰のものでもなく、
有機体でもない。会社はビジネスを行う上で便利で役立つ箱である










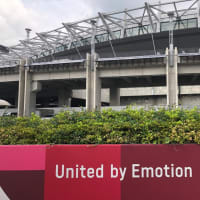















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます