立野城
たちのじょう
| 城名 | 立野城 |
| 住所 |
松阪市立野町
|
| 築城年 | 室町時代 |
| 築城者 | 水谷刑部少輔 |
| 形式 | 山城 |
| 遺構 | |
| 規模 | 90m×110m(70m×130m 諸説あるが城は消滅して分からない) |
| 城主 | 水谷刑部少輔 |
| 標高 | 130m |
| 比高 | 90m |
| 歴史 | 北畠氏外様の沢・秋山氏、譜代の水谷・鳥屋尾氏の北畠四家老の一人。大河内城の出城的存在。谷の入口を守る位置にある。 |
| 経緯 | 茶臼山本陣跡というのは、立野城(水谷刑部少輔。松尾立野城主・親織田派)を織田軍が大河内城攻撃に使ったので付いた名前であるとされるが、茶臼山本陣跡と立野城が同じ場所を指しているのかは諸説ある。 |
| 書籍 | 三重の中世城館 日本城郭全集 |
| 標高138mの急峻な丘陵頂部にあり、大河内城跡は阪内川を挟んで指呼の間にある。城は東西70m、南北130mの範囲内にある南北2つの台状地からなり、その周囲には平坦地を巡らす。本城については、大河内合戦時の信長本陣跡とする説、城主を水谷刑部少輔とする説などがある。 | |
| 環境 | 立野城がある山は東南側から砂利取りのため削られ元の姿はない。吾輩の記憶では北からの風景で山頂がひとつ無くなってしまった、と思っている。 |
| 勢陽五鈴遺響 | 城主水谷刑部少輔住まいセリ、とある。 |
| 考察 | 吾輩の考え。 |
| 立野城があったのは仮に東山(茶臼山?)とし、織田信長が陣を張ったのは見晴らしの効く仮称・西山(桂瀬山?)と仮定する。二つは尾根で結ばれており行き来はできた。日中は距離的に近い桂瀬山で大河内城を見守り、夜は安全を考えて背後の高い位置にある立野城で寝泊まりした。動きやすい西山に輓場跡や信長の腰掛石があり、その位置が裏付けになっているように思われる。多数の兵はこの二つの山には入りきらない。おそらく周辺の平地に柵などを設けて1ケ月余りを過ごしたのではないだろうか。 | |
| 水谷刑部は立野城を明け渡して事前に大河内城に篭った。そして1ケ月の間には城内で北畠具教に和解の説得をしたと考えられる。 | |
| 地図 | |










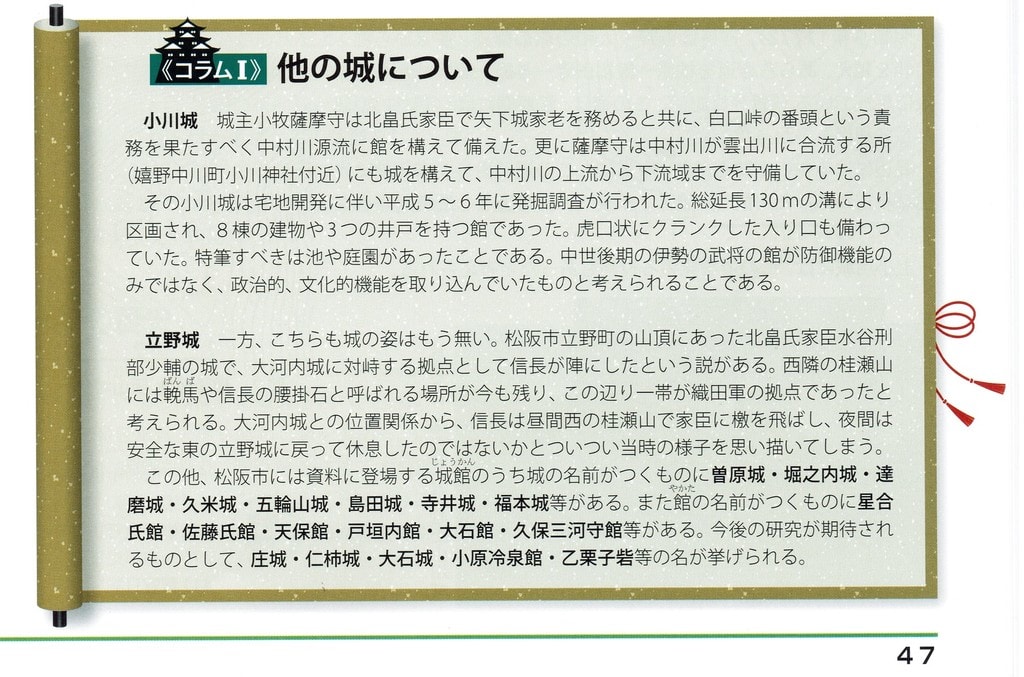

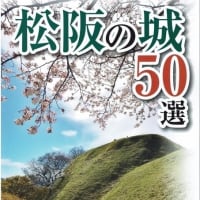

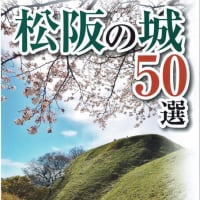
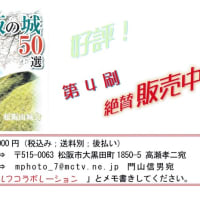




織田信雄について奈良県宇陀市に移り住んだのでしょうか?
文献が残っていれば知りたいものです。
今後も楽しみに拝読いたします。ありがとうございました。