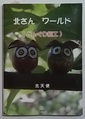今日会社で新年の神社での祓いの案内が届いたんです^^。
そこで調べてみたんです^^。
「喪に服す」と言いますが、正確には「忌」の期間と「喪」の期間は異なります。
忌中とは、神道の「穢れ(ケガレ),気枯れ である死を忌む期間」という考え方から、
忌中時(五十日)は出仕(仕事)を控え、殺生をせず、髭や髪を剃らず、神社に参拝しない、としています。
仏教では四十九日法要が終るまでを忌中とされています。
一方喪中とは、「死者を偲ぶ期間」であるとされ、忌中とは別の考え方になるのです。
日本では、喪中の規定に関する法律は奈良時代の「養老律令(ようろうりつりょう)」にはすでに見られ、
江戸時代になると「服忌令(ぶっきりょう)」という法律によって喪中の規定がはっきりなされていて、
これらによると父母の喪は12か月~13か月であると制定されています。
明治7年の太政官布告による服忌令では13か月、明治42年の皇室服喪令では12か月と、
こちらもほぼ同様の期間が決められています。
法律があった何て知りませんでした^^;
服喪期間について、あくまで参考程度になりますが
一般的には下記のとおりであると認識されています。
父母、養父母、義父母
…12か月~13か月
子供
…3カ月~6か月
兄弟・姉妹
…30日~3カ月
祖父母
…3カ月~6か月
祖祖父母、叔父叔母、伯父伯母
…喪中としない
それで,神社にはお参りをしてはいけないんですが,お寺さんの方は大丈夫なんですって^^。
神社のお札や破魔矢はその時のもなので,お受けしてくるのは良いんだそうです^^。
でも前のものを取り外したりすることは駄目なんですって^^;
本来は半紙で覆っておくんだそうです^^;
それで忌明けに取り換えるんだそうです^^。
お寺さんの方は葬式も行いますし,法事も行います^^。
穢れと言う概念ではないんですね^^。
お年玉も駄目なんですって^^;
一応お祝いの部類に入るのでね^^;
だからお年玉では無くて「おこづかい」と言う名目にするんですって^^。
お正月にはお墓参りに行ってご先祖様にご挨拶と言うのが良いみたいです^^。
来年は七福神めぐりも出来ないのでお墓参りに行って参ります^^。
そこで調べてみたんです^^。
「喪に服す」と言いますが、正確には「忌」の期間と「喪」の期間は異なります。
忌中とは、神道の「穢れ(ケガレ),気枯れ である死を忌む期間」という考え方から、
忌中時(五十日)は出仕(仕事)を控え、殺生をせず、髭や髪を剃らず、神社に参拝しない、としています。
仏教では四十九日法要が終るまでを忌中とされています。
一方喪中とは、「死者を偲ぶ期間」であるとされ、忌中とは別の考え方になるのです。
日本では、喪中の規定に関する法律は奈良時代の「養老律令(ようろうりつりょう)」にはすでに見られ、
江戸時代になると「服忌令(ぶっきりょう)」という法律によって喪中の規定がはっきりなされていて、
これらによると父母の喪は12か月~13か月であると制定されています。
明治7年の太政官布告による服忌令では13か月、明治42年の皇室服喪令では12か月と、
こちらもほぼ同様の期間が決められています。
法律があった何て知りませんでした^^;
服喪期間について、あくまで参考程度になりますが
一般的には下記のとおりであると認識されています。
父母、養父母、義父母
…12か月~13か月
子供
…3カ月~6か月
兄弟・姉妹
…30日~3カ月
祖父母
…3カ月~6か月
祖祖父母、叔父叔母、伯父伯母
…喪中としない
それで,神社にはお参りをしてはいけないんですが,お寺さんの方は大丈夫なんですって^^。
神社のお札や破魔矢はその時のもなので,お受けしてくるのは良いんだそうです^^。
でも前のものを取り外したりすることは駄目なんですって^^;
本来は半紙で覆っておくんだそうです^^;
それで忌明けに取り換えるんだそうです^^。
お寺さんの方は葬式も行いますし,法事も行います^^。
穢れと言う概念ではないんですね^^。
お年玉も駄目なんですって^^;
一応お祝いの部類に入るのでね^^;
だからお年玉では無くて「おこづかい」と言う名目にするんですって^^。
お正月にはお墓参りに行ってご先祖様にご挨拶と言うのが良いみたいです^^。
来年は七福神めぐりも出来ないのでお墓参りに行って参ります^^。