SFCの飯盛義徳(いさがいよしのり)さんの『地域づくりのプラットフォーム-つながりを生み創発をうむ仕組みづくり』2015年を拝見しました。
飯盛さんとは、Glocomの集まりでご一緒したことがありました。丸田一・国領二郎・公文俊平編著『地域情報化 認識と設計』2006年という本にその時のものがまとめられています。
飯盛さんは、その時も、ご自身が佐賀で手がけられている「鳳雛塾」と富山で生まれこの本を書いている頃に連携することになった「インターネット市民塾」を取り上げておられました。
当時、私は、地域で活動をしていなかったので、鳳雛塾や市民塾など、実際に地域で活動されながら、それを理論化しようとされておられることに、凄いなぁと思い、気後れしていました。
私は、この本では、パソコン通信時代の優であった大分県の「コアラ」を取り上げています。この勉強会では、パソコン通信の時代とインターネットになってからでは、同じ地域情報化といっても性格が違うというのが若手の意見で、私は、「どこがどう違うのか、インターネットが新しい道具であるというだけではないのか」と食い下がりましたが、年寄には分からないヨ的な反応で、結局、最後まで良く分かりませんでした。
飯盛さんの新著を拝見し、頭が少し刺激されました。ここ数年、自分も地域活動をし始めたので、そこで経験したことを含め、少し整理したい気持ちになりました。
++++++++++++++++++
1.未来(あったらいいな)から考える
自治体等の長期計画は、概して、現在の状況からそれを10年後、20年後に伸ばす形(トレンド)で作られます。
そうすると、どうしても、現状に左右されてしまいます。予算がないのでムリだ、道路は国や都の計画なのでムリだ・・というようになります。
あるいは、きれいな言葉をならべますが、それを実行できる裏付けや具体的な施策がなく、絵に描いた餅のようになります。
これまでの市民活動も、現在の問題点を解決するという傾向が強いです。
たとえば、買物難民が増えているので、代わりに買い出しに行ってあげる、あるいは、都市部に週何回か巡回バスを走らせる。
商店街が衰退しているので、イベントを実施して客を呼ぼう。
ある特定の緑地を守ろうといった活動などなどです。
これらは、大事なことで、具体的な成果をあげていたり、無償の努力に頭が下がるケースもあります。
しかし、時には、具体的な解決策がなく、ただ「反対」だけを叫んで、多くの市民から浮いてしまうことがあります。
あるいは、イベントは成功して神輿を担いだ人は、当面満足したけれど、商店街にその時客が増えただけという、がっくりする結果になったりします。
スマ大のスタンスは、「あったらいいな」と思う未来の姿を描き、それを実現するには、どうしたらよいかを考えるというものです。
現実と未来の姿の間には、大きなギャップがあるのが普通です。そのギャップをどのように埋めていったら良いかを考えます。並の考えでは、なかなか実現できない場合、そこにイノベーティブな発想が生まれることを期待します。
また、「未来の姿」に共鳴した他の人がその姿に沿った動きを自発的に行うことを誘引する場合もあります。
こうした考え方を私は、三重県名張市国津地区の「アララギプラン」を策定した知人から教えて頂きました。「アララギプラン」は、名張市は、大阪のベットタウンとして、駅近くには、人口が増えていたので、後背地にあたる国津地区は、都市部に住む人たちにとっての「トトロの郷」になったらいいなというイメージを示したものです。その「プラン」を読んだ住民がそれぞれの立場でやれることをやっていくという形で「ヴィジョン」を「形」にしてきました。
スマ大副代表の鈴木さんは、当時、「スープストック」を社内ベンチャーで立ち上げた人が社内でビジネスプランを説明するにあたって、スープストックが出来た時の人々のライフスタイルを描くという方法を取って、賛同を得たという話が好きでした。
「夢を描き」それを読んだ人に、「あぁ、そんな風になったらどんなに良いだろう」と共感を持ってもらい、夢の実現に一緒に向かってくれるようにするわけです。
しかし、残念ながら、まだスマ大は、「あったらいいな」のビジョンを描ききれずにいます。日々迷走しているのは、そのせいだと思います。
私個人としては、「市民力を高める」というのを目標にしています。「市民力を高める」というのは、「自分たちのまちを良くするのは、自分たちだと思い、行動する人が増えること」です。
自分たちのまちをこのようにしたい、自分で出来ることは、ここまでで、ここは自分たちでやる。もし自分たちで出来ないなら、行政、企業、他の方々と連携するといったイメージです。
私は、三鷹市で、「市民側が長期計画を策定し、それを行政に提出した」のを大変羨ましく思っています。三鷹市の例は、長い年月かけて市長や行政がいろいろと仕掛けて実ったものですから、それを市民の側から仕掛けることが本当に出来るかどうか。三鷹市だって、計画づくりに関わった人は、市民全体からみれば大きな数ではないと思いますが、ともかくそうした実績ができているわけです。
先日読んだ原 武史『レッドアローとスターハウス-もうひとつの戦後史』では、ひばりが丘団地ができたての頃には、いろいろな不便があり、それを自治会が西武鉄道や行政に働きかけて解決、実現していった経緯が書かれています。
足元に問題があれば、市民は動く、動かざるをえないのだなぁと思いました。
逆に、今、市民の人たちが動かないのは、おそらく、「そこそこ満足している」からなのだと思います。
これまでは、国や地方自治体が市民のサーバントとして(本当はそうだと思います:税金でサービス提供を委託しているわけですから)、そこそこのことをやってきてくれていたので、ほぼ「お任せ」でこれたのです。
面倒くさくなくて、幸せな時代だったと言えるのかもしれません。
でも、実際、何か問題が起きた時に、一つの解にまとめあげることが出来るものなのか。Aさんに良いことがBさんに良いこととは限らないという問題を、市民参加でどのように作り上げていけるのか、正直まだ分かっていません。
そうした調整を誰がやれるのか、解は、一つであっても、Aさんも納得し、Bさんも納得するような解が見つけられるのか?
私個人の夢は、「市民力を高める」を目標にしていますが、スマ大に参加しているそれぞれがどう思っているのかは、実は真面目に議論しつくしてはいません。
以前のイベントのタイトルを「10年後、私たちがもっとワクワクするまちについて、話してみよう!」としました。おそらく、「10年後、私たちがもっとワクワクするまちを作ろう!」といった辺りが目標かと思います。
最新の画像[もっと見る]










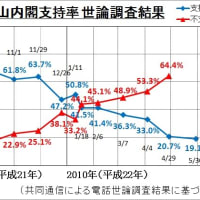
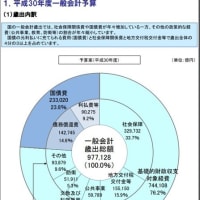
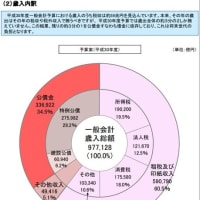
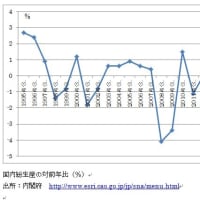
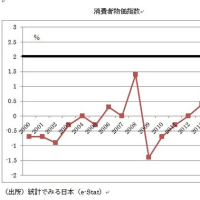



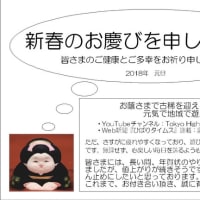


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます