知人に勧められて、タイトルの本を読んだ。
私は、現在の西東京市に1947年に生まれてからずっと住んでいる。西武新宿線の田無駅近くに家がある。
タイトルの「レッドアロー」は、西武池袋線と西武新宿線の特急の名称であるし、「スターハウス」は、日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構:UR都市機構)が立てた大規模団地ひばりが丘団地にある当時人気が高かったシンボル的な建物の名前である。
つまり、この本は、西武線とその沿線に建てられた大規模団地を主な題材として「もうひとつの戦後史」を語っている。
著者の原さんは、1962年生まれだから私より15歳くらい若い人で、3歳からひばりが丘団地に住み、久米川団地、滝山団地と公団住宅を転々とし、75年に横浜市緑区(現在の青葉区)に引っ越すまでの13年間を西武沿線で過ごしたという。
私は、原さんの本を読むのは初めてだが、日本政治思想史がご専門の原さんは、海外の研究ばかりを重視したり、日本を抽象的にひとつにまとめてみるのではなく、マルクスの「下部構造」のように人々が何気なく選択した住居や沿線などの空間が文化や政治意識の形成に大きな影響を及ぼしているのではないかと考える人らしい。
タイトルから、もうちょっと気楽な本かと思ったら、予想以上に重たい本であった。自分もこの沿線に住んでいるのに、全く知らないことばかりが書かれていた。清瀬のハンセン病患者や結核患者向けの病院の話や東久留米の自由学園のことなどは、情報として面白かった。原さんの分析で面白かったのは;
1.同じまちにあるひばりが丘団地では、箱は出来たけれど保育園が足りない、電車の本数が足りないなど、住むのに問題が山積みであったことから、自治会が自然発生的に生まれ、いろいろな問題を自主的に解決しようとしていたこと、
2.アメリカにあこがれ、天皇を敬っていた堤康二郎の息がかかった沿線であるのに、彼は、そこに住宅を建てることに意欲的ではなく、もっぱら公団等によって大規模団地が作られ、それは、彼が嫌ったソ連(共産圏)の姿に近似していたこと、
3.ソ連では、団地に住んでいたのは、主に労働者であったが、日本では、新中間層であり、インテリ層であったこと。驚くほど後に著名な人たちが団地に住んでおり、特に、共産党が自治会などの動きを活用しつつ票を伸ばしていったこと、
同じまちに住んでいた自分としては、お母さんたちを中心に、自治会活動が活発であったことに驚いた。
また、共産党がそんなに伸びていた時期があるなんて知らなかった。
私が意識している限りでは、田無市は、社会党→民主党の力が強く、ずっと革新首長だったと記憶している。
私自身は、旧中島飛行機の社宅だったところに住んでおり、農家や商家が地元の人と考えると、後者が保守的で、社宅の人たちがどちらかというと革新的だったように思う。しかし、それでも、私が掛りつけの指田医院のおじいさんは、確か町長でもあったが、社会党だったように思う。保谷は、地主が多く、保守的だったと記憶する。
また、原さんの本には、少ししか書かれていないが、私の記憶では、私の小学校時代以降、公明党(創価学会)の組織化がものすごく進んだ記憶がある。15歳年下の原さんの周辺では、それほどではなかったのだろうか。
滝山団地がコミューン化し、それが小学校の教育にまで影響を与えていたというのには、驚く。
今、ひばりが丘団地は、リニューアルが進み、高層化して余った土地には、公団ではない別のディベロッパーがいくつかマンションを建てるらしい。
空いた土地には、老人ホームや学童保育も新しく建てられた。一方で、商店街は2つくらい解散したらしい。
我が家の周りは、農家の相続問題で、それまでのきつね山たぬき山がどんどん宅地化されて、すぐに売れてしまう。
中島飛行機の社宅(二軒長屋)だった私の住宅は、私の親たちが皆亡くなって、空き家が増え、でもすぐに転売されて別の人が入居してくる。
原さんが、トクヴィルが理想とした自治活動が盛んな地域に最も近いのは国立だろうと言っている。
所得水準が中央線沿線よりは低い西武沿線、かつまだまだ新しい居住者が増えている地域だが、新しい自治活動のうねりを作り出すことはできるだろうか。
私は、現在の西東京市に1947年に生まれてからずっと住んでいる。西武新宿線の田無駅近くに家がある。
タイトルの「レッドアロー」は、西武池袋線と西武新宿線の特急の名称であるし、「スターハウス」は、日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構:UR都市機構)が立てた大規模団地ひばりが丘団地にある当時人気が高かったシンボル的な建物の名前である。
つまり、この本は、西武線とその沿線に建てられた大規模団地を主な題材として「もうひとつの戦後史」を語っている。
著者の原さんは、1962年生まれだから私より15歳くらい若い人で、3歳からひばりが丘団地に住み、久米川団地、滝山団地と公団住宅を転々とし、75年に横浜市緑区(現在の青葉区)に引っ越すまでの13年間を西武沿線で過ごしたという。
私は、原さんの本を読むのは初めてだが、日本政治思想史がご専門の原さんは、海外の研究ばかりを重視したり、日本を抽象的にひとつにまとめてみるのではなく、マルクスの「下部構造」のように人々が何気なく選択した住居や沿線などの空間が文化や政治意識の形成に大きな影響を及ぼしているのではないかと考える人らしい。
タイトルから、もうちょっと気楽な本かと思ったら、予想以上に重たい本であった。自分もこの沿線に住んでいるのに、全く知らないことばかりが書かれていた。清瀬のハンセン病患者や結核患者向けの病院の話や東久留米の自由学園のことなどは、情報として面白かった。原さんの分析で面白かったのは;
1.同じまちにあるひばりが丘団地では、箱は出来たけれど保育園が足りない、電車の本数が足りないなど、住むのに問題が山積みであったことから、自治会が自然発生的に生まれ、いろいろな問題を自主的に解決しようとしていたこと、
2.アメリカにあこがれ、天皇を敬っていた堤康二郎の息がかかった沿線であるのに、彼は、そこに住宅を建てることに意欲的ではなく、もっぱら公団等によって大規模団地が作られ、それは、彼が嫌ったソ連(共産圏)の姿に近似していたこと、
3.ソ連では、団地に住んでいたのは、主に労働者であったが、日本では、新中間層であり、インテリ層であったこと。驚くほど後に著名な人たちが団地に住んでおり、特に、共産党が自治会などの動きを活用しつつ票を伸ばしていったこと、
同じまちに住んでいた自分としては、お母さんたちを中心に、自治会活動が活発であったことに驚いた。
また、共産党がそんなに伸びていた時期があるなんて知らなかった。
私が意識している限りでは、田無市は、社会党→民主党の力が強く、ずっと革新首長だったと記憶している。
私自身は、旧中島飛行機の社宅だったところに住んでおり、農家や商家が地元の人と考えると、後者が保守的で、社宅の人たちがどちらかというと革新的だったように思う。しかし、それでも、私が掛りつけの指田医院のおじいさんは、確か町長でもあったが、社会党だったように思う。保谷は、地主が多く、保守的だったと記憶する。
また、原さんの本には、少ししか書かれていないが、私の記憶では、私の小学校時代以降、公明党(創価学会)の組織化がものすごく進んだ記憶がある。15歳年下の原さんの周辺では、それほどではなかったのだろうか。
滝山団地がコミューン化し、それが小学校の教育にまで影響を与えていたというのには、驚く。
今、ひばりが丘団地は、リニューアルが進み、高層化して余った土地には、公団ではない別のディベロッパーがいくつかマンションを建てるらしい。
空いた土地には、老人ホームや学童保育も新しく建てられた。一方で、商店街は2つくらい解散したらしい。
我が家の周りは、農家の相続問題で、それまでのきつね山たぬき山がどんどん宅地化されて、すぐに売れてしまう。
中島飛行機の社宅(二軒長屋)だった私の住宅は、私の親たちが皆亡くなって、空き家が増え、でもすぐに転売されて別の人が入居してくる。
原さんが、トクヴィルが理想とした自治活動が盛んな地域に最も近いのは国立だろうと言っている。
所得水準が中央線沿線よりは低い西武沿線、かつまだまだ新しい居住者が増えている地域だが、新しい自治活動のうねりを作り出すことはできるだろうか。










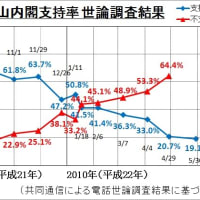
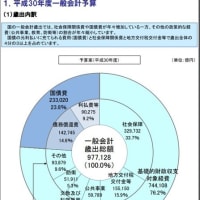
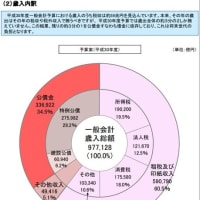
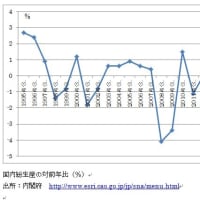
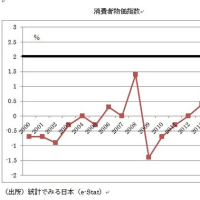



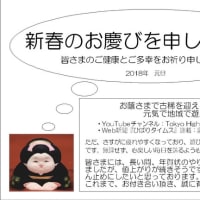


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます