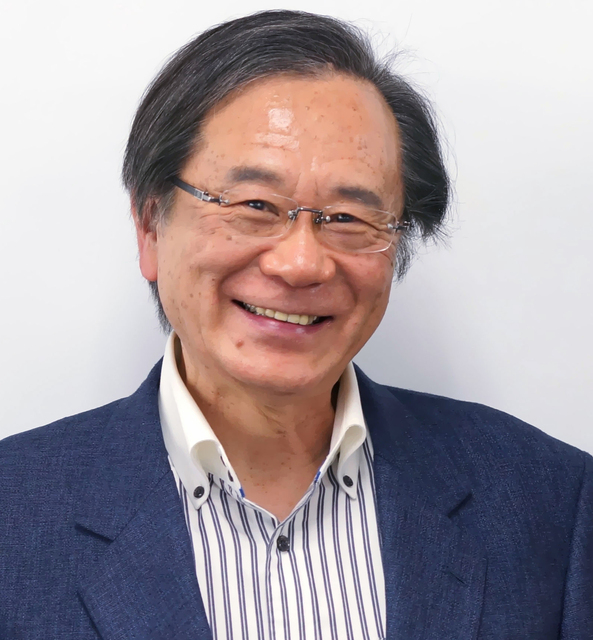〔PHOTO〕gettyimages
〔PHOTO〕gettyimages
12月23日に81歳を迎える今上天皇は、かねてよりご自身の陵墓案など「その日」を視野に入れた活動をされてきた。だが皇族の身分を規定する『皇室典範』には、代替わりについての大きな穴があった—。
「皇太弟」に「皇太甥」
「えっ、そうなんですか?皇太子という存在は必ずいるものだと思ってました。皇太子がいない状況というのは、神話とかそのあとの時代ぐらいなのかと」(漫画家・倉田真由美氏)
おそらく大多数の人が倉田氏と同じ思いを抱くだろう。今上天皇が代替わりし、現皇太子の浩宮徳仁親王が皇位に就いたとき、皇室には「次の天皇(皇嗣)」たる権利を持つ「皇太子」がいなくなってしまうのだ。
そんな話があるか、秋篠宮文仁親王も悠仁親王もいらっしゃるではないかという反論が返ってくるだろう。確かに皇位継承権を持つ皇族男子は存在する。けれども、お二人は「皇太子」にはなれない。『皇室典範』が定めている皇太子の条件に合致しないからだ。
皇室典範が定める皇太子の定義にはこうある。
〈第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という〉
ここに出てくる「皇子」とは、天皇の息子を意味する。だから現在、皇太子の地位には、今上天皇の長子である浩宮がついている。
では、浩宮が即位して天皇となった場合はどうなるのか。浩宮には娘(愛子内親王)はいるが、息子(皇子)はいない。皇室典範第一条には〈皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する〉とあるので、息子がいない以上、「男系男子」の孫(皇太孫)も当然いない。
「現皇太子が即位した時点で、皇位第一継承者は弟宮の秋篠宮文仁親王になります。ただ、秋篠宮は『皇嗣たる皇子』ではないから、皇太子にはなりません。歴史上の表記でいえば、〝皇太弟〟ということになる。悠仁親王はどうか。たとえば、父である秋篠宮が兄の天皇より先に亡くなった場合、悠仁親王が皇位第一継承者になるわけですが、悠仁親王は皇太孫ではなく、天皇の甥なので、やはり皇太子にはなりません」(ノンフィクション作家・保阪正康氏)
皇太子不在を、それほど問題にする必要はないという意見もある。近現代史研究家の浅見雅男氏は言う。
「歴代の天皇家において、皇太子が空位だったことは決して珍しいことではありません。皇室典範が穴だらけなのはそのとおりですが、むしろそれによって皇位継承は、昔から融通無碍におこなわれてきた。世継ぎの方に対して、皇太子という呼び方を絶対にしなければいけないという決まり自体がないのです。もし、浩宮在位中に悠仁親王が皇位継承第一位になった場合は、『皇太甥』とするのが、一番自然ということになるでしょう」
今の世に皇太甥と書いて「こうたいせい」と読める人がはたしてどれだけいるだろうか—。
「東宮職」もなくなる
皇室ジャーナリストの山下晋司氏が語る。
「皇太子がいなくなれば、宮内庁法第六条によって〈皇太子に関する事務をつかさどる〉とされる『東宮職』がなくなります。東宮職は、現在約50名。ほかに料理人や運転手などの管理部の職員もあわせると六十数名の居場所がなくなります。解雇できませんので人事異動で対応するしかありませんが、それだけの人数を異動させるとなると大変です。宮内庁には頭の痛い問題でしょう」
皇太子としての公務を誰が担うのか、という問題も、当然出てくる。
「皇太子殿下が即位されれば、皇位継承順位第一位の秋篠宮殿下が、今の皇太子殿下の職務を引き継がれるでしょう。そうすると、宮家皇族としてこれまで秋篠宮殿下がやってこられた公務はどうなるのかという問題が出てきます。
外国交際の面でも、悩ましい問題が生まれるでしょう。事実上の皇太子ではあるが、法的には一宮家の親王という場合、外国に対してクラウンプリンス(皇太子)という言葉を使うのか、それともただのプリンスとするのか。当然、次期皇位継承者ということでクラウンプリンスとして活動していただいたほうが日本の国益にはなるでしょう。国内と海外で使い分けをするという可能性もあります」(前出・山下氏)
東宮家と宮家では、公的な活動の内容も大きく違ってくる。宮家皇族は公益法人など各種団体の名誉職に就いて活動できるが、皇太子・皇太子妃は、天皇・皇后と一緒で、原則的には団体の名誉総裁には就かない。秋篠宮は、現在、世界自然保護基金ジャパン名誉総裁や日蘭協会名誉総裁など多くの名誉職に就いているが、皇太子の職務を引き継いだ場合、これら名誉職や、その活動はどうするのかもはっきりしない。実際問題として、宮家皇族としての公務と皇太子の公務を兼任するというのは難しいだろう。
もっと大きな問題もある。「生活費」の問題だ。
皇族には「内廷皇族」(皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃など)と、内廷から独立して一家をかまえている「宮家皇族」の2種がある。ちなみに特別な存在である天皇は、内廷皇族にも宮家皇族にも含まれない。
国が支出する費用は、内廷皇族と宮家皇族ではまるで違う。天皇および内廷皇族に支出される「内廷費」は、平成26年度は年額3億2400万円。現在の状態のまま天皇が代替わりすると仮定すれば、内廷皇族は美智子皇太后、雅子皇后、愛子内親王の3方。天皇を加えて4方の世帯ということになる。仮に愛子内親王が結婚して皇籍を離脱し、3方になったとしても、金額は同じだ。
他方、宮家皇族に支出される「皇族費」は、親王で3050万円、親王妃がその半額というように、頭数ごとに皇室経済法で定められているが、内廷費と比べると極端に少ない。
秋篠宮、あるいは悠仁親王が、事実上、皇太子の役割を担う場合も、現行法では内廷費の対象にはならないので、すべて皇族費でやりくりしなければならないという事態になるのだ。
内廷費と皇族費は、いわば皇室のプライベートのお金だが、それとは別に、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるための「宮廷費」というものがある。宮内庁が経理を担当する公金で、平成26年度の予算は55億6304万円。この宮廷費も、支出内容によっては、内廷皇族は使うことができる。たとえば、愛子内親王の学費・教育費は、宮廷費から支出されている。
「将来の天皇なのだから、悠仁さまの学費もオモテの金である宮廷費から出しましょうという話があったんです。でも、これは実現せず、悠仁さまの学費は、従来どおり秋篠宮家の皇族費から出されたと聞いています」(宮内庁関係者)
「次の天皇=皇太子」の違和感
このように、皇太子の不在により多くの問題が噴出してくる。そもそもなぜこんなことになっているのか。
「今の皇室典範、皇室経済法という法律も、宮内庁という組織も、皇位は親子継承しか前提にしていない。だからこんな問題が生じてきたのです。確かに今までは親子継承が6代も続いてきた。しかし、そのほうが日本の歴史上から見れば珍しいのです」(前出・保阪氏)
愛子内親王を皇太子とすれば、これらの問題は回避できる。けれども、この方法は無理だろうと言うのは、宮内庁担当記者だ。
「愛子さまを皇太子にするということは、『女系・女帝』を容認するということです。でも、これは国論を二分しかねない大変革で、宮内庁はもちろん、政府も手をつけたくないでしょう」
では、どうすればいいのか。皇室典範にある皇太子の定義を変えるという案が、宮内庁でひそかに検討されているという。
「現行の第八条の条文を、『皇位継承順位第一位の皇族を皇太子という』に改正する方法があります。そうすれば、皇太子殿下が即位された時点で秋篠宮殿下は皇太子となります。皇太孫に関する部分を削除する必要はありますが、この皇太子の定義を変えるだけで、内廷費・皇族費のことや東宮職のことなどの問題は解決します」(前出・山下氏)
だがそれでは、従来「天皇の息子」だったはずの皇太子に、「天皇の弟」がなっているという国民の違和感はぬぐい難い。
宮内庁ははたしてどう考えているのか。「代替わりの際に皇太子に当たる皇族がいなくなることについての見解」を質すと、以下のような回答があった。
「(代替わりとなった場合の秋篠宮の呼び名として)現在、『皇太弟』という制度はありません。
(将来の対策について)将来的に生じうる様々なケースを想定し、研究しておくことは有益であると考えております」
前出・浅見氏は言う。
「皇室典範第三条には〈皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる〉とあります。たとえば秋篠宮が皇嗣となって10年、20年後に兄の天皇ともども老年に達した場合、皇位の安定のためにも壮年となった悠仁親王と皇位継承順位を取り替えてはどうか、という意見が出てくるかもしれません」
声を上げるとたちまち議論百出となるのが皇室問題。冒頭の倉田氏は「皇位継承で一番大事なのは、波乱がないことだと思うんです」と案じている。おそらく宮内庁も、根回しをすすめながら、じっとタイミングを窺っているのだろう。
「週刊現代」2014年11月29日号より