2017年5月9日投稿
入札、契約制度について
地方公共団体における調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、より良いもの、より安いものを調達しなければなりません。
そのため、地方公共団体が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る調達方法である「一般競争入札」が原則とされています。一方、この原則を貫くと調達の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果として当初の目的が達成できなくなるなどの弊害が生じることがあり得ます。このため、「指名競争入札」や「随意契約」による調達が例外的な取り扱いとして認められています。さらに地域活性化の観点からは、地元企業が受注し地域経済に貢献することも求められており、この点も踏まえ調達がなされる必要があります。
以上について制度面からまとめると、地方公共団体の調達について定める地方自治法では、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則として掲げつつ、一定の場合には、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認められています。
また、地方自治法施行令では、入札に参加する者の資格要件について、事業所所在地を要件(いわゆる地域要件)として定めることを認めるとともに、総合評価方式による入札では、一定の地域貢献の実績等を評価項目に設定し、評価の対象とすることが許容されており、これらをもって地元企業の受注機会の確保を図ることが可能となっています。
さらに、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律において、地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならないとされています。
各地方公共団体においては、これらの規定を適切に活用していくことが求められています。
随意契約について
地方公共団体の調達は、競争性、透明性等を確保することが原則であり、住民の目から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことはあってはならないことです。
入札契約制度上、随意契約による方法で契約を締結できることは明らかですが、入札契約制度の運用において、広範囲にわたり、安易に随意契約を締結しているなど、必ずしも適切とはいえない事例があるのではないかとの指摘が行われるなど、住民に対して十分な説明責任を果たしているとはいえない状況にあります。
このため、入札契約制度の趣旨に沿った運用を確保し、もって、住民に対して十分な説明責任を果たすことが求められています。
http://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j27d08.pdf ここから引用です
公共事業の発注者は,「公正さを確保しつつ,より良いモノを廉価でタイムリーに調達する責任」を有
している(「発注者責任研究懇談会中間とりまとめ」1999年4月)。そのため,工事内容の特性に応じて,
落札者の評価要素や競争条件,施工者に求める仕事の範囲等の組み合わせを変え,多様な入札・契約方式
を活用することが求められている。特に,工事内容の難易度が高く,施工者からの技術開発の進展が予想
されるような工事については,価格のみならず,品質や技術の評価が重要である。
本稿では,まず日本の公共工事における入札・契約方式の特徴を整理し,それが公共工事の高コスト,
施工者選定の不透明性に繋がっていることを述べる。次に,公共工事をめぐる不祥事を契機に,手続きの
公正さの確立,品質確保,コスト縮減を目指して実施が進められつつある多様な入札・契約方式の導入状
況と,それぞれの方式の課題について概観する。これらの入札・契約方式の中には,導入後間もないため
十分な運用事例が少なく,どのような工事にどのような入札・契約方式が相応しいのかが明らかになって
いないものが多い。当初の意図通りに導入が進まない方式も含め,現時点での制度運用上の課題を整理す
ることとしたい。
札幌市は随意契約もネット公開して理由も記載されている
芽室町の隣り町 清水町の「広報しみず」で公開しています
芽室町も公開すべきです。個別のものは役場1階情報公開コーナーで誰でも閲覧できますが、インターネットの普及しているこの時代は札幌市のようにネット上での公開が透明、公平性の担保の為に必要と考えます
芽室町の場合 広報誌には掲載していません 各種団体が総会では細かくお金の使い方についてキチンと報告しています。税金をどのように使ったかを解り易く報告するのは行政の義務でありインターネットの普及でその作業にかかる手間は多くありません。




帯広市は個々の業者が幾ら受注しているか を公開しています。



帯広市の建設工事等入札心得 (平成 20 年 4 月 7 日改正)
(総則)
第1条 帯広市が発注する建設工事等の入札その他の取扱については、帯広市契約規則(昭和 39 年規則第 22 号)及び帯広市
工事執行規則(昭和 52 年規則第 28 号)その他の法令に定めるところによるものとします。
(入札の保証)
第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)は、入札執行前に見積もった入札金額の 100
分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提出しなければなりません。ただし、市を
被保険者とする入札保証保険証券を提出したときは入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提出するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付
のある承諾書を提出してください。
(入札等)
第3条 入札参加者は、仕様書、図面等を熟覧のうえ、入札しなければなりません。この場合において仕様書、図面等
について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができます。
2 入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
3 郵便による入札を指定したときは、入札しようとする者は、入札書を定められた方法で、一般書留郵便、簡易書留郵便又
は配達記録郵便のいずれかにより、提出しなければなりません。













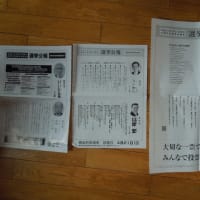

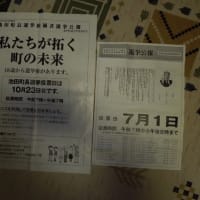

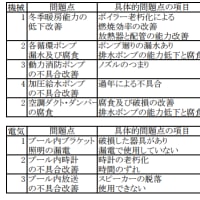
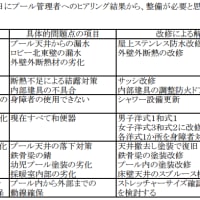
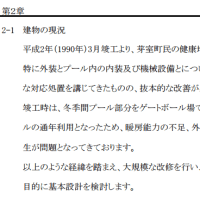


改革の秘策はあるのですが、なかなか切り込める勇気はないかな。勇気と知恵必要。
癒着としがらみのある町では難しい~