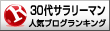プログラムに寄稿文の初稿が完成。
後は少しずつ完成度を上げていこう。文字数は少し2000字を過ぎているくらいなので、まぁ調整は不要であろう。
------------------------------------------
バレエの情景 ~シベリウスの“若気の至り”~
・日本における認知度(および筆者との出会い)
先日「バレエの情景」の公演が日本初演であることが判明した。後述するが、フィンランドの初演から約130年遅れての初演ということになる。
じっさい有名な曲とは思わないが、これまで日本で全く聴かれてこなかったことを意味するのか?という問いに対しては、いや、決してそうではない、と言っておきたい。
日本に音源が無かった訳ではないのだ。2005年頃、”ちょっと有名曲以外にもシベリウスの曲を聞いてみよう”と色気を出した、(当時大学生の)筆者が触れられる程度には世に流通していた作品である。
ただ、曲の情報は少なかった。曲の情報と感想を発信してくれる人は居なかった。今でこそ”バレエの情景 シベリウス”と検索すれば数人の熱心なファンのレビューを読むことも出来るが、
少なくとも筆者がこの曲に触れた2005年にはこれらの情報にアクセスできなかったし、私も殊勝にも先陣を切って世界に感想を発信する度胸もなかった。
大げさな言い方だが、本演奏を期により多くの人に聴かれるようになることを願う。
ご存知NAXOS、スウェーデンのレーベルであるBIS(このレーベルは本曲に限らずシベリウスのマイナーな作品をよく収録している)を中心に、
今は複数のオーケストラ・指揮者による演奏を聴くことが出来る。
・背景
シベリウスが作曲を始めたのはウィーンに留学中の1891年初頭からとされている。
当のシベリウスは26歳(?)、現代で言えば大学院生の習作のようなものである。
さて、ウィーンで自分の作品がより高い頻度で演奏されることを期待しつつ、
彼は交響曲の第2楽章として”バレエの情景”を作曲していた。
しかし、結果から言えばこの曲は交響曲の一部として演奏されることは叶わなかった。彼の言を借りれば、” Jag har mistat lusten att fullborda den af skäl att jag måste tillegna mig mera säkerhet i den gamla symfoniformen.
(古い交響曲の形式にもっと自信をつけなければならないという理由で、完成させる意欲を失ってしまったのです。)”ということである。
一方で作曲家デビューの期を伺っていたシベリウスは、譜面を単独でヘルシンキに送り、初演の準備を進めていた。彼は作品の出来が公演に耐えるものではないという不安も感じていたが、
彼を崇拝する男、ロベルト-カヤヌスがその不安を払しょくする。シベリウスこそがフィンランドの音楽を担う人物に成長すると信じて、
シベリウスを鼓舞し、1891年4月28日のポピュラーコンサートでバレエの情景は初演を指揮した。シベリウスは後にこのことを深く感謝している。
なお、この初演は、批評家からは” En vision, sällsam, demonisk; en pantomim med de mest fantastiska rekvisita.(幻影、奇妙な、悪魔のような、最も素晴らしい小道具を使ったパントマイム)”と評された。
”バレエの情景”という曲の批評としては不穏な言葉が並ぶが、その理由は次の段落で述べるようなものである。
・”バレエの情景”という題名と中身のギャップ
題名からして、大半の読者は明るい・軽快・優美・賑やかといったイメージをもって曲に臨むであろう。しかし、上記のイメージとはかけ離れた響きから本曲は始まる。
陰鬱・重い足取り。舞曲として聴くには違和感を禁じえない不穏さに包まれている。きっと聴衆の方も”バレエ”であるようには思われないだろう。曲が始まったらどうかこの解説は脇において、自分がどのように感じるかを確かめて欲しい。
それもそのはず、シベリウスは”バレエの情景”について師・友人にこのように述べている。
„Med balettscenen är det annat. Ett sorgligt, sorgligt minne ligger till grund. Det är något af ‘rus’ och ‘lår’ i den.(“バレエの情景”と言いますが、言葉通りの意味ではありません。根元には、悲しい思い出が眠っている。「陶酔」や「太もも」が内包されています。)”
“Det är svårt för mig att hitta på något motto. Jag satt en natt på ett horhus i Wien. Hororna dansade […] och blef till sist så der underbart vemodigt stämd – litet à la ‘o vanitas vanitatum vanitas.’ ‘Allt fåfängelighet’ Det är nu just det der att allt kött måste ruttna, alla menniskor, vore de än , bli as! …
私にはこの曲に標語を与えることは難しい。ある夜、私はウィーンの娼館に座っていた。娼婦たちは踊っていた(中略)
そして、最後には、私はとても素晴らしく切ない感動を覚えた、すなわち'o vanitas, vanitatum vanitas(無だ!無なのだ 空なのだ:ゲーテの詩)'という状態です。ここで起こっていることは全て虚無…
まさに、すべての肉体は腐り、すべての人間は、それが何であれ、灰となるのです。
色々大袈裟なことを言っているが、身も蓋もなくまとめてしまうと、「バレエの情景」という曲は、娼館の女性の踊りを眺めているうちに込み上げてきた退廃的な感傷・非現実感からインスピレーションを得た曲であると述べている。
人はモノを創り、あまりにも自分の個人的な事情が作品に反映されてしまった時には、これが自分のことであると悟られにくくするようにこういったオブラートを挟むものである。
これを頭に入れて曲をお聞きいただくと、題名に感じる違和感も消え失せ、きっと”バレエの情景”が頭に浮かんでくることであろう。
クレルヴォの前座としてはいささか尖った曲であるが、まだ若かったシベリウスの”こじらせ”を感じて頂きたい。