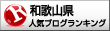◆生殖補助医療 いつから?
日本でも1983年に最初の成功例が報告されて以来、現在までに77万人以上の生殖補助医療(体外受精胚移植や顕微授精、凍結胚移植)による新生児が誕生しています。
◆2003年に厚生労働省の審議会が生殖補助医療法の制定を求める答申を出しました。
【答申(とうしん)】とは、上司の問いに対して意見を述べること、または諮問機関から行政官庁に対して意見を述べることを指します。
国内の卵子提供 2020年以降で少なくとも340人「ルール作成を」
2024年1月30日 19時59分
国内では必要なルールが整備されていないためこれまで主に海外で行われていた第三者からの卵子提供による妊娠・出産について、NHKが、卵子提供を仲介している複数の業者に取材したところ、2020年以降、少なくとも340人が国内で卵子提供を受けていたことが分かりました。
第三者から卵子の提供を受けて出産する「卵子提供」は国内では禁止されてはいないもののルールが十分整備されておらず、病気による不妊など一部のケースを除いて、主に海外に渡航して行われてきました。
NHKでは、日本人向けに卵子提供を仲介している複数の業者に国内での卵子提供を仲介したことがあるかについて取材しました。
その結果、7つの業者が国内での卵子提供を仲介したことがあるとし、これらの業者を通じて2020年以降、実際に国内で治療を受けた女性は、少なくとも340人に上ることが分かりました。
業者の多くはコロナ禍で海外への渡航が難しくなったことをきっかけに国内での仲介を始めたとしています。
国内での卵子提供をめぐっては具体的なルールがないことから▽安全性の確保や▽生まれてきた子どもの出自を知る権利の保障などの課題が指摘されていますが、これまでどの程度実施されているかなどの詳しい実態は分かっていませんでした。
生殖医療に詳しい慶応大学の吉村泰典名誉教授は「コロナ禍とはいえ、これだけ多くの人が国内で受けていたことには驚いた。現状では、提供を受けた人が周囲の人に話しにくかったり、生まれた子どもに事情を伝えにくかったりする。ルールやガイドラインを早急に作っていくべきだ」と話しています。
【抜粋】国内のルール 長らく整備されず
国内での卵子提供による出産をめぐっては、2003年、国の審議会の生殖補助医療に関する部会で「一定の範囲で容認する」とする報告書がまとまりましたが、同時に「必要な制度が整備されるまでは実施されるべきではない」などとする条件が付けられました。
しかし、このあと指摘された「必要な制度」は長らく整備されませんでした。
このため国内での卵子提供を禁止する法律などはないものの、関係者の間では実質的に「国内では実施できない」という認識が定着し、海外に渡航して卵子提供を受けるケースが広がっていました。
また、日本産科婦人科学会でも国内での卵子提供については見解を示しておらず、生殖医療の関係者からは「ルールがない中での実施には慎重にならざるをえない」という声が上がっていました。
こうした中、超党派の議員連盟が、卵子提供を含む生殖補助医療に関する法案作りを進めていて、今国会への提出を目指しています。
国内での卵子提供をめぐる議論では、▽提供を受ける女性や卵子を提供するドナーの健康や▽生まれた子どもの出自を知る権利の保障など、重要な課題が指摘されていますが、今回、こうした点についての議論が進む前に現実が先行する形となっていることが明らかになりました。
:118回虚偽答弁除名処分無し!「舌切り雀」安倍派政治資金⇒アベノミクス「選挙資金脱税事件!?」「見えないココロザシ・志」日本将来もうコリア国に抜かれている立法府「ウサギとカメ!?」「馬鹿にされてからの、挽回は三倍以上の努力必要!」KPOP腰切れ・・・トホホ!?