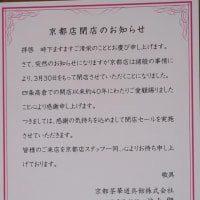今日は
ご縁のある方々と連れだって
八坂神社清々館と
知恩院真葛庵の
月釜に出かけました

朝十時ごろの八坂神社前

清々館
今日の席主は
正井風玄宗匠でした
寄付きの掛物は
曲水の宴を詠った画賛
本席の床には
利休道歌より
茶の湯には 梅寒菊に黄ばみ落 青竹枯木暁の霜
茶の湯における
陰と陽の調和を表現した句です
私は個人的に
この歌が表現している
茶の湯の精妙なる美の世界に
とても心惹かれます
しかし
どちらかというと
口切の頃に掛けられることが多いこの掛物
春爛漫のこの時期に
お使いになった
席主様のお心の内には
如何ような思いがおありだったのでしょうか・・・
お床に飾られていた
瀬戸の焼物の茶器
銘は「面壁」
蓋に面壁九年の達磨が
画かれていました
お床に置かれた
大ぶりな瓢の花入も
まだまだ
修行中でありまする・・・と
頑なに座り続けている
達磨の姿を連想させます
このひと月ほど
お席主は
体調を崩されて
しばらく入院生活を強いられていたそうです
きっと
本日のお道具組には
席主のお心内の様々な思いが
込められていたのでございましょう



円山公園の桜を愛でながら
知恩院へと向かいます

真葛庵は久田社中のお席でした
秋田の桜の皮でこしらえた
中次が使われていました
桜の皮独特の模様が美しく
ほんの少し丸みのある
優しい形の中次でした
蓋上には
尋牛斎宗匠が朱書きされた
桜の花びらが舞っていました
実は私も
今月のお稽古で
両親が以前秋田に遊びにでかけた折に
お土産で買ってきてくれた
樺細工の抹茶入れを
中次に見立てて使っているので
なんだかうれしくなりました