私は神戸市東灘区にある本住吉神社・例大祭で
毎年、だんじりを曳いている。

私の歴史への窓口はだんじりだ。
本住吉神社の由来や、なぜだんじりが始まったのかなど
歴史をつい探りたくなる。
ちなみに本住吉神社に祀られるのは神功皇后だ。
それだけで謎とロマン満載だ。
なぜなら神功皇后は卑弥呼だった説やら、
天照大御神だった説など、いまだに名だたる歴史学者が
束でかかっても解明できないでいる。

▲本住吉神社
神功皇后は、江戸時代までは「実在していた」といわれ、
明治時代にはお札にもなったが、戦後は神話の中の想像の人物だと
言われるようになった。
にもかかわらず、奈良市山陵町には神功皇后の墓がある。
だんじり熱が高じて、数年前に私は神功皇后陵を見に行った!

▲神功皇后陵
私はだんじりの曳き手でもあるので
本住吉神社が住吉神社の総本山であり、神功皇后は「実在していた派」だ。
多少史実と違っても(それは誰もわからかないのだが)
幾つかの都合のよい断片を繋ぎ合わせて「さもありなん」と信じている。
神功皇后陵をはじめ現存する多くの古墳は宮内庁管理となっており
発掘調査はおいそれと許可されない。
古墳の発掘調査は天皇家のルーツにも直結するので
「はい、はい」とすんなり宮内庁は許可できない。
それ故、仮説を繋ぎ合わせた憶測の域を越えられないでいる。
だからこそロマンとなり多くの古墳ファンを惹き付けるのだが、
宮内庁の管理する古墳の調査が行われれば、日本書紀や古事記、
魏誌倭人伝など紙で残る書物よりも長持ちする埋葬品
(銅鐸、鏡、埴輪、土器など)や、壁画などの解明で
一気に古墳時代が見える化することだろう。
私は古墳の発掘調査しかないと宮内庁の発掘許可を心待ちにしている。
先日、コロナ禍ではあったが、実家への陣中見舞いの帰り道
明石海峡大橋の本州側にある「五色塚古墳」に寄ってきた。
生まれも育ちも神戸っ子の私には、小学校の社会科の教科書には
必ず出てくるお馴染みの古墳だが、恥ずかしながら一度も見たことがない。
見学者用の無料駐車場完備の五色塚古墳。
まずはその巨大なフォルムに圧倒された。
日本で初めて整備された五色塚古墳は、全面を石(葺石)で覆う
巨大な前方後円墳だ。それまでのこじんまりとした円墳や方墳から
神功皇后の活躍した3世紀後半あたりから巨大な前方後円墳が出現してくる。
大きいほど目立つし、権威が誇れる。この時代は大和朝廷がまさに
起ころうとしていた時代で、巨大⇒強靭⇒権力があると結び付くからだろう。
国内最大の前方後円墳は大阪府堺市にある大山古墳(仁徳天皇陵)だが
五色塚古墳もかなりの大きさだ。

▲五色塚古風:墳陵長194m、高さ18.8m
では、なぜ私が五色塚古墳に行ったのか?
それは本住吉神社の歴史にある。
神功皇后は女性でありながら武勇に優れた女帝で
夫の仲哀天皇の死後、お腹に子供を宿したまま海を渡り新羅と戦った。
西暦201年のことになる。
そして戦いを終え、同年12月に九州で生まれたのが
後の応神天皇だとされている。ところが仲哀天皇には別に息子がおり
皇位を奪われるのではないかと不安にかられた息子たちが
畿内へ戻ってくる神功皇后の軍に対して挙兵し迎え撃とうする。
その拠点が五色塚古墳で、「仲哀天皇の陵墓」ではなく、
水路が狭い明石の地に建てた砦だった(という説もある)。
五色塚古墳のパンフレットには4世紀末~5世紀初頭の築造で
「この辺りの豪族の墓」とあるが定かではないとある。
したがって、神功皇后撃退の砦説や、仲哀天皇の陵墓説、
そしてこの辺りの豪族説など百花繚乱となる。
だがだんじり愛ゆえ、私は神功皇后撃退の砦説を信じたい。
確かに五色塚古墳に登ってみると、明石海峡はよく見通せる。
葺石も淡路産であることは確定している。


▲五色塚古墳から明石海峡は一望できる
結局、息子たちは神功皇后一行への攻撃はしなかった。
神功皇后一行は何事もなく奈良に通じる大和川のほとり
大阪市住吉を目指す。

ところが神功皇后の船が現在の西宮沖まで来ると
いっこうに船は進まなくなる。
するとそこへ天照大御神が現われ、
「底筒男命、中筒男命、表筒男命を社に祀れ」と啓示を受ける。
そこで神戸市東灘区の住吉の浜に船を止め、近くに社を建立した。
この底筒男命、中筒男命、表筒男命と神功皇后を祭ったの社こそが
私がだんじりを曳く「本住吉神社」だというのだ。
本住吉神社は西暦208年に建立され、
その後無事大阪湾を渡った神功皇后は大阪府の住吉に住吉大社を
西暦211年に建立された。3年の差があるのはリアルである。
本住吉神社の方が古い建立であり、本住吉神社が全国の住吉神社系の
総本山であると断言したのが、江戸時代の歴史家・本居宣長である。

明治政府の朝鮮半島植民地化の正当性を保証する論理のひとつとして
神功皇后の三韓征伐が使われたことで、神功皇后実在説が信じられ
やがて神功皇后が卑弥呼だと考えられるようになる。
私はそこまでは思っていないが、卑弥呼であれば面白いとは思う。
いずれにしても古墳発掘が許可されるまでは、推論を楽しむべし。
宮内庁の壁はおいそれとは崩壊しない。
それまでは、歴史のロマンを個々の夢想に。

















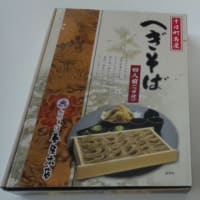


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます