今まさに携帯電話
日本では携帯電話の番号継続(ポータボリティ)制度が24日から開始。
ソフトバンクは、自社の携帯同士なら通話料とメール代が、一部の時間帯を除き全て無料になる新料金プランを26日から導入するとの発表があった。なんとなくこのフィリッピンのSUNセルラーみたいな戦略にも思えるのですが。
世界携帯電話加入者数は中国、インド、ロシアといったBRICs諸国を中心とした急速な増加で2003年末現在13億を超えた。世界全加入者13億のうち約3割を占める中国市場を除いては、ボダフォン、オレンジなど少数のメジャーキャリアが投資の形で世界各国へ進出し市場独占が強まる傾向。急速な携帯電話加入者増で2003年の携帯電話販売台数も5.2億台と予想を大幅に超え、2004年度は6億台弱に達した。
2004 年現在、世界携帯電話加入者数は13.5 億に達したが、総人口対普及率では21%に過ぎません。同市場は中国、インド、ロシア、ブラジルのBRICs新興市場が牽引し、今後5 年間二桁成長が期待され、2008 年には人口普及率34%の23 億加入者になると予測されます。一方、2003 年5.2 億台だった携帯電話端末市場は2008 年には9 億台にまで拡大すると予測されています。2005 年のメーカーによる携帯電話製造台数は約 7 億 2,000 万台に達し、前年比 5.8% 増。収益は、新規加入者や機種変更などを主として、約 1,120 億米ドル規模に。
世界最大市場の南北アメリカ。2005年は対前年比20.2%増の約2億5000万台。その半分以上は米国で販売された。
ブラジルの販売台数が増えたものの、まだ米国市場と1億台の差がある。
カナダ、メキシコを含めると北アメリカで7割に達する。まだまだ南北の差は大きい。2006年の南北アメリカ全体の販売台数は同7.9%増の約2億7000万台の見通し。そのうち米国は、同7.5%増の1億4530万台。 モトローラがシェア30%を占める
世界最大の経済大国である米国の携帯電話機の平均販売単価は意外に低い。第3世代機の普及も進んでいない。
「第3世代よりも先にスマートフォンが普及する。スマートフォンの販売台数は、2006年でまだ500万台程度だが、確実に台数が増えている
このようなニーズを把握するモトローラのシェアが30%と高い。2位は韓国のサムスン電子とフィンランドのノキア社が15%。
2006年のブラジルの携帯電話機の販売台数は、対前年比10.0%増の3850万台の見通しで、2005年までは40%増以上で成長していたが、一転して低成長。ブラジルで販売される端末は、モノクロ機が32%。カメラ付きは29%で、まだまだローエンド機の需要が強い。フィンランドのノキアのモノクロ機「1100シリーズ」が非常に人気がある。
2005年末時点のメーカー・シェアでは、モトローラが23%でトップだが、わずかに2ポイント差でノキアが続いている。3位は韓国のLG電子の15%、4位は韓国サムスン電子の13%。2005年後半には、韓国Pantech&Curitel社がシェアを拡大し、2005年末には10%近いシェアを獲得した。地球のちょうど反対側、ブラジルでは韓国勢が善戦している。
欧州で最大市場になったロシアモスクワだけが突出してハイエンド・モデルの需要が高い
2005年にイギリスを抜いてロシアが欧州の中で最大の市場になった。さらに2006年に、ロシアの携帯電話機販売台数は対前年比11.6%増の3850万台に拡大する見通しだ。ロシアは、液晶画面がモノクロの機種が20%も残っている。一方でモトローラの高級機種「RAZR」の販売が好調。機種の幅が非常に広い。これはモスクワだけ突出してハイエンド・モデルが売れているため。モスクワ以外の地域ではモノクロ機のニーズが高い。モスクワだけが特別。人口に比べて販売台数が多いのもモスクワの特徴。
ロシア市場のメーカー・シェアを見ると、フィンランドのノキアが約30%でトップ。2位は20%で韓国のサムスン電子。3位は、モトローラ、台湾のBenQ-Siemens社、英ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズの3社が10%前後で団子状態。
中国市場は失速、安定期へ 音楽機能の普及率が40%と高いのが特徴
2000年以降、世界の携帯電話機市場をけん引してきた中国。2006年は失速している。2006年の中国の携帯電話機販売台数は、対前年比5.0%増の約1億1500万台にとどまる見通し。2005年までの二桁成長から安定成長へ移行する。
GSM方式に需要集中
中国で販売されている機種は、液晶画面がカラーモデルが90%以上を占め、カメラ付モデルは55%。「中国では音楽機能の普及率が40%と高いのが特徴。2006年は携帯電話機向けメールマガジンがはやり始めてきている。
中国の携帯電話機は機能が豊富になり、日本の携帯電話機並みに。通信方式はGSM方式に集中している。CDMA方式の端末の販売台数は、2005年に600万台まで落ち込んだ。2006年は500万台を割り込む見通しだ。またPHS方式の端末の販売台数も減っている。2004年に3000万台以上だったが、2005年に2500万台まで減った。2006年は2000万台を下回る見通し。
インドではラジオとゲーム機能が必須 ノキアの牙城にモトローラが切り込む
2006年のインドの携帯電話機の販売台数は、2005年に引き続き対前年比50%増と大きく伸びる。その結果、世界の国別販売台数では、米国、中国に次ぐ日本を抜いて3位に入る。
売れている機種を見ると、米国や中国ほど単価の高い機種ではなく、液晶画面がモノクロのモデルが販売台数全体のうち40%と高く、逆にカメラ付モデルは20%にしかすぎない。機能の限られた安価な機種に人気が集まる一方、インド特有のニーズもある。「娯楽の少ないインドではラジオか音楽が必須機能になる。またインドで最も盛んなスポーツであるクリケットのゲームの有無が携帯電話機の売れ行きを左右するとまでいわれる。
フィリピン相変わらず3G機種が好調に売れている。なんといってもNOKIA
1999年にプリペイドカード方式が導入され、手軽にテキスト送信できるSMSのサービスが提供開始されてから、携帯電話の加入数は急激に増加、1年後の2000年には携帯電話の普及率は固定電話の普及率を上回ってしまった。その後も右肩上がりの上昇を続け、2004年末時点での携帯電話加入者数は約3,000万人に達し、契約1件につき利用者を1人と仮定した場合、フィリピン人口に対する携帯電話の普及率は30%以上に急増。2005年末には携帯電話の普及率が45~50%に達し、市場拡大は今後もますます続きそうな勢いをみせている。携帯電話事業者最大手のスマートを見ると、2001年末時点に489万3,800件だった契約数が2004年9月末時点には子会社のピルテルとあわせて1,750万件を突破した。携帯電話事業者第2位のグローブも同時期に1,170万件に達し、新規参入事業者のサンセルラーも80万件を記録している
PLDTグループ スマート・コミュニケーションズ 1,331万件 44%
ピリピノ・テレフォン(ピルテル) 419万件 14%
アヤラ財閥 グローブ・テレコム 1,170万件 39%
ゴゴンウェイ財閥 サンセルラー 80万件 3%
全世界の加入者数13億台中フィリピンの加入者台数3000万人。ますます加入者が増加しているフィリピン。さすがに電話好きな民族であることが理解できるような数値でもあります。
だんとつでNOKIAのユニットに人気があるフィリピン。機種のバリエーションではこのフィリピンが世界一コレクター的な市場でもあるかも知れない。すなわち何でも売れる市場なのかも。
世界最大市場の南北アメリカ。2005年は対前年比20.2%増の約2億5000万台。その半分以上は米国で販売された実績からして、このフィリピンの実績は「恐れ入りました。」ほどの需要国であることは間違いないのかも。
フィリピンで事業展開を考えていらっしゃる方、事業方法をよく調査、携帯電話販売等の権利をもたれたほうが安定した事業ができるかもしれません。
このフィリピンはチャンゲ携帯の電話ショップが多くありますが、最近、パンパシフィックホテルのマカティスクエアー内に韓国人が出展した携帯電話専門店のように、ある程度外国人に引っ付きまわるおねーちゃんをターゲットにした携帯電話店も面白いかも知れません。資金力があれば、在庫数も多く展示でき、客のニーズを捉えることができるのは世界中まったく同じようにも思えます。小間物始め客のニーズにあった商売方法であれば、飲食業を経営するより高収益が上げられると思うのですが、いかがなものでしょうか「日本人殿」
もう遅いといわれる方もいるようですが、携帯電話市場はますます進化していくと思います。
日本では携帯電話の番号継続(ポータボリティ)制度が24日から開始。
ソフトバンクは、自社の携帯同士なら通話料とメール代が、一部の時間帯を除き全て無料になる新料金プランを26日から導入するとの発表があった。なんとなくこのフィリッピンのSUNセルラーみたいな戦略にも思えるのですが。
世界携帯電話加入者数は中国、インド、ロシアといったBRICs諸国を中心とした急速な増加で2003年末現在13億を超えた。世界全加入者13億のうち約3割を占める中国市場を除いては、ボダフォン、オレンジなど少数のメジャーキャリアが投資の形で世界各国へ進出し市場独占が強まる傾向。急速な携帯電話加入者増で2003年の携帯電話販売台数も5.2億台と予想を大幅に超え、2004年度は6億台弱に達した。
2004 年現在、世界携帯電話加入者数は13.5 億に達したが、総人口対普及率では21%に過ぎません。同市場は中国、インド、ロシア、ブラジルのBRICs新興市場が牽引し、今後5 年間二桁成長が期待され、2008 年には人口普及率34%の23 億加入者になると予測されます。一方、2003 年5.2 億台だった携帯電話端末市場は2008 年には9 億台にまで拡大すると予測されています。2005 年のメーカーによる携帯電話製造台数は約 7 億 2,000 万台に達し、前年比 5.8% 増。収益は、新規加入者や機種変更などを主として、約 1,120 億米ドル規模に。
世界最大市場の南北アメリカ。2005年は対前年比20.2%増の約2億5000万台。その半分以上は米国で販売された。
ブラジルの販売台数が増えたものの、まだ米国市場と1億台の差がある。
カナダ、メキシコを含めると北アメリカで7割に達する。まだまだ南北の差は大きい。2006年の南北アメリカ全体の販売台数は同7.9%増の約2億7000万台の見通し。そのうち米国は、同7.5%増の1億4530万台。 モトローラがシェア30%を占める
世界最大の経済大国である米国の携帯電話機の平均販売単価は意外に低い。第3世代機の普及も進んでいない。
「第3世代よりも先にスマートフォンが普及する。スマートフォンの販売台数は、2006年でまだ500万台程度だが、確実に台数が増えている
このようなニーズを把握するモトローラのシェアが30%と高い。2位は韓国のサムスン電子とフィンランドのノキア社が15%。
2006年のブラジルの携帯電話機の販売台数は、対前年比10.0%増の3850万台の見通しで、2005年までは40%増以上で成長していたが、一転して低成長。ブラジルで販売される端末は、モノクロ機が32%。カメラ付きは29%で、まだまだローエンド機の需要が強い。フィンランドのノキアのモノクロ機「1100シリーズ」が非常に人気がある。
2005年末時点のメーカー・シェアでは、モトローラが23%でトップだが、わずかに2ポイント差でノキアが続いている。3位は韓国のLG電子の15%、4位は韓国サムスン電子の13%。2005年後半には、韓国Pantech&Curitel社がシェアを拡大し、2005年末には10%近いシェアを獲得した。地球のちょうど反対側、ブラジルでは韓国勢が善戦している。
欧州で最大市場になったロシアモスクワだけが突出してハイエンド・モデルの需要が高い
2005年にイギリスを抜いてロシアが欧州の中で最大の市場になった。さらに2006年に、ロシアの携帯電話機販売台数は対前年比11.6%増の3850万台に拡大する見通しだ。ロシアは、液晶画面がモノクロの機種が20%も残っている。一方でモトローラの高級機種「RAZR」の販売が好調。機種の幅が非常に広い。これはモスクワだけ突出してハイエンド・モデルが売れているため。モスクワ以外の地域ではモノクロ機のニーズが高い。モスクワだけが特別。人口に比べて販売台数が多いのもモスクワの特徴。
ロシア市場のメーカー・シェアを見ると、フィンランドのノキアが約30%でトップ。2位は20%で韓国のサムスン電子。3位は、モトローラ、台湾のBenQ-Siemens社、英ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズの3社が10%前後で団子状態。
中国市場は失速、安定期へ 音楽機能の普及率が40%と高いのが特徴
2000年以降、世界の携帯電話機市場をけん引してきた中国。2006年は失速している。2006年の中国の携帯電話機販売台数は、対前年比5.0%増の約1億1500万台にとどまる見通し。2005年までの二桁成長から安定成長へ移行する。
GSM方式に需要集中
中国で販売されている機種は、液晶画面がカラーモデルが90%以上を占め、カメラ付モデルは55%。「中国では音楽機能の普及率が40%と高いのが特徴。2006年は携帯電話機向けメールマガジンがはやり始めてきている。
中国の携帯電話機は機能が豊富になり、日本の携帯電話機並みに。通信方式はGSM方式に集中している。CDMA方式の端末の販売台数は、2005年に600万台まで落ち込んだ。2006年は500万台を割り込む見通しだ。またPHS方式の端末の販売台数も減っている。2004年に3000万台以上だったが、2005年に2500万台まで減った。2006年は2000万台を下回る見通し。
インドではラジオとゲーム機能が必須 ノキアの牙城にモトローラが切り込む
2006年のインドの携帯電話機の販売台数は、2005年に引き続き対前年比50%増と大きく伸びる。その結果、世界の国別販売台数では、米国、中国に次ぐ日本を抜いて3位に入る。
売れている機種を見ると、米国や中国ほど単価の高い機種ではなく、液晶画面がモノクロのモデルが販売台数全体のうち40%と高く、逆にカメラ付モデルは20%にしかすぎない。機能の限られた安価な機種に人気が集まる一方、インド特有のニーズもある。「娯楽の少ないインドではラジオか音楽が必須機能になる。またインドで最も盛んなスポーツであるクリケットのゲームの有無が携帯電話機の売れ行きを左右するとまでいわれる。
フィリピン相変わらず3G機種が好調に売れている。なんといってもNOKIA
1999年にプリペイドカード方式が導入され、手軽にテキスト送信できるSMSのサービスが提供開始されてから、携帯電話の加入数は急激に増加、1年後の2000年には携帯電話の普及率は固定電話の普及率を上回ってしまった。その後も右肩上がりの上昇を続け、2004年末時点での携帯電話加入者数は約3,000万人に達し、契約1件につき利用者を1人と仮定した場合、フィリピン人口に対する携帯電話の普及率は30%以上に急増。2005年末には携帯電話の普及率が45~50%に達し、市場拡大は今後もますます続きそうな勢いをみせている。携帯電話事業者最大手のスマートを見ると、2001年末時点に489万3,800件だった契約数が2004年9月末時点には子会社のピルテルとあわせて1,750万件を突破した。携帯電話事業者第2位のグローブも同時期に1,170万件に達し、新規参入事業者のサンセルラーも80万件を記録している
PLDTグループ スマート・コミュニケーションズ 1,331万件 44%
ピリピノ・テレフォン(ピルテル) 419万件 14%
アヤラ財閥 グローブ・テレコム 1,170万件 39%
ゴゴンウェイ財閥 サンセルラー 80万件 3%
全世界の加入者数13億台中フィリピンの加入者台数3000万人。ますます加入者が増加しているフィリピン。さすがに電話好きな民族であることが理解できるような数値でもあります。
だんとつでNOKIAのユニットに人気があるフィリピン。機種のバリエーションではこのフィリピンが世界一コレクター的な市場でもあるかも知れない。すなわち何でも売れる市場なのかも。
世界最大市場の南北アメリカ。2005年は対前年比20.2%増の約2億5000万台。その半分以上は米国で販売された実績からして、このフィリピンの実績は「恐れ入りました。」ほどの需要国であることは間違いないのかも。
フィリピンで事業展開を考えていらっしゃる方、事業方法をよく調査、携帯電話販売等の権利をもたれたほうが安定した事業ができるかもしれません。
このフィリピンはチャンゲ携帯の電話ショップが多くありますが、最近、パンパシフィックホテルのマカティスクエアー内に韓国人が出展した携帯電話専門店のように、ある程度外国人に引っ付きまわるおねーちゃんをターゲットにした携帯電話店も面白いかも知れません。資金力があれば、在庫数も多く展示でき、客のニーズを捉えることができるのは世界中まったく同じようにも思えます。小間物始め客のニーズにあった商売方法であれば、飲食業を経営するより高収益が上げられると思うのですが、いかがなものでしょうか「日本人殿」
もう遅いといわれる方もいるようですが、携帯電話市場はますます進化していくと思います。

























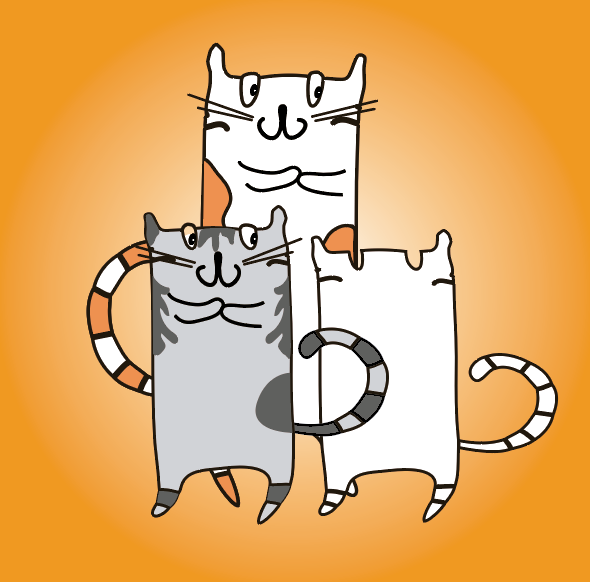

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます